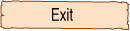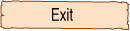Luc Besson監督作品 The Fifth Element
- Nikita、Leonに続く「愛と暴力の3部作完結編」である。と勝手に決めさせて頂いてもいいだろうと思う。Nikitaは泣き虫な女殺し屋と彼女に思いを寄せる優しき男、Leonは基本的には情にもろい男殺し屋と彼に思いを寄せる少女の物語であった。今回は完全無欠な女性と完全無欠な男性の二人(女性の方は生物学的にはヒトではないと思うのだけれども、とりあえず外見に従おう。)によって織りなされる愛と暴力の物語である。「3部作完結編」と呼ぶ由縁はここにある。
- 但し、ここで重要なのは二人とも物語の冒頭からから完全無欠というわけではなくて、「崇高な存在supreme being」であるリールー(Leeloo)という略称を持つ女性には「か弱さ」という弱点があるわけだし、ブルース・ウィリスが演じる完全無欠のスーパー・ヒーロー、コーベン・ダラス(Korben Dallas)もどうやら妻には愛想を尽かされ、軍隊も解雇され、タクシー運転手としても免許剥奪寸前まで追い込まれているというような、「本当の愛」を知らない筋肉だけの男なのである。物語を通じて、リールーはコーベンに愛を教え、コーベンは肉体をもってリールーを守る。ここではある意味で女性と男性の相互補完性が表現されている訳だ。ここではこの作品で第5番目の要素の力を解き放つために用いられる言葉あるいは感情である「愛」が、キリスト教的なアガペーでもプラトン的な「愛」(ギリシャ語でなんていうんだっけ?アガペーだったりして。)でもなく、どちらかといえばフロイトが死の欲動であるタナトスと対立させた生の欲動であるエロスの意味で用いられていることを述べておかねばなるまい。もこのことは後に述べる本作品と庵野秀明の『新世紀エヴァンゲリオン』との対立的な関係とも関わる重要なポイントである。
- さて、話を戻そう。一昔前までのハリウッド映画その他では女性は徹底的に男性によって守られるべきものであったのだが、そんな図式は当然今日では通用しない訳で、リールーは必然的に「強い」ものとして描かれることになる。彼女に欠けているのは不在であった5,000年間の地球の歴史に関する知識と、与えられるものとしての「愛」であり、これらが備わることによって、究極兵器として完成する。コーベンは肉体的には完全なので異星人の物理的な攻撃で死んだり傷ついたりはしないけれど、与えるべきものとしての「愛」を知らないこと、要するにここでは「愛」する能力とほぼ同義であるという想定があるはずの「思慮」あるいは「知恵」を欠いていることにより、「完全な悪」からの攻撃を受けている地球を危うく滅亡させそうになってしまう。ここではグノーシス主義や、新グノーシス主義、及びその影響下にあるベーメ神学を応用したフィリップ・K・ディックの『聖なる侵入』(創元文庫刊)における「墜ちた神」イマヌエルと、その分身である「聖なる知恵(ハギア・ソフィアあるいはロゴス)」であるジナ=シェキナの物語を想起しよう。本映画ではほぼこの図式が踏襲されていて、ラストは明らかにイマヌエルとシェキナの合体=聖なる結婚による「マクロコスモス的なシュジギ」への止揚を表現していることになる。要するに、無知なる肉体に知恵が吹き込まれることによって人間となる、というユダヤ・キリスト教及びグノーシス主義に共通する人間観が、グノーシス主義への傾斜を示しつつ、幾分の変節を加えられながら踏襲されているということである。
- さて、ユダヤ・キリスト教の文脈では男性として描かれる神が生命を、邪悪なものとして描かれる蛇が知恵をそれぞれ与えることになってしまったために、女性はグノーシス主義が説く知恵の源泉としての地位を追い落とされてしまい、男性よりも自然に近くそれ故に男性より劣位なのだ、というような思考を産み出し、これが今日まで続く性差別の源泉となった、というような議論がある。まあ、これはイデオロギーが社会を作る、というロジックに従えば、という話であって、実際のところは全く逆に性差別という社会的事実が先にあって、そこから性差別的な教義体系が産み出された、という見方も出来るのだが、どちらが正しいかを決めることはとても困難なことで、これは社会学者その他が古くから大いに悩んできた問題でもある。とりあえずベッソンは、両性の、非対称的ながらもかなり平等な相互補完的な意義を認めるグノーシス主義に近い図式を展開しているように見え、このことからユダヤ・キリスト教の持つ、フェミニスト神学などが問題にしているような性差別性は感じられないのは事実である。
- しかし、良く目を凝らすならば色々と問題点が見えてくる。例えば第5番目の要素=究極兵器であるリールーが放つビームからは男根中心主義(ファロサントリズム)が感じとれるだろう。これこそが1970年代あたりから例えばフロイトのそれこそファロサントリックな精神分析学に対する批判として現れてきたポストモダン・フェミニズムがその批判の対象としてきたものである。あんなありきたりなものではなくて、もっと意外な戦い方をして貰いたかったと思う。例えばリールーが「絶対的な悪」を飲み込んじゃうとか。ちなみに同じく石集めの物語である『ドラゴン・ボール』の初期には大魔王を電子ジャーに封じ込める、なんていう卓抜なものがあった。ベッソンも多分見ているはずだから、応用してもう一ひねり欲しかったと思う。ブルース・リーがある場面で映し出されたり、リールーがカンフー・アクションをすることなどからも分かる通り、ベッソンが「東洋的なもの」を取り込もうとしているのは間違いないのだから。ファロサントリズムを出したついでに言うと、ラストのショットでコーベンがリールーの上に乗っていたのはまずいのではないだろうか。何しろ、リールーは「至高の存在」だったはずである。コーベンはそれすらも弁証法的に乗り越えてしまったとでも言うのであろうか?そもそも、「風は吹く。」「雨は降る。」「火は燃える。」「地は?。」式に解釈すると、話の展開上「完全な女性性」である「リールーは愛される。」ということになるわけで、これでは女性の「主体」はどうなってしまうのだ?、「愛する」ことは出来ないのか?というようなポストモダン・フェミニズムを持ち出すまでもない素朴な疑問が起きてくる訳だ。
- もう一つの問題は、本作品では前作に強く現れた「人種」あるいは「エスニシティ」の問題がさらに強い形で表現されていることである。Leonはアメリカ合州国におけるマイノリティであるイタリア系移民のお話であった訳で、エスニシティを巡る諸問題が方々に散りばめられていたように思う。あの作品は確かによく出来ているけれど、例えばフランシス・F・コッポラの「ゴッド・ファーザー」シリーズ同様にイタリア人=暴力的というイメージの浸透に少なからず貢献してしまったことは否定出来ないだろう。本作品では、Independence Day同様に地球を守るのがアメリカ合州国大統領指揮下の軍隊であることはベッソンがフランス人であることを考えると別に問題ないのだが(ほとんど揶揄に近いパロディだろうか?)、余り重要な働きをしていない米国大統領が黒人であるというのはちょっとまずいのではないかと思う。これだけならいいのかも知れないが、悪役の異星人は地球人の(あるいはベッソンの)美的感覚からして醜いとされる。これは人種差別や民族差別の常套手段である。地球を救う二人は白人であり、さらに言えば「完全な女性性」を持つとされるリールーが白人であることは非常に気になる。そもそも、地球を救う究極の兵器に関する伝承をキリスト教の僧侶が継承している、という設定も非常に気になる。また、ゲイリー・オールドマンの演ずるイマヌエル(!!!)・バプチスト・何とかかんとか・ゾーグ(Zorg)の手下に黒人が多いことも非常に気になる。ファンキーな狂言回しである黒人DJが性的倒錯者として描かれていることも非常に気になる。そもそも、リールーが学ぶ地球の歴史はパソコンに「英語」のキーワードを打ち込んで得られるものであって、The dictionary of global culture(Kwame A. Appiah & Henry L. Gates,Jr.(eds),Knopf,1997)のような書物が編纂されるポスト・コロニアルな状況下で、ベッソンがどうやら「地球の歴史は西洋の歴史であり、西洋の歴史は地球の歴史である。」というような命題に忠実に従っているらしいことは、ちょっと信じがたいことである。それだけコロニアリズムは打ち壊しがたいものということなのかも知れない。以上、ベッソンって、実はすごく保守的な人なのでは?などと考えてしまった。
- とりあえずは単純な娯楽作品なのだけれど、いろいろと考えさせられる。今日においては作品を作ることが政治的なことであること、あるいは政治的でない作品を作ることなどなどそもそも不可能であることがはっきりしてしまっている訳で、映画作りが実に難しい作業であることを再認識させられた。特に、人類の救済みたいな巨大なテーマを扱うことにおいては、「政治的に良くない」表現を回避することは大変難しい。
- 最後に、誰でも気付くだろう『エヴァ』との類似点と相反する点について述べよう。類似点の第1は大したことではないのだが、リールーと悪役異星人との戦いは明らかにリドリー・スコット監督作品The Blade Runnerの引用なのだが、同時にまた『エヴァ』完結編におけるアスカが搭乗する弐号機のカンフー・アクション的な戦闘シーンを想起させるものである。第2点は、こちらの方が重要だが、本作品もまた必ずしも完全ではない男女二人の物語であることである。ある種の相互補完性、『エヴァ』ではむしろ相互依存性とみなされるものによってこそ人は人たりうる、あるいはそれらによってしか人は人たり得ない、というメッセージを共有しているように思う。但し、本作品は『エヴァ』とは全く対照的な、オプティミスティックな終結を迎える。これは先に書いた通りである。シンジとアスカは不完全なまま残される訳で、恐らく本作品におけるような「聖なる結婚」には至れないのである。加えてもう一つ、『エヴァ』完結編では人間の魂を飲み込む「黒い月」が地球内部からせり出してくるわけだが、本作品では明らかに「悪」とみなされるやはり黒い球状の物体が太陽系外から接近してきて地球を危機に陥れる。このあたり、内部と外部、あるいは自己と他者をはっきり区別するとされる西欧的あるいはユダヤ・キリスト教的思考法と、自己と他者が未分離で、同時に善と悪もそれほど明瞭に分離しないとされるグノーシス主義的あるいは東洋的な思考法の根本的な対立の発露、と見なせないことはない。私個人としては西洋と東洋を単純に二分割するのは好きではないのだけれど。
- ちょっと大げさになりすぎた。この辺で終える。ちなみに面白さは保証します。徹夜明けでも全然眠くなりませんでした。(1997/10/07。10/08にかなりの加筆。)