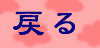物語は至って簡単にして暗澹としたもの。そう、これがミュージカルでなかったらどうなっていたのか、などということを考えてしまう殆ど絶望的なストーリーである(まあ、それはそれでBreaking the Waves(邦題『奇跡の海』)を撮った同監督の本来の持ち味なのだけれど…。)。概略を簡潔に記すと、アメリカ合州国(「合衆国」としか変換されないAtokの辞書は間違っている。くどいけれどきちんと指摘しておく。)在住のチェコ・スロバキア移民(字幕では「チェコ」になっていたが、正しくはチェコ・スロバキア。これは両国が分離する前の話なのだ。だからこそ、主人公・セルマ Selma は「共産主義者」のレッテルを貼られることになる。翻訳者は、この辺の事情を理解していない。)にして恐らくは未婚の母という設定のセルマが、自分の命と引き替えに息子(ジーン Gene という名前である。誰でもお気付きのようにGene Kellyからとられている。遺伝子という意味もあるけれど、それは深読みでしょう。)の視力喪失を防ぐ、というものである。
セルマの人生は悲惨の一言で言ってのけられる。遺伝するいずれは失明に至る眼病を患い、移民、シングル・マザーその他には冷たい合州国の保険制度下では高額の手術費用(セルマが貯えたのは取り敢えず2,056ダラーズ10センツ。何度も出てくるので覚えてしまった。この額が高額だということや、セルマがモノクロームのミュージカル映画を観ていること、またセルマの借りているトレーラの所有者(The Green Milesでも看守役をやっていたDavid Morseが演じている。本作では警官役である。)がCDデッキではなくリコード・プレイヤで音楽を聴いていることなどから、この物語がちょっと前の話だということが分かる。)を捻出するのもままならない。更には自分自身はちっとも悪くないのに強盗殺人の嫌疑で死刑判決を受け、これまたマイノリティを冷遇する合州国の司法制度によって、まともな控訴審も行なわれることなく(それはセルマの意志でもあるのだが…。)、セルマはそれこそあっけなく絞首刑に処せられ(このラスト近い監房から処刑場までに至る「107歩の行進」(間違っても「365歩」ではない。)の場面が素晴らしい。ただ数を数えながら歩く、というシーンなのだが、物凄い演出で圧倒する。ちなみに107は素数である。)、「最後の歌」を終わりまで歌うことすら許されず、文字通り息の根を止められる。
この暗澹たる物語に光明を与えているのが(とは言え、それが幻想である事がこの物語を一層悲惨なものにしている、という見方も可能ではある。)、視力を失いつつあるセルマが「見る」自ら歌い・踊る白昼夢なのであり、この部分が本作をミュージカル映画に仕立てている。作中でも述べられている通り、ミュージカルにおける〈突然歌い出し、踊り出す〉、というパフォーマンスの在り方は、基本的にリアリズムの対極をなす。1960年代以降、ミュージカル映画が衰退し、ハリウッド映画においてさえもリアリズムが追求されることになっていくのは映画史上の常識であるけれど、私自身もそうなのだが、映画人や評論家の一部は、ミュージカル映画こそを映画の究極の形態と考えているのであって、彼等は可能ならばいずれはミュージカル映画を撮りたい、或いは新しいミュージカル映画を観たいという願望を抱いているのである。それでは今日においてミュージカルはどのような形で可能なのか、という問いに対する一つの解答が本作品である。即ち、唐突な歌・踊りを、ミュージカルへの憧憬止むことのないセルマの見る「白昼夢」として挿入し、そうすることによってリアリティを確保しつつ、ミュージカルについてのミュージカルを作ればいいのだ、というのが本作を創り上げたスタッフの導き出した答えであり、本作はその点でメタ・ミュージカルなのだ。
尚、見事なバランスと構成を持ったメタ・ミュージカル映画を創出した、というその点だけでも充分にエポック・メイキングな作品なのだけれど、本作の価値はやはり何と言ってもBjorkのパフォーマンスに尽きる。自ら作詞・作曲・編曲した楽曲を歌い、それに合わせて踊るのみならず、悲惨な人生を余儀なくされた一女性を見事に演じ切ったこの稀代の天才パフォーマーの演戯を、堪能しよう。これはFaye Wongも、Micheal Jacksonも、Madonnaもなし得なかったことだ(美空ひばりはいい線行っていた。)。本当は惜しみない拍手を送りたかったのだが、さすがに恥ずかしいので出来なかった。私の拍手もまた、闇の中で響かせるに留めようと思う。(2000/12/29)