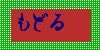舞台は九州北部。昨年5月に現実に発生してしまったバス・ジャック事件を予知していたかのように、この作品における物語の発端は1995年(これは「2年後」と明示された本作品の大部分を占める映画内時間において、サッカーの1998年W杯フランス大会・アジア地区予選が行なわれていることから分かる。そうすると、冒頭のバス内のシーンで、吊り広告に撮影時が1999年を意味する文字が刻まれていたことは、些細とは言えうっかりしたミスである。気付く方も気付く方だけれど…。)に西鉄の巡行バスで起きたバス・ジャック事件ということになる。計6名が死亡したこの事件の3名の生存者(役所広司演ずる運転手・沢井真と、宮崎将・あおい兄妹が演ずる田村直樹・梢兄妹。)と、斉藤陽一郎演ずるその兄妹の従兄弟・秋彦(この人物も別の事件によるトラウマに苦しんでいる。)が共同生活を始め、それぞれが持つトラウマをそれぞれに解消していくプロセスを描いていく。彼等が孤立性の高い共同生活を余儀なくされるのは、世間がそうした事件の与える後遺症というものを過小視しており、というよりはむしろそうした事件と関わったという事実から彼等に全く無根拠な周縁性を与えてしまい、数少ない理解者はいるものの、結局トラウマからの脱却は自らなさねばならない状況に追い込まれたことによる。何とも切ない話だが、これは殆ど現実なのではないかと想像する。1995年に日比谷線に乗り合わせてサリンを浴びた私の父親は、全くトラウマを抱えていないように見えるのだが、村上春樹の著述などを思い起こしつつ、被害者問題というのは社会全体が一丸となって取り組むべき課題なのではないかと改めて思った次第。
ちょっと脱線してしまったが、話を戻すと、本作品はある種集団療法や家族療法の持つ可能性に言及しながら、同時にまた現実はそれほど甘くはないことも指し示すことになる。トラウマを抱えている4名が揃いも揃って恢復する、などという現実にはあり得べくもない大団円はこの作品においても訪れ得ず、1名は連続殺人事件の被疑者として収監され、1名は共同生活から脱落し、1名は恐らく肺癌によって近い内に死亡するだろうことが暗示される。ということは残りの1名にはそれなりの救済が与えられたことがラストで示されるのだけれど(とは言え、さほど明るい未来が待ち受けているとも思えないところが何とも切ない。)、ほぼ全編がモノクロームで撮影されたこの暗澹たる作品に与えられる文字通り一筋の、ほんの一筋の光明は、誠に感動的なものである。
尚、以下蛇足だが、劇中で用いられるBGMにはChicago音響派のリーダー的存在であるJim O'Rourkeの作品が使われている。これを持ち出した仙道氏のセンスには感心してしまう(仙道氏の提案ではないかも知れないけれど。)。仙道氏と言えば少し前までその妻であった河瀬直美監督の『萌の朱雀』が思い起こされるが(4年振りの新作『火垂』が間もなく公開される。期待したい。)、同作品に主演した今後間違いなく開花するであろう仙道氏の秘蔵っ子的存在・尾野真千子は沢井真の妹役で出演し、その色々な意味での成長を見せてくれる。まあ、何はともあれ、日本映画界が世界に誇る役所広司(既に森雅之を超えたかも知れない。)の相変わらずの余りにも素晴らし過ぎる演技を堪能するためだけにでも、一見の価値のある作品である。(2001/03/12)