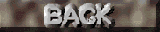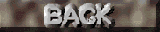Peter Greenaway監督作品 The Pillow Book
- P.グリーナウェイはずいぶん前に出た『イメージフォーラム』の別冊の中で、「『枕草子』を映画化するんだ。」、というようなこと語っていたが、1995年に完成したようで、ようやく日本でも上映の運びとなった。『数に溺れて』、『Zoo』、『プロスペローの本』でも示された、この人の博物学的、あるいは百科全書的な知識への傾倒ぶりは今回も明瞭に現れている。どうやらこの人はM.フーコーのいうような意味での古典主義時代の知識というものこそが真の知識であると考えているようで、清少納言の筆による『枕草子』にもそれを見出したようだ。すなわち、この世界のありとあらゆることを、言葉に置き換えること。それも、可能な限り一対一の関係を保ちながら。というようなことがそこでは行われていると、英訳を読んだであろうグリーナウェイは解釈したらしい(付け加えると、それを女性が記したという点が重要だというようなことを朝日新聞のインタヴューでは述べていた。)。もちろんそんなことが不可能だということは、記号が事物との一対一の関係を廃棄して一人歩きをしているような「近代」という名の牢獄に捉えられたしまっている我々には自明に見えてしまうことなのだが、グリーナウェイはあくまでもそういう近代的な知や認識の在り方に抗おうとするかのようである。
- では、その方法はいかに、ということになるのだが、これまでの諸作品はそれなりに納得のいくものであったのに対して、この作品での試みは正直言って現時点では私の理解の範囲を超えている。以下に示すのは、本作品を巡ってつれずれなるままに考えたほんの些細なよしなしごとである。
- この映画の主人公は清少納言(Nagon)からものすごい変形をなされた清原諾子(Nagiko、以下ナギコ)いう名前を持つ日本人と中国人(香港人かも知れない)を両親に持つ京都(グリーナウェイの考えでは日本文化は京都という場所によって代表しうるということなのだろうか?)生まれの女性である。「納言」は役職名なのだから、本当は彼女の固有名の「清」の部分を取って「清子」とでもすれば良かったと思うのだが、こうしたひょっとしたら意図的かも知れない勘違いは他にも随所に見られ、むしろグリーナウェイはそれを楽しんでいるようなので放っておいてもいいのかも知れない。彼女は清少納言に倣って日記を付けていくのだが、様々な事件を経て何故か香港に移住し(この辺りについては、自国の領土内でなるべく撮影を済ませたかった、という英国映画界の政治・経済的な事情を邪推させられる。)、そこで自分の書いたものを出版すべく、かつて父と同性愛的関係にあった日本人の出版者(タイトルではpublisherとなっていた。固有名はここでも簒奪されている。この人の描かれ方は欧米の映画で良く見受けられる日本人ヤクザの描かれ方を踏襲している。以下、出版者とあれば彼のことである。)に、彼と現在同性愛的関係にある英国出身の若者を通じて接触するのだが、その際に出版者に原稿を読ませるために自分の書物を若者の体の表面に書き込むという方法を用いる。
- ここで行われているのは、身体の言語化でもなければ、言語の身体化でもない。言葉が書かれるのはあくまでも身体の表面であるし、その言葉はあくまでも文字によって表現される。ここでは、身体の内部に書き込むという発想は明らかに意図的に排除されている。すなわち、死んでしまったナギコの恋人の内臓は、出版者の手によって文字が書き込まれた皮膚を除去された後に、清掃車にゴミとして投げ込まれるというシーンが描かれているし、体の隠れた部分に書き込まれることはあってもせいぜい舌位までであるし、ましてその書の文面や映像を脳裏にしまい込んでいるということはないのだし、DNAへの書き込みあるいはDNAの書き換えといったハイテク利用の技法も用いられない。とにかく、体の表面に文字を書き込むという発想がどういった脈絡で導かれたのかが私には良く分からない。誕生から少女時代にかけての毎年の誕生日に、父親が自分の名を顔に、命名者である父親の名を背中に書き込むいう場面が繰り返されるのだが、要するにこれを成人になるまで引きずって(ナギコは自分の子にも同じ行為を行うのだが、この時点で自分への名前の書き込みはやめてしまうのかも知れない。)、彼女のコミュニケーション手段(命名されることというのは人間が最初に行う、あるいは行われる言語行為かも知れない。)とは、自己及び他者の身体の表面への文字の書き込みということによって成立する、というようなことが表現されているのかも知れない。そう考えれば、近代に生きる我々が一般的なコミュニケーション手段であると考えている話すことと聞くこと、書くことと読むことが、身体表面への書き込みとそれを読むこと(それらは少し後で述べるように性行為と重なりあわされている。性行為とは、基本的には遺伝子の伝達を目的としている。ヒトの場合にはそこから遠く隔たってしまっているのだが、コミュニケーション手段と考えても良い。但し、その場合に何が伝達されるのかを言語化するのは大変難しい。)という別のコミュニケーション手段を提示することによって相対化されるとでも考えたのかも知れない。何かものすごいことをいっているようで、何となくは理解出来なくはないのだが、どうもうまく言葉を用いて表現出来ないのがもどかしい。身体の表面に文字を刻むことと、性行為が重ねられているようであるが、当然それは、紙に性描写を書き込むよりは身体的な行為といえなくもないが、あくまでも言語化には違いない。言語化してしまえば身体性は半減するわけであるが、その中途半端さを狙っているのであろうか。もっと単純に、出版者と執筆者の権力関係を回りくどく表現していると考えても良いのかも知れない。しかし、自作を売り込むべく肉体を武器にするというような図式は、とてつもなく時代錯誤的な気もする。もちろんここでは、もう少し複雑になってはいるのだけれども、いかがなものであろうか。
- 話は変わって、一見奇妙だったのは、ナギコの『枕草子』全十三書が結局のところ出版されていないようであったことである。出版者は身体表面を通じてもたらされたナギコの書を部下に写し取らせているのだが、どうやら製本らしきことをしたのは彼の同性愛の相手であり同時にナギコの恋人でもある英国青年の死体からはぎ取った皮膚に対してだけである。出版者はこれに対して猛烈な愛着を示し、ナギコと彼の間ではこの書物を巡っての争奪戦=取引合戦が繰り広げられる。
- なぜ出版されないのか、といえばそれは複製ということに対するグリーナウェイの批判的態度を反復したものなのかも知れない。以前の作品『建築家の腹』では主人公の建築家が自分の腹のコピーを大量に印刷する場面があるが、これに通底する複製文化批判と捉えて良いと思う。複製とはまさに近代を象徴する知の形態の一つであり、古典主義的な写本制度を重視するグリーナウェイならではのモチーフ選択といえよう。
- ちなみにこの辺りのナギコ対出版者の対立の図式は極めて単純な善悪二元論なのであるが、しかしながらここでは同時に、グリーナウェイの他の多くの作品に見られるシンメトリックな世界像の提示が反復されていることを指摘しておきたいと思う。
- 以下は付け足しになるが、この映画における日本人の描かれ方は正直申し上げて無茶苦茶であり、「オリエンタリズムだ」、とはっきり申し渡せる類のものではある。しかしながら、グリーナウェイほどの人間がそんなに素朴にオリエンタリズムに陥っているとも思えない。むしろ、おそらくドナルド・キーン訳で読んだであろう『枕草子』や、その他の情報源から形作られた彼にとっての日本や香港、あるいはアジア像を素直に打ち出してみせる、そうすることで非難されようがとりあえずお構いなしに、というようなことが目指されているのではないかと思える。なぜそうするかといえば、そうすることしか出来ないことをグリーナウェイ自身がよく分かっているからである。つまり、英訳されたテクストを通じて得られた情報が現実の日本と対応しているはずはないのだが、彼にとってはそれ以外の現実はあり得ないし、そういう文化の翻訳の持つ限界を知り抜いているようなのである。もちろん人類学者その他の日本文化研究者のように日本に足繁く通って、「これが日本文化だ。」と一応言い得るものを作り出すことも可能であることを主張する人たちが存在すること位は誰でも知っているのだが、グリーナウェイはそういう発想自体に敵対するかのようである。つまり、「人類学者はん、あんたそないなことでほんまに日本のことが分かるとでもおもうてんのか?そんなん無理や。それやったら、括弧付きの「日本」でもええから、正直にこれは捏造かも知れへんけどまあ許しといてや、というような顔をして提示した方がずっとましや。」というようなことを考えたのではないだろうか。
- それと若干関連するが、ナギコの生成するテクストにおける漢字の使用がやけに目立っていた。曖昧な記憶であるが清少納言の『枕草子』では漢字はほとんど用いられていなかったような気がする。少なくとも映画の中で提示されるテクストではそうであった。「漢」とは、「男」を意味する。漢字は少なくとも日本では男文字であったわけだが、それに対して平仮名は女文字であった訳である。古来使用する文字に関するジェンダーは確然として存在していたわけで、それについて語られている訳ではないが、ナギコの漢字の多用には何かのメッセージが込められているようである。
- さらに気が付いたことがあれば、どんどん付け加えたいと思う。今のところは、この位の評論が私の限界である。(1997/8/8。8/9に加筆。)