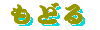時代は20世紀末、場所は大韓民国(以下、韓国)と朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮)の国境に設けられたJoint Security Area(「共同警備区域」。「日本規格協会」ではない。)。ここに駐在する韓国軍のイ・スヒョク兵長(イ・ビョンホン)が、北朝鮮軍兵士3名(『シュリ』にも出演したソン・ガンホ等が演じる。)を死傷するという事件が起きる。その真相を巡って、なかなかに凝った構成のサスペンス・ドラマが展開する。
さて、物語は、それぞれArea、Security、Jointと名付けられた3部からなる。真ん中のSecurityでは超越的な第三者の視点で事件前の韓国軍兵士と北朝鮮軍兵士の交流を描き、また、前段と後段にあたるArea、Jointの部分は、事件発生後に永世中立国スイスから派遣された朝鮮系男性を父親とするスイス軍将校の女性捜査官ソフィー・チャン(イ・ヨンエ)が、事件当事者達から話を聞くことによって「事の真相」を自らのうちに構築していくプロセスを描く。
ごく個人的に、その「真相」がどういうものであるか、という一般観客が読み取るべき映画の本題とも言える部分についてはどうでも良いものに思い、ひたすらこの作品の持つ「事実の構成法」へのメタ・レヴェルな言及とも言える部分に興味を覚えた。それは特に、前段と後段なのであって、要するにここで行なわれているのはまさしく、話者の「語り」から「事実」を再「構成」しようという試み、という極めて人類学的な営みだからである。
そう、映画の冒頭で、女性捜査官がJSAに着任直後、「人類学者」でもあると自称する上司の部屋を訪れ、ポリネシア研究の文献が本棚にズラッと並べられているのを見て(これは私も一瞬で見てとりました。)、「いわゆる肘掛け椅子の人類学者ですね。」という嫌味を述べているのは、本作品が人類学に対する何らかの提言を行なうものでもある、というかなりあからさまな意志表示なのであり、社会人類学を専攻する私としてはこの点にこそ注目せざるを得ないことになる。
その提言とは、結局のところ「人類学者は調査対象である社会なり個人に対して、政治的に介入せざるを得ない。」と同時に、「人類学者が明らかにし得ると考えている事実とは、個々人の主観の表明から人類学者自身が構成した主観に過ぎない。」、という極めて辛辣なものである。
さよう、ラスト近くで「真相」を明らかにしたかに見える女性捜査官は、結局のところそれを公表することを自ら禁じるか、あるいは政治的かつ外部的要請から禁じられてしまい、所詮は自己の中で「事実」を構成することしか出来ないのだし、更に言えば、ラストのどんでん返しではそれさえも「虚構」に過ぎないらしいことが暴露されてしまう。そしてまた、一連の捜査を行なうことで、二つの死体を事件に付け加えてしまうことにより、「中立」を標榜する捜査官という立場の無力さを一身に表現することにもなるのである。
私が、これらの事柄を、同じく「中立」を標榜し、「一つの事実」をインフォーマント(情報提供者)の語りから構成することが可能と考えるような、さすがに今日では少数派とは言え、未だにそれらが不可能なことについて無自覚な者も多々あるだろう人類学界に対する、辛辣な批判であると同時に、「ではどのようなことが可能なのか?」、という問いかけにもなっているように観てしまったのは、決して的外れなものではないと考える。それは確かに、そのように観なければ本作品は私にとって誠に凡庸極まりないものになってしまい、2時間近くを消費したことが無駄になる。そうして、それはあんまりだ、何とかしよう、という悪あがきに基づいた深読みに過ぎないのかも知れないけれど、ただ、人類学への言及は上述の通りかなりあからさまなものなので、上記のような「解釈」はあながち間違ったものではないだろうとも思う。
最後に、ここまで私は、この作品についての極めて個人的な「読み」を記述してきたのだけれど、こういう言わば斜に構えた評論を行なった理由は、この映画が「ナショナリティを共有する南北兵士間の友情とその破局を描くことで、20世紀半ばから南北に政治的に分断された朝鮮民族の悲劇を表現する。」ものであることは誰にでも分かることであり、敢えて私が改めて述べる事柄ではないからである。以上。(2001/07/05)