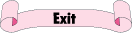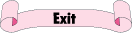宮崎駿監督作品『もののけ姫』
- 年末に来てとうとう観てしまった。さんざん議論されている作品(といいながらどういう議論があるのかは良く知らない。)なので敢えて私が何かを言うこともないと思うのだけれど、簡単ながら私見を披露させてもらう。(くれぐれも真似をしないように。)
- 全体の印象としては、もう誰かが言ってしまったかも知れないけれど、私見では本作品の作風は「クロサワ映画」に極めて近いのではないかと思う。これは本作品が「時代劇」(宮崎は時代劇を初めて撮った?)だからというだけのことなのかも知れないが、恐らくはこれまでの作品の重要なモチーフであった「空を飛ぶこと」の代わりに、今回はクロサワ映画でおなじみの「動物にまたがって野山を駆け回ること」が重視されていて、さらにはスピード感あふれるクロサワ映画ばりの殺陣の場面もふんだんに使われていることから来るものなのだと思う。勿論「自然と人間の共生」・「環境と人間」・「文明と人間」・「戦争と人間」なんていう重々しいテーマ群もクロサワ映画ではおなじみのものである。主人公アシタカの重要な台詞、「生きろ!」なんてのは、明らかにクロサワの『生きる。』を命令形にしたものだ。以上は途轍もなく私的な感想だが、あながち外れていないと思う。これだけクロサワ映画に近いのだから、国際的にも評価されるのではないだろうか。「カンヌ」とか「ベルリン」に出してみたらいかがだろう?
- さて、本作品に登場する各集団の対立図式は以下の通りである。<封建領主浅野家率いる武力集団+彼等と協力関係にある天皇から「シシ神」退治の許可を得たジゴ坊率いる僧兵集団>v.s.<モダン・フェミニスト「エボシ御前」率いる鑪(たたら)コミューン>v.s.<ディープ・エコロジストであるもののけ姫「サン」とその協力者の山犬3頭>v.s.<シシ神が守護する大いなる自然>。全二者の関係はもう少し複雑だし、大いなる自然も一枚岩ではないのだけれど、面倒なので4項に分けておく。それぞれは当初は基本的にはそれぞれの隣あるいは両隣の集団と対立しているのだが、本作品中での最終的な闘争に向かって四つ巴(そんな言葉は無いけれど。)のような対立関係になっていく。こうやって一列に並べて図式化することによりはっきりと見えてくるのは、鑪コミューンとサン達の持つマージナリティ(境界性)である。基本には武家を中心とする封建体制=国家と自然との対立があって、その間に鑪コミューンとサン達がマージナルなものとして介在する、という図式である。勿論、中世末の日本にフェミニズムだのエコロジーだのという思想・運動があったとは考えられないのだけれど、まあ、時代考証についていちいち揚げ足をとっていったらきりがないのだし、宮崎の作品世界は基本的にファンタジーなのだからそういうことはここでは不問に付すとして、この作品の中では明らかにそういう思想から出て来たものと取るしかない言説が数多く散りばめられているので、この点に関しては宮崎の意図を読み間違えてはいないと思う。
- ここで重要なことは宮崎はこうした四つの相対立する立場を打ち出しながら、これまでの作品とはやや異なって、本作品をどの立場が正しいとかどの立場は間違いである、というような一義的にしか解釈可能出来ない単純な物語にはおとしめていない。どの立場に立つにせよ、それにはそれぞれの抱える様々に異なる理由や背景があるようだし、どの立場が正しいのかを判断するような超越者は実のところ本作品には前提されていないので(シシ神はさほど強くないし、善と悪の両面を持ち、生と死双方を司る。)、そういう解釈は観客に委ねられることになる。この、多義性、もっと言えば分かりにくさ、が広く、余りにも広く受け入れられてしまった、ということ自体が、極めて興味深い現象なのではないかと思う。
- では、主人公アシタカは一体どういう存在なのであろうか。東国は「蝦夷(えみし:ちなみに作品中でもあくまでも「大和(やまと)」の人々からの呼称ということになっている。)」の青年アシタカは右腕に「祟り」を受け、これを祓うべくシシ神を求めて西国に遍歴の旅に出る。その途中で鑪コミューンの二人の男を助けたり、サンを窮地から一時的に助けたりするのだが、結局のところ自分にかかった祟りを自らの力で祓うことは出来ないのだし、サンの育ての母である山犬「モロ」の言う通りサンを根本的に救済すること、すなわち「人間社会に復帰させること」は出来ない。ましてや、「共存の道はないのか?」と鑪コミューンの人々やサン等に問い、上記の対立を解消させようと努力はしてみたものの、結果的には何も出来なかったことになる。まあ、それなりに仕事はしているのだが、決してクロサワ映画の多くで三船敏郎が演じていたような英雄ではないということだ(でも、考えてみれば三船が英雄的な役所を得たのは『椿三十郎』、『用心棒』、『七人の侍』位のものだ。しかも、この三つの作品にしたところで三船の役所は基本的にアウト・ローである。)。彼の立場はあくまでも傍観者であり、多めに見積もっても仲介者であるに過ぎない。これはいわゆる「とらわれのお姫様を救出し、結婚する」、という世界的に極めて広範に用いられている、いわゆるアンドロメダ型神話に対するアンチテーゼとなっている。
- 上のことと関連するが、最も面白く感じられたのは最終的にサンがディープ・エコロジストの面目を守り、森へと戻っていくのに対し、アシタカはこれまたマージナルな彼の出身地である「蝦夷」に復帰せず、鑪コミューンの人々と共に生きる、あるいは一連の戦いで右腕を失ったエボシ御前の右手となって働くことを決意する、という点である。(ちなみに最終的にはアシタカの右腕は回復する。これは象徴論的には極めて重要な交換である。J.カンピオンの『ピアノ・レッスン』における切断された指とピアノから外された鍵盤の交換を想起させる。祟られ、切断されるのが左腕でなく「右腕」であること自体も面白い。右腕、あるいは右手の持つシンボリズムについてはR.エルツ『右手の優越』垣内出版を参照のこと。ただし、絶版なので図書館で探して下さい。)鑪コミューンはある意味では封建制を超え、近代工業社会までを視野に含むような存在形態である(家内制手工業ではなく工場制手工業が行われている。但し、「資本家」による搾取はない。だからこそ「コミューン」なのだ。)。前近代的封建体制国家「大和」に組み込まれていない「蝦夷」の青年が、近代にいきなり組み込まれてしまう、という図式が仄めかされているのだ。これは近代において主として西欧が、その植民地をいきなり近代の文脈に組み込んでいくプロセスを逆手に取ったものである。このことからも分かる通り、実は本作品はポスト・コロニアリズムをも視野に入れた映画だったのである。(1997/12/28)