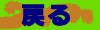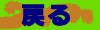Mel Gibson監督作品 The Passion of the Christ 2004.12(2004)
-
映画監督としても評価の高いアクション・スターであるメル・ギブソン( Mel Gibson )が私財をなげうって作り上げた、タイトルの通りイエス・キリストの受難劇。描かれるのは福音書の記述のうち「オリーヴの園」辺りからその復活までとなる。例えば18世紀中ごろに成立したJ.S.バッハ( Bach )のオラトリオ『マタイ受難曲』は復活を描くことなく終わっているのだけれど、今日の世界は、この映画などを見る限りにおいて宗教史的にはよりファンダメンタルな方向に進んでいる、ということも言えなくはない。
-
そういう冗談はさておき、この作品は基本的に「正典=カノン」と見做されている四つの「福音書」の記述に忠実な形で、イスカリオテのユダの裏切りによって起きるイエスの捕縛から磔刑(たつけい)、さらには上記の通り復活までを描き切る。
-
ところで、肝心なイエス最期の言葉は「神よ何故私をお見捨てになられたのか」(一応「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」と言っているように聞こえる。この映画における使用言語に関する話は後述。)なので、この部分は『マタイによる福音書』(「による福音書」は以下略)か『マルコ』に基づいていて、このあとに更に続けて「父よ私の霊をあなたの御手にゆだねます」という言葉があって、これは同じく『ルカ』より、あるいはまた兵卒が槍で脇腹を突き刺す場面もあって、これは『ヨハネ』より、といった具合に、四つの正典「福音書」を統合する形で脚本が書かれていることが良く分かるのである。
-
さてさて、周知の通りイエス・キリストの受難というのは例えば絵画や先に挙げた音楽など実に様々な形で描かれてきた。映画で言うとピエル・パオロ・パゾリーニ( Pier Paolo Pasolini )監督の『奇跡の丘』(原題は IL VANGELO SECONDO MATTEO 。1964年の作品。)という大変素晴らしい作品があるのでこれは是非見て頂きたいのだが、要するにもうやり尽くした感もある状況でM.ギブソンが今回新たに受難劇を作る意図あるいは意味というのはどこにあったのか、というのはとても重要な問題だ。
-
例えばその『聖書』解釈において取り立てて目新しさはないこの作品の最も画期的な点は、そこで使用されている言語にある。元々ギリシャ語で書かれ、後にラテン語に翻訳されてヨーロッパに流布し、今日ではあらゆる言語に訳されている『新約聖書』だけれど、ギブソンは敢えてこの映画で、当時エルサレム周辺(要するにパレスティナ)で使われていたと考えられるアラム語、ヘブライ語、ラテン語を織り交ぜる形で脚本を作らせている。
-
話が前後するけれど、この映画における主演のイエス役ジェイムズ・カヴィーゼル( James Caviezel )が拷問の果てに血みどろとなって死んで行く姿の痛々しさは筆舌に尽くし難いところでもあり、これと上記使用言語の厳密化や、更にはまた舞台装置の凝りに凝った造形やロケーション地選定におけるこだわりなどとも相俟って、こうした様々な点に明瞭な形で現われている、この映画におけるリアリズムを追求しようとする姿勢には誠に壮絶なものがあるのであって、確かにそれらが実は商業性を意識したものなのかも知れないとは言え、ここまでやれば何も言えない、というところまでやってしまっている作品だと考えた次第である。以上。(2005/12/18)