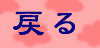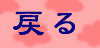イム・グォンテク監督作品『春香傳』
-
大韓民国映画界の巨匠イム・グォンテク監督による、朝鮮半島に古くから(とは言え後述の通りそれ程古くはないだろうことが推測し得る。)伝わるパンソリ芸=語り物の一演目、『春香傳』(このタイトルはあくまでも小説に付されたもので、パンソリ芸としては『春香歌』と呼ぶべきもののようだ。)の映像化。大韓民国での映画化やテレヴィ・ドラマ化は数知れず、更には朝鮮民主主義共和国でも1980年に映画化されていることや、日本国内にある数多の朝鮮料理店の名前にも採用されていることなどからして余りにも有名な作品らしいこの物語は、端的に言って朝鮮版『水戸黄門』である。だから、取立てて粗筋や概略を述べることはしない。
-
要は、余りにも単純な勧善懲悪(農民を酷使し、あるいはまた自分の意に従わない春香を理不尽な形で死罪に処しようとする悪代官を懲らしめる、というものです。)、女性が貞節を守ることの美徳(女は二人の夫に仕えず、というものです。)がこの物語のテーマである。面白いのは後者について、この物語においては、それを守るためならば国法に背いても良い、というテーゼが打ち出されている点。即ち、主人公・春香は妓生(きーせん:日本の文脈では芸妓ということになるだろうか。しかし、両班(やんばん)を「貴族」、族譜(ちょっぽ)を「家系図」と訳しておきながら、「妓生」についてはそのまま字幕に載せたのは問題かも知れない。これでは、分からない人には分からない。)の娘なのであり、かつての朝鮮の国法に基づく身分制度の元においては親の職業は受け継がれるべきもので、それに背くことは国家への反逆ということになるのだが、この物語ではそれは貞節を守るための美徳として賛美されている。
-
そうなると、このパンソリ芸が作られた年代・時代背景や、作り出した社会層というものが非常に気になってくる。何しろ、この物語は、国家の法に定められた身分制度を否定する、即ち、卑賤視されていた女性が国家に反逆し闘う(という意味で、春香は「烈女」として民衆の支持を得ることになる。)という階級闘争を描いたものなのだから。となると、この作品の成立年代はさほど古くはなさそうな気がしてくる。
-
さて、以上のような深読みをすればそれなりに楽しめるのだけれど、そもそもはあきれてしまう程単純明快な物語、その点ではこの欄で少し前に紹介したDancer in the Darkも同様なのだが(同映画とこの作品の関係を、両映画に共通の「薄幸な女性に課せられた身体刑」の差異というモティーフに即して考えると誠に楽しい。M.フーコー著・田村俶訳『監獄の誕生』新潮社、1977(1975)を参照のこと。)、それを今日の目の肥えた観客に受容可能ならしめるために行われている工夫は、この物語のナレーションを大韓民国の「国唱人間文化財」チョ・サンヒョンに務めさせ、それどころか、この人がパンソリ芸をどこかのホールで実際に上演しているシーンを織り交ぜながら話を進行させていく、というものである。誠に画期的だ。何しろ、この人の歌唱が素晴らしい。参りました、という感じ。そもそもは映像なし、語りのみで情景を喚起し、人物描写を行ってきたパンソリ芸なわけであり、そういう意味ではこの作品の映像は付け足しであるとすら思えてくる。(とは言え、映像もなかなかのものであることも付け加えておきたい。)もう一つ付け加えるならば、本作においては、上演している本人どころか、観客席までもが映し出され、この映画の鑑賞者には彼等の反応までを見て取ることが可能になっている。口承芸に興味のある私のような者には、パンソリ芸の場におけるクライアントとのインタラクション(相互行為)をつぶさに観察することが出来て、誠に有意義な時間であった。
-
そのこととも関連するのだが、パンソリという口承芸の一作品であるこの物語において、両班の出自を持つ主人公・李夢龍が科挙という文字を用いる試験を経て「密使」(だから『水戸黄門』なのです。)として国家に採用される点、妓生の娘・春香が書に堪能である「才女」として描かれている点が誠に面白い。柳田國男の問題提起以来、口頭文化と文字文化の関係については若干の事例収集・考察が行われてきたに過ぎず、今後更に発展させるべき問題機制ではないかと考えているのだが、このパンソリ芸上演形式の在り方もまた、その一端を示す事例として、記憶に留めておきたいと思う。(2001/01/23)