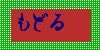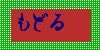Lasse Hallström監督作品 The
Cider House Rules
-
原作はJohn Irving、監督は『マイ・ライフ・アズ・ア・ドッグ』(原題はMy Life as a Dog)、『ギルバート・グレイプ』(原題はWhat's Eating Gilbert Grape?。直訳すると『何がギルバート・グレイプを食べているのか?』)を撮ったLasse Hallströmという、文学界、映画界の二人の巨匠が創り上げた慈愛と諦念と希望に満ちた秀作である。
-
-
-
あたかも手塚治虫の『Black Jack』、武田泰淳の小説『堕胎医』の黒澤明による映画化である『静かなる決闘』(だったっけ?)、森敦の『われ逝くもののごとく』を足して三で割ったような設定とストーリー展開。舞台は1940年代のメイン州はニュー・イングランドの孤児院兼産婦人科とリンゴ農場。Tobey Maguire演じる主人公は、本作でアカデミー賞助演男優賞に輝いたMicheal Caine演じるところの違法人工中絶を「善意」ないし「確信犯」的に行っている産科医が孤児の段階から手塩にかけて育て上げた無免許産科医という設定。
-
-
-
あたかも森の小説の如く、次から次へと人が死んで逝き、埋葬の場面が繰り返されるのだけれど、<人工中絶をしょっちゅう行っているせいもあって人の死に対しては客観的に対処出来てしまう主人公達>、という設定から導かれる通り(この設定は、20世紀という「過剰な死の時代」への痛烈な皮肉にもなっていると思う。この点で本作品は、既に紹介したAmerican Beautyとも響き合うことになる。)、そういった死の数々は、人工中絶には反対の立場をとる主人公が中絶された胎児を嫌々ながら(とは言え、無表情に)焼却炉に捨てる場面と同じように極めてあっさりと描かれる。
-
-
-
ただ、全編を通して殆ど無表情で演技してきたTobey Maguire(全くこの人の演技は「お見事」、としか言いようがないのだが…。)も、その育ての親でありかつ師匠であるMicheal Caine演じる産科医の死に対しては、涙を見せることになる。ここまでの淡々とした描写も、この場面を引き立たせるための脚色であったことが明らかになるという訳だ。フムフム、誠に素晴らしいではないか。
-
-
-
さて、私は何でもかんでも人類学的コンセプトである「通過儀礼」に還元してしまう大塚英志的な評論は大嫌いなのだけれど、本作はかなり意識的に通過儀礼的モティーフを用いていることに注意を促しておきたい。つまりは、通過儀礼というのは<分離→移行→統合>というプロセスを経て完成するもの、とされている訳だけれど、本作品の物語の流れが、<人工中絶に反対する主人公の孤児院兼産婦人科からの別離(分離)→リンゴ園での生活、そしてやむを得ぬ事情がある場合の人工中絶の容認と実施(移行)→師匠の死と孤児院兼産婦人科への復帰(統合)>という形に整理できてしまう事から、余りにも見事に研究者が導き出した通過儀礼のプロセスをなぞっていることが見て取れてしまうであろう。だから何なんだ、と言われても困るのだけれど、まあ、それこそがこういう還元主義的「分析」が、結局は「説明ならざる説明」乃至「説明のための説明」に終始してしまうという欠点を如実に示すものでもあるのだ。
-
-
-
もう一点。こっちの方は凡庸ならざる分析だと思わず自負してしまうのだが(笑)、リンゴ園の労働者住居内(これが「サイダー・ハウス」な訳です。)に張ってある管理者側が書いた五箇条の禁止事項(「ルールズ」ですね。複数形です。)を、非識字者である黒人労働者達はそれを読む事が出来ないために全く効力を発揮していやしない、という事と、自分の卒業証書や医師免許を写し取ることにより、弟子である主人公のそれらを偽造し、しかもそれらが白人の識字者の集まりである理事会だか何だかで効力を発揮してしまう、という事の対比が面白かった。「文字と権力」「言葉と権力」「知と権力」などという、今日の人文諸学において極めて重要なテーマを、本作の作者達は誠にさりげなくまぎれ込ませているのだ。
-
-
-
最後にもう一つ。本作のメインのテーマはどう考えても人工中絶の是非を巡るものなのだけれど(余談ですが、最近のアメリカ映画のテーマ設定の「ヘヴィさ」には感動すら覚えます。「生命倫理」について関心のある方、及び研究者は取り敢えず観ておくべき映画でしょう。)、結論としては、「やむを得ない事情(強姦その他による不本意な妊娠、経済的に育児が不可能、肉体的に出産に耐えられない、などなど。日本における「優生保護法」改め「母体保護法」下で行われている人工中絶は、かなりの部分が「経済的な理由」によるものでありかつまた比較的高齢の女性に多い、という事を聞いた事があるのだが、間違っていたらごめんなさい。『母体保護法の実施に関する調査報告』みたいな資料が厚生省あたりから出ていると思うので、それを参照して頂きたい。今は、調べている時間がないのです。)があれば認めざるを得ない」、という、恐らく今日のアメリカでは最も一般的なのだろう(日本ではそうですね。)と思っていた見解に収束するのだけれど、何故敢えてこういう作品が作られなければならないのかを考えればすぐに分かる通り、現実は全くそうなっておらず、やはり「プロ・ライフ派」(生命尊重派。これに対するのが本人の意志を尊重する「プロ・チョイス派」という事になります。常識ですね。)の勢力は相変わらずなのかな、と認識を改める必要を感じてしまったのであった。
-
-
-
確かに、最近新聞紙上において、「プロ・ライフ派による中絶クリニック爆破テロ」、のようなものが殆ど報道されなくなっているのだが、現状についてはきちんと見極めなければならないと、思いを新たにするのであった。基本的にプロ・チョイス派に近い立場で作られているこの映画の上映へのプロ・ライフ派による抗議運動みたいなものもひょっとするとあったかも知れない。ご存じの方はご一報下さい。以上。(2000/07/08)