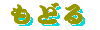
基本的に明確な主人公が存在しないこの映画は、メキシコ−アメリカ合州国間の麻薬密売ルートに関わる人々が織りなす群像劇である。即ち、本作品は大きく分けて三つの交互に現われるプロットから構成され、結末に向けてそれは上記麻薬密売ルートという一つの相の元に収束していくことになる。その三つのプロットは、1.メキシコ国内の麻薬密売組織撲滅に奮闘するメキシコ人刑事Javier Rodriguez(Benicio Del Toro:本作品でアカデミー助演男優賞を受賞。これは全く正しい選択。)、2.次期米国麻薬対策本部長候補のオハイオ州・最高裁判事Robert Wakefield(Michael Douglas:どう見ても影が薄い。)とその麻薬中毒の娘Caroline(Erika Christensen:どうみても娘の方がインパクトがある。)、3.サンディエゴの大物麻薬密売人Carlos Ayala(Steven Bauer)とその妻Helena(Catherine Zeta-Jones:その悪女振りはなかなかに見事。)、そして彼らと対峙するMontel Gordon (Don Cheadle)及びRay Castro(Luis Guzman:以上2名はpaul thomas anderson監督作品の常連。)を中心とする警察内の麻薬対策班、という人々を中心的な担い手とするもの、ということになる。
上記のようにそれなりに複雑な構成を持っているこの作品、Soderbergh監督は上に挙げた三つのプロットにそれぞれ黄、青、白という色分けをフィルム選択(で良いのかな?)によって施し、観客が混乱しないように心配りをしている(私には不要だけれど…。)。これらの色について、単なる心配りなどではなく、ドラッグの色なりイメージなりと関係があるのでは、などと考えるのは、決して邪推ではないのかも知れない。「ブルー・ヴェルヴェット」というのが、ドラッグの一種であることは、例えばDavid Lynchの映画タイトルに端的に現われている、ある意味で一般常識でさえあるのだから。
さて、冒頭で、本作品は「作品」として優れている旨を記したが、それはこの作品が、単に反麻薬をいたずらに強弁するような凡庸な作品ではないからである。そう、Soderbergh監督は、この作品において、米国の麻薬問題の背景には南北間(本作品ではメキシコ/米国として表現されている。)や人種間(当然のことながら、ヨーロピアン/ヒスパニック・アフリックとなる。)の経済格差が存在することをきちんと、それも麻薬中毒のヨーロッパ系優等高校生に代弁させている。しかも、それを聞き、かつまた自分の娘というたった一人の人間すらを、麻薬の誘惑から救うことにおいて難儀してしまうRobert Wakefield判事は、麻薬対策本部長に指名されたは良いけれど、その就任演説を中座し、まずは自分の家族から始めよう、という感じで(なんだか中国の故事みたいだが…。)、地道かつ着実とも思える努力に向かうのである。実のところ、この辺の展開には誠に感心してしまったところなのだけれど、要は、主としてヨーロッパ系からなる政府代表とその部下達が、上記のような社会的背景を無視していわば暴力的な形で介入したところで、問題は何も解決しない、という、言ってみればこの作品は、安易で権威主義的な反麻薬・麻薬撲滅運動など、かえって事態をこじらせるだけで、それよりもより根元的なところから始めるべき、というメッセージを含んでいるのである。「妥当」と述べたのはこのような理由からである。
例によって蛇足だけれど、この作品におけるBenicio Del Toroの存在感は確かに圧倒的である。それと同時に述べておくべきなのは、この人、実は以前にTerry Gilliam監督のどちらかと言えばドラッグを肯定的に描いたFear and Loathing in Las Vegasという作品においてJohnny Deppと共演し、始めから終わりまでほとんどラリりっぱなし(こんな日本語があるのかどうかは知らないけれど。)の役を演じていたのだが、本作品では極めて真摯に麻薬問題に取り組む刑事を終始真顔で演じていて、その点が端的に言って「可笑し」かった。ということで。(2001/05/29)