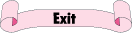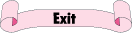1. ウィリアム・ギブソン著『ヴァーチャル・ライト』角川書店、1994(1993)
- 続編である同著者の最新作『あいどる』(角川書店、1997(1996))をとっとと読んでしまうべく、その準備としてかなり前に古本屋で入手してあった本書をようやく読むこととなった。1980年代における「スプロール」三部作のような、サイバー空間を主な舞台とした、宗教性の濃い、やや思弁的な物語ではなく、あくまでもエンターテイメント小説である。端的に言えば、本作はP.K.ディックのいわゆる「警察国家」もの小説群をかなり意識しているのではないかと思われる。さて、本書の最大の見どころはなんといっても「橋上文化」の描写であろう。時代設定は西暦2005年、大地震により橋としての本来の機能を失った「サンフランシスコ・ベイ・ブリッジ」は、国家権力の及ばない「橋上生活者」たちのいわばアジールと化している。面白いのは橋上文化を研究する「山崎」という日本人の社会学専攻の研究者の存在で、彼に言わせれば橋上文化、あるいは橋そのものはまさに赤瀬川源平の言う「超芸術トマソン」なのだ、ということになる。昨年暮れに東京湾横断道「アクアライン」が開通したけれど、通行量は予想をはるかに下回るらしく、「これってひょっとしてトマソン?」とか何とか思ったのは私だけではないだろう。いずれにせよ、東京湾岸の三つの大きな橋、「レインボー・ブリッジ」、「ヨコハマ・ベイ・ブリッジ」、「アクアライン」が大地震によって機能しなくなり、今後日本経済がさらに悪化した場合に出現するはずの大量の失業者達のアジールと化す可能性は十分にあるのではないかと考えてしまった。
2. 篠田節子著『アクアリウム』新潮文庫、1996(1993)
- かなりシビアな「エコロジー運動」批判小説である。山岸真が巻末で極めて要を得た解説をしているので詳しいことはそれに譲るとして、ここで1998年に入った現時点から意見を述べるとすれば、本書で提起された問題は宮崎駿の『もののけ姫』におけるそれに直結する、ということである。基本的な図式は<奥多摩に林道を建設しようとする企業・賛成者等からなる一派とその反対運動の指導者であると同時にこれをその実売名行為として行っている尾崎という人物及びその協力者>v.s.<ひょんなことから同反対運動に荷担してしまう主人公の公務員・長谷川と反対運動の欺瞞的特質や環境行政の途轍もないとろさに自覚的な本気の反対派女性・伊丹>となる。ここでいう林道建設反対運動とは結局のところいわゆる都会人による土地住民無視の自己癒し的な意味を多分に含んだ「エコロジー運動」なのであって、そういうことを盛んに主張する企業や諸団体にありがちな「自ら環境を汚染しておいて、浄化装置を売る」式の欺瞞的な性格が本書ではあからさまかつ徹底的に批判される。なお、本書に登場する洞窟内に生息する生物「イクティ」は山岸の指摘の通りS.レムの『ソラリスの陽のもとに』における「ソラリスの海」を素材としたものであろうが、レムのほとんどの作品においては「人間とその他の知的生物とのコミュニケーションは基本的に不可能である」、というテーゼが打ち出されているのに対し、イクティと長谷川は心的交流を果たすことになる。私はレムのテーゼに首肯しつつ、どうやったらコミュニケーション可能なのかさっぱり分からない異星人やイルカなどと心的交流をしたりすることがビジネスにまでなってしまっている今日的状況に憂いを感じていたりするのだが、まあ、後述のようにイクティはちょっと特殊な存在なので、これはこれで良いのかも知れない。面白いのは結末部で、長谷川にとってイクティは一旦死んでしまったかに思われたのだが、伊丹に言わせればそれは、長谷川の前に「森を構成するすべての生命体が、動物の形態を取って現れた」ものなのであって、長谷川は「ここの無数の生命と交信することのできる人」なのだ、ということになり、そして、森が破壊され尽くされない限り、それは「生き続けていると思う。奥多摩の森は懐が深いから」(p.309)ということになる。この辺りは『もののけ姫』の結末と全く同様であることはお分かりであろう。一つだけ気がかりなのは、林道建設への妨害行為としての「建設促進派宅の4,000万円分の鯉の殺害」、「建設機材への放火」、「トンネルの爆破」等というテロ行為を篠田がやや肯定的に描いてしまったことかも知れない。人が死んでいないからいいのかも知れないけれど、暴力は暴力である。なお、もう一つ付け加えると、この辺りの、大菩薩峠付近で繰り広げられる爆弾作りその他は、『カノン』における活動家・岡宏子の挿話とも結び付け得るものではないかと思う。
3. 鈴木光司『仄暗い水の底から』角川ホラー文庫、1997(1996)
- 東京湾岸を舞台とし、そこにたゆたう様々な「漂流物」(まさに「トマソン」!!!)を主要なテーマにした連作短編集。以上3冊、わざと集めているわけではないのだが、どういうわけか同じ傾向の本が並んでしまった。最後の挿話「海に沈む森」は奥多摩の「白岩鍾乳洞」を舞台にしており、実は篠田の『アクアリウム』のラストの舞台は同鍾乳洞付近ということになっている。もっと言えば本書の解説を書いているのは篠田である。こうなってくると、二人は相互参照しているとしか思えないのだが、白岩鍾乳洞についてはどちらが先なのだろうか。「海に沈む森」の初出年度が不明だけれど、篠田の方が先のように思う。なお、篠田は本書の解説の中で鈴木の『リング』(角川ホラー文庫、1993(1991))に関して、「安易なオカルティズムに流れたり陳腐な動機で語られる部分はない。」(p.270)と述べているのだが、私には、ヴィデオ・テープに殺された女性霊能者の怨念が乗り移り云々、というのはまさに「安易なオカルティズム」としてしか読めなかった。ただ、「陳腐な動機で語られる部分はない。」というのには賛同するし、続編の『らせん』は真の傑作である。その続編である近日刊行予定の『ループ』(角川書店)では、私見では<人類v.s.女性霊能者のクローン>、という展開が何となく予想されてしまうのだが、こんな安易な予想を遙かに超え、『らせん』をもしのぐようなスーパー・ノヴェルの登場を期待している。
4. 篠田節子著『美神解体』角川ホラー文庫、1995(1994)
- コンパクトな作品だけれど、なかなかインパクトがあった。主人公は美容整形によって絶世の美女と化したピアニスト・麗子。物語は彼女が思いを寄せるある商業デザイナー・平田一向が所有し、二人がしばらくの期間滞在することになる八ヶ岳の山荘での凄惨な事件を綴る。平田の性癖はちょっと変わったものなのだけれど、彼はそれが高じてある女性を殺害しかつまたその美学に従ってその死体をバラバラにしてしまったことがあり、再び同じことを繰り返しそうになる。彼の美学では、表面的な美の裏にあるものを明らかにすることが至上の喜びなのであり、当然麗子もその対象となる。要するに、彼の趣味は美女を「解体」すること、である。結局のところその試みはうまくいかず、麗子は美容整形により自分の持って生まれた顔を失うという一つの死を経て、さらには本書で述べられる一連の事件を通じて新しい顔を自分のものであるという認識に到達することによって新たな生を得るに至ることになる。いわば「死と再生」を基本テーマとした通過儀礼的な小説であると言えるだろう。なお、私には篠田が美容整形をかなり肯定的に扱っている点が興味深かった。
5. 村上龍著『オーディション』幻冬社文庫、1997.12(1997.6)
- なんと、半年で文庫化。こうなってくるとほとんど文庫書き下ろしと変わらなくなってしまう。少女時代に虐待を受け、そのトラウマからのがれられず付き合う男達の足を片っ端から切断してしまうという性癖を持つ絶世の美女を巡る物語である。彼女を「オーディション」で発見した青山は結局右足を失うことになるのだが、解説で斎藤学が述べている通り、これは象徴的な去勢であり、この小説もまた通過儀礼的なものだということが言えるのではないかと思う。なお、以上2つの小説の主要モチーフは「解体」あるいは「切断」である。これらと「酒鬼薔薇聖斗事件」を結び付けることはたやすいだろうと思う。だからといって私には今のところ今日の尋常でない状況への処方箋は思い付けないというのが本音である。
6. フィリップ.K.ディック『パーマー・エルドリッチの三つの聖痕』ハヤカワ文庫、1984(1964)
- 基本的な文献であり、今頃読んだというのが恥ずかしい位である。この作品が庵野秀明の『新世紀エヴァンゲリオン』に与えた影響は計り知れない。作品全体の解説をするのも面倒なので、二つばかり特に重要な部分を引用したい。
- a.「神は永遠の生命を約束するだけ。われわれはそれをお渡しできます。」(p.226)
- b.「救済というものは存在する。しかし−
- だれもが救済されるとはかぎらない。」(p.337)
- a.は「チューZ」という服用者に後々まで残る強烈な幻覚作用、あるいは時間感覚の変化(それによって永遠の生命が保証されるわけだ。)をもたらす新種のドラッグを火星の植民地に売り込みに来たパーマー・エルドリッチ一派の宣伝用ビラの文句である。このキリスト教的伝統から見れば極めて「冒涜」的な言説は、パーマー・エルドリッチに憑依した異世界の生命体の人類全てを基本的には「それ」の支配する主観的世界に投げ込もうという意図から出たもので、ある意味では『エヴァ』における「人類補完計画」の原型とも言える。b.は人類の運命を担ってパーマー・エルドリッチと対決する予知能力者・バーニイ・メイヤスンが物語の結末間際で到達した洞察である。ここには後に『ヴァリス』シリーズで蕩々と語られることになるグノーシス主義的なアンチ・キリスト教的(あるいは初期キリスト教的?)かつ個人主義的な救済観が現れていることになる。これもまた、『エヴァ』における極めて個人主義的な救済を表現した結末に応用されたものである。なお、解説に引用されたディック自身の言によれば、本書の本文全体は邦訳書では9行足らずの「パラグラフ」の「つけたし」らしいので、本来は本書の全てを語っているらしいこの部分を引用した方がいいのかも知れない。でも、そうするとディックの言うところに従えば本一冊を引用することになってしまい(わずか9行の本!!!)著作権の問題が生じてしまいそうなので止めておく。是非手にとって確かめていただきたいと思う。この部分もまた『エヴァ』に深く影響を与えていることは間違いないだろう。(以上、1998/01/05)