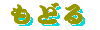婛偵彂昡棑偱弎傋偨捠傝乮偙偪傜傪嶲徠偺偙偲丅乯丄偙偺塮夋偺尨埬偼Brian Aldiss偑1969擭偵敪昞偟偨抁曇'Supertoys Last All Summer Long'偱偁傝丄偦偺屻彅乆偺曄慗傪扝偭偰嵟廔揑偵S.Spielberg偑塮憸壔偵偙偓偮偗偨丄偲偄偆偙偲偵側傞丅
偲偙傠偱丄Aldiss帺恎偑乽僗僞儞儕乕偺堎忢側垽忣乗傑偨偼巹偲僗僞儞儕乕偼擛壗偵偟偰亀僗乕僷乕僩僀僘亁傪亀A.I.亁偵媟怓偟傛偆偲偟偨偐乗乿乮強廂亀僗乕僷乕僩僀僘亁抾彂朳丄2001.04乯偲偄偆僥僋僗僩偺拞偱岅偭偰偄傞偺偼丄Aldiss偑嵟廔揑偵姰惉偝偣偨偙偺塮夋偺尨埬偲側偭偨乽僗乕僷乕僩僀僘嶰楢嶌乿偼丄乽僐儞僙僾僩偲偟偰丄傢偨偟偺峫偊傞堦杮偺塮夋偵昁梫側傕偺傪偡傋偰娷傫偱偄傞丅僯儏乕儓乕僋偺峖悈傕噣惵偺梔惛噥傕搊応偟側偄丅偨偩偺丄垽偲抦擻傪昤偄偨嫮楏偱椡嫮偄僪儔儅乿乮p.362乯側偺偩偦偆偱丄帠幚偦偺捠傝側偺偩偗傟偳丄幚嵺偵塮憸壔偝傟偨傕偺偵偼丄乽僯儏乕儓乕僋偺峖悈乿傕乽噣惵偺梔惛噥乿傕嬌傔偰廳梫側梫慺偲偟偰搊応偟偰偄傞丅摿偵丄屻弎偺傛偆偵屻幰偼杮嶌昳偺儊僀儞丒儌僥傿乕僼偱偝偊偁傞丅偳偆傕偙偺擇恖偺娫偵偼丄堄巙偺慳捠偑婎杮揑偵寚擛偟偰偄傞傛偆側偺偩偑丄梋傝婥偵偣偢偵愭偵恑傕偆丅
偝偰丄噣惵偺梔惛噥乮Blue Fairy乯偲尵偊偽丄Walt Disney偵傛傞戞2嶌栚偺挿曇傾僯儊乕僔儑儞嶌昳乮1940擭偵嶌傜傟偨偙偺嶌昳偑丄偐偺柤嬋乪When You Wish Upon a Star乫傪惗傫偩偙偲偼廃抦偺捠傝丅傑偁丄偦傫側偙偲偼偳偆偱傕椙偄偺偩偗偳乧丅乯偺報徾偑嫮楏夁偓偰崲偭偰偟傑偆丄偦傕偦傕扤偑幏昅偟偨偺偐偝偊掕偐偱偼側偄乮僀僞儕傾恖側傫偩傠偆偗偳乧丅偙傟偼偪傚偭偲嫽枴偑偁傞丅偱丄僱僢僩撪傪扵偭偰傒偨偺偩偑丄寢嬊椙偔暘偐傜側偐偭偨丅偆乕傫丅壗偲偐偟偰偔傟乕丅旕忢偵婥偵側傞丅乯嬌傔偰椙偔弌棃偨暥寍嶌昳亀僺僲僉僆亁偵偍偄偰丄僕僃儁僢僩栮偝傫偑憿偭偨乽栘嬼恖宍乿偱偁傞僺僲僉僆傪乽恖娫乿偵曄偊傞暥帤捠傝偺杺朄傪帩偮懚嵼丅偙傟偑偙偺塮夋偺傎偲傫偳儊僀儞丒儌僥傿乕僼偲偟偰搊応偡傞丄偲偄偆偙偲偼懄偪偙偺塮夋丄傂偄偰偼Aldiss偺乽僗乕僷乕僩僀僘嶰楢嶌乿偡傜傕偑偦傕偦傕亀僺僲僉僆亁傪尨埬偲偟偰偄傞丄偲偄偆帠幚傪擛幚偵帵偡偙偲偵側傞丅
偦偆丄杮塮夋偺儊僀儞丒僾儘僢僩偼丄偁傞帠忣偐傜偲偁傞彈惈儌僯僇丒僗僂傿儞僩儞乮Frances O'Connor乯傪曣恊偲偟偰垽偡傞偙偲傪僾儘僌儔儉偝傟偨僨僀償傿僢僪偑丄偙傟傑偨偁傞帠忣偑偁偭偰偦偺彈惈偐傜偺垽傪慡柺揑偵嫕庴弌棃側偄忬嫷偵捛偄崬傑傟丄偦偺尨場偵偮偄偰僨僀償傿僢僪偼丄帺暘偑乽恖娫乿偱偼側偄偙偲偑栤戣側偺偩丄偲偄偆悇榑傪峴側偄丄偦偆偙偆偡傞偆偪偵傆偲帹偵偟偨摱榖亀僺僲僉僆亁偵搊応偡傞丄恖宍傪乽恖娫乿偵曄偊摼傞椡傪帩偮噣惵偺梔惛噥傪扵偡椃偵弌傞丄偲偄偆傕偺側偺偱偁傞丅
偦偺恎懱偲嵃偺峴偔枛偵偮偄偰偙偙偱偼徻偟偔怗傟側偄偙偲偵偡傞偗傟偳丄傗傗姶彎揑夁偓傞偺偑婥偵側偭偨偲偼尵偊丄恖岺揑偵憿傜傟偨僨僀償傿僢僪偑丄恖椶偑巰柵偟偨2,000擭屻偺悽奅偵偍偄偰斵偺屻宲婡払偵僨乕僞亖婰壇傪梌偊傞偙偲偵傛傝丄偁傞堄枴偱憿暔庡揑峴堊偺堦抂傪扴偭偰偟傑偆丄偲偄偆恾幃偼丄惤偵傾僀儘僯僇儖偐偮擯傝偺棙偄偨傕偺偲偟偰丄昡壙偟偨偄偲巚偆丅
埲忋丄偲傝偲傔傕側偔彂偒晅偗偰偒偨偗傟偳丄嵟屻偵婥偵側偭偨偙偲傪2揰傎偳丅偦偺1丅僨僀償傿僢僪偺奐敪僌儖乕僾偺儕乕僟乕偱偁傞儂價乕嫵庼乮William Hurt乯丄懄偪乽憿暔庡乿偼抝惈偱偁傝丄斀懳偵僨僀償傿僢僪偺乽曣恊乿偲側傞彈惈丒儌僯僇偼乽旐憿暔乿偱偁傞僨僀償傿僢僪偺乽垽偺懳徾乿偵夁偓側偄丄偲偄偆婎杮恾幃偼丄偦傕偦傕偺尨埬幰払傗嵟廔惗惉暔偱偁傞偙偺塮夋偺嶌傝庤払偺帩偮丄儐僟儎丒僉儕僗僩嫵揑偲尵偭偰椙偄偩傠偆嬌傔偰壠晝挿惂揑側乹憿暔庡亖恄乺娤擮傪偦偺傑傑斀塮偟偰偄傞偺偱偼側偄偐丄偲偄偆偙偲丅偦偺2丅杮嶌昳偼丄偦傕偦傕Aldiss偺忋弎偟偨抁曇彫愢偺塮憸壔傪嵟弶偵巚偄晅偒丄嵟廔揑偵惢嶌幰偺堦恖偲偟偰柤傪楢偹傞偙偲偵偼側偭偨屘S.Kubrick偵曺偘傜傟偰偄偰丄妋偐偵夋柺峔惉偺抂乆偵偦傟偑姶偠庢傟偨偺偩偗傟偳丄儔僗僩偺20暘偖傜偄偵偮偄偰尵偊偽丄Kubrick偱偁傟偽娫堘偄側偔丄僫儗乕僔儑儞偼堦愗柍偟偱丄戜帉傕尷奅傑偱愗傝媗傔傞偙偲偱丄彜嬈惈偼搙奜帇偟偮偮丄姶彎揑偵側傞偙偲偼嬌椡旔偗傛偆偲偟偨偱偁傠偆丄偲偄偆偙偲丅傑偁丄嫮偄偰尵偊偽丄偙偺曈傝偑彜嬈揑偵偼嵟傕惉岟偟偨偗傟偳拞恎偑敽傢側偄偲尵傢傟懕偗偰偒偨塮夋恖偱偁傞丄Spielberg偺尷奅側偺偐傕抦傟側偄丅晅偗壛偊傞偲丄偦傕偦傕恖椶偑巰柵偟偨悽奅偵偍偗傞乽岅傝庤乿乮幚嵺偵丄抝惈偺惡偱丄偄偐偵傕偍偲偓榖丄偲偄偭偨姶偠偺岅傝岥偱僫儗乕僔儑儞偑擖傞傢偗偱偡丅乯偲偼堦懱扤側偺偐丄偲偄偆栤戣傕偁傞丅傗偼傝丄儐僟儎丒僉儕僗僩嫵揑側堄枴偱偺丄慡偰傪嶻傒弌偟偨憿暔庡偲偟偰偺恄偺帇揰丄偲偄偆傕偺偑憐掕偝傟偰偄傞偺偱偼側偄偐偲傕巚偆丅偙偺揰傕傑偨丄婎杮揑偵儐僟儎宯偱偁傞Spielberg偺尷奅丄偲偄偆偙偲偵側傞偺偩傠偆偐丅埲忋丅乮2001/07/13乯