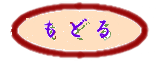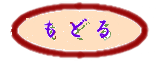Judith Butler著 竹村和子訳『アンティゴネーの主張 問い直される親族関係』青土社、2002.12(2000)
-
本欄では紹介の時期を逸したけれど、1990年に『ジェンダー・トラブル』(竹村和子訳、青土社、1999(1990))という、その年以降のフェミニズム、ジェンダー論、更には関連領域にまで多大な影響を与え続けている書物を刊行したJudith Butlerが、2000年に刊行したAntigone's Claim : Kinship Between Life and Deathの全訳である。
-
本書においてButlerは、ギリシャ古典劇の登場人物であるアンティゴネーに関する記述についての、G.W.F.HegelおよびJacques Lacanの一見したところ対照的とも言える読解を中心とし、加えてLacanがその構造主義的精神分析学において参照しかつ踏襲している親族構造論を作り上げたClaude Levi-Strauss(Leviの‘e’は右上がりアクサン付き。)の議論をも俎上に載せ、フェミニスト的視点からそれらの解体ないしは脱構築を試みつつ、同時にまた当該ギリシャ古典劇に対する別の形での読解可能性を模索する。
-
要するに、アンティゴネーはソフォクレスが著したギリシャ古典劇のなかで、兄にあたるポリュネイケースの埋葬を、時の王クレオーンの禁止に逆らって実行するのだが、これはHegel的に言えば公に対する私=家族・親族関係の表出であり、それはやがて乗り越えられるべきものとして解釈され、Lacan的にはアンティゴネーが体現する近親姦タブーが、無意識的に働く規範として家族・親族関係ひいてはその拡大である社会関係を構造的に支えるものとして解釈されることになる。
-
Butlerに言わせれば、そうした読み方の度重なる生産こそがまさしく、近親姦タブーや同性愛タブーをあたかも自明かつ自然なものとし、公的領域=国家と私的領域=家族・親族を分離しつつ前者が後者を支配下におく、といった権力構造を構築し更には支え続けてきたものなのだ、ということになる。そして、Butlerは、例えばアンティゴネーとポリュネイケースの関係のような形であたかも近親姦タブーが破られたかに見える状況が生じた場合に起こる家族・親族関係や、更に大きくは家族−国家あるいは私的領域−公的領域という一見自明視された関係が「攪乱」されていく様をこそ読み取るべきこと、そしてまたそこには別の社会関係が出現する可能性をこそ見出すべきなのである、と論を進めていく。
-
ところで、社会人類学を専攻し家族・親族論にも多大な関心を払ってきた私であるが、基本的には具体的などこそこの社会の事例をもって、例えば日本人や欧米人一般が抱き、かつまたそれを法制度などに適用している家族観・親族観をうち砕くことに腐心してきた人々が、社会人類学という学問領域には存在し、その功績は決して小さなものではないと、ごく個人的には考えている。
-
本書はそういう研究スタイルとは異なる批評という形で、つまりは現行の法制度作りに多大な貢献をしたHegelや、社会人類学内部では実のところ批判の多いLevi-Straussの議論を基本的に容認している、今日も人文社会諸学においてかなりの影響力を持っていると思われるLacanの精神分析学などを批判的に読み解きつつ、そういう作業を行なったもの、というように私自身は読んだのだけれど、その議論が実に啓発的かつ示唆的なものであることは間違いなく、フェミニスト批評、ジェンダー論をやっている人にとっては必読書であることを述べるとともに、ひいては家族・親族論やそれに関わる法制度等々に関心をもつ方々にも取り敢えずの一読をお薦めする次第である。以上。(2003/07/12)