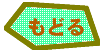元ネタを知っているせいもあり(ちなみに、本書の元ネタは、25頁まで読み進めれば誰でも気付く通り夢野久作のあの作品である。もっと後ろまで読むと、ドイツ出身のあの作家のあの作品であることが判明する。)、なおかつ瀬名のこれまでの著作のような最新情報が全く含まれていないせいもあって、やや平凡な作品であるように思われた。私見では、瀬名のストーリー・テリング能力やテーマ設定能力は、数多いるエンターテインメント作家の中で特に抜きんでたものとは言えず、結局のところ瀬名作品の面白さは〈これでもか!!!〉、と言わんばかりの最新知識・専門知識の羅列にあるのだと考える。Edward W.Saidの『オリエンタリズム』にもチラッと登場する19世紀半ばに活躍したフランスのエジプト研究家 Augusute-E(右アクサン)douard Mariette についての知識は増えたものの、その他に本書を通じて新たに私に付け加わった知識は殆ど存在しない。ついでに言えば、Marietteを主要な登場人物としたからには、藤子不二雄のテクストからの引用として述べられている「恐竜の話を描くんだったら、恐竜博士になるくらい恐竜について勉強しなさい。」(143頁)というようなことを忠実に実行すべきなのに、「謝辞」の部分には、Marietteに関してはフランス語で書かれた評伝の知人による日本語抄訳を参照した、という、正直と言えば聞こえの良いことが書かれていて(532-533頁)、何だか言行不一致な感じがした。付け加えるなら、153頁には、「第一資料にこだわってしまうのは、私が理系の研究室で論文を書く訓練を受けたためかもしれない。」と書かれているのだが、ここにおいても上述の「謝辞」の記述との間に齟齬が存在することは否めず、そもそも〈文系の人間は第一資料にこだわらない〉、というこの部分で暗に述べられた事実は私の知る限り存在しない。
話を進めよう。だらだらと作中内人物によって語られる「物語論」についても、「今更何を?」、という感じである。正直言って、古い。本書がオリエンタリストの一人であるMarietteを主要な登場人物にし、主な舞台を19世紀半ばのエジプトやパリの万国博覧会会場(言わずと知れた西欧の植民地主義=コロニアリズムの典型的な表出形態の一つである。)にした以上は、本書内でも言及されている文芸評論家達(柄谷行人や吉本隆明やRoland Barthes等)の文学理論ではなく(柄谷については、近年も誠に浩瀚な活動をされているので、注釈が必要だろう。ここでは1980年代までの柄谷、という意味である。)、やはり今日における文学理論の中でも極めて重要な位置を占めているポスト・コロニアル文芸批評の泰斗であるSaidが示しているような視座があってしかるべきではないかと思う。ひょっとして、「読んでいないのでは?」などと邪推してしまう。
そうそう、本書は結局のところ〈読者に感動を与える〉、ということを基本的に意図し、それは私に対しては全く失敗しているのだけれど、その目的のために素材としてエジプトにおける冒険譚を挿入していることは極めて問題で、それのみならず、例えばエジプトのような社会を扱うことによって生じる文学作品構築上の政治性の発露に関する何等の言及なり注釈なりが存在しないのは、今日の文学作品の在り方として、余りにも杜撰ではないかと思う。
また、冒頭の、本年が丁度没後100年にあたるかの偉大なる作曲家Giuseppe Verdiからの引用(?)は作品に深みを与えているけれど、「謝辞」の前にある「故・藤子・F・不二雄先生」への献辞は、余計なものであるし、はっきり言ってみっともない。もっと言えば、作中で再三なされる『ドラえもん』への言及も同様。こんなことは、わざわざ『ドラえもん』に出現する固有名詞や普通名詞を登場させるまでもなく読者には分かることで(要するに、「どこでもドア」的タイムマシンや、美宇という名の少女と彼女のペットである黒猫・ジャックの登場自体で、読者には本書が藤子・F・不二雄へのオマージュであることは瞬時に察知出来る筈なのである。)、これまた余計でありかつみっともないものである。
最後に唯一興味深かった点を述べる。本書における「フーコーの振り子」への再三に渡る言及は、500頁からのMichel Foucaultの言う所謂「古典主義時代」の博物学に関する言及と相まって、なかなかに趣深いものである。本書は夢野久作のあの作品と同時にUmberto Ecoのあの作品も元ネタにしているのだけれど、後者において、フランスの物理学者Le(右アクサン)on Foucaultへの言及はあってもM.Foucaultへの言及が恐らくは故意に避けられているのとは相反して、本書において瀬名が、直接名指しではないとは言いながら意図的か無意識的かは別としてかなり明白な形で後者への間接的言及を行なっているのは、色々な意味で面白い。何が面白いのかは、蛇足になるので述べないことにしよう。(2001/02/25)