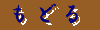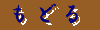Georges Dumezil著 丸山静・前田耕作編『デュメジル・コレクション 2』ちくま学芸文庫、2001.07
-
20世紀最大の神話学者の一人、G.Dumezil(例によって、eは右上がりアクサン付き)の、本邦初訳シリーズ第2弾である。『ゲルマン人の神話と神々』(松村一男訳、原著は1939年刊行)及び『セリウィウスとフォルトゥナ』(高橋秀雄・伊藤忠夫訳、同じく1943年刊行)の2編が収録されているのだが、読んでいる時間が無いので、例によって、紹介のみ。(2001/09/29)
夢枕獏著 『陰陽師 付喪神ノ巻』文春文庫、2000.11(1997)
-
岡野玲子によるコミック化、続いて本年度はNHKによるTVドラマ化(ご承知の通り、不測の事態により中断。「その位許してやってよー。」と言いたくなるのだが、まあ、「晴明さん」に前科があったらまずいか…。一応不起訴らしいけれど。)、そして今秋には滝田洋二郎監督・野村萬斎主演による映画化によって、「陰陽道」ブームは更に加速している昨今なのだが、本書はそれら全ての元ネタである、本書の著者・夢枕獏による「陰陽師」シリーズ第1弾『陰陽師』(文春文庫、1991(1988))、第2弾『陰陽師 飛天ノ巻』(文春文庫、1998(1995))に続く第3弾ということになる。
-
未入手の第4弾『陰陽師 鳳凰ノ巻』(文藝春秋、2000.6)および初の長編『陰陽師 生成り姫』(朝日新聞社、2000.3)が既に刊行されているこのシリーズについてはいずれきちんとまとまった文章を書きたいのだけれど、何せ時間が無い。ということで終わらせてしまいたいのだが、本書の末尾に思想家・中沢新一が「解説」を書いていて、その中で本シリーズにおける陰陽師・安倍晴明が基本的に「『シャーマニズム系』ヒーロー」でありながら、これまでに描かれてきた「『シャーマニズム系』ヒーロー」達と比べ、「どこかが決定的に違って」おり、それは「この晴明はひょうきんで、世俗のことにも裏からばかりではなく表の顔からも通じていて、人々にたち混じっても、まわりの人たちをたたずまいの異様さでたじろがせてしまうことがない」(以上、『』は原文では「」。)点にある、というのは、全く妥当な見解であると思う。実はその点こそが誠に興味深いのであって、それは、本欄で既に紹介済みの、「シャーマニズム」ブームの火付け役となりそうなコミック『シャーマン・キング』(集英社ジャンプコミックス)の主人公である自称「シャーマン」の「麻倉葉」だの、本年7月に発売されたコンピュータ・ゲーム『ファイナル・ファンタジーX』に登場するヒロインである「召還士・ユウナ」にも通じる事柄なのである。最近現れた一連の「シャーマニズム系」ヒーロー群が、確かに「癒し系」ないし「ユルユル系」に向かっている事実をどう捉えれば良いのか、ということは、確かに考察するに値する重要な問題なのである、と述べて終わりにする。(2001/09/29)
Octavio Paz著 牛島信明訳『弓と竪琴』ちくま学芸文庫、2001.06(1956→1967)
-
メキシコ出身の、ノーベル文学賞を受賞している詩人にして評論家であるOctavio Pazによる、余りにも重要な詩論の文庫版である。詩=ポエジーの持つ力について、その全てを書ききろうという著者の大胆な試みには、その試み自体がなされたことに感動を覚える。今回再読して発見したのは、この著者のシュルレアリズムへの傾倒ぶりの大きさであった。隠れシュルレアリストとも言うべき人類学者を扱った『クロード・レヴィ=ストロース』(鼓直訳、法政大学出版局、1988)などという本も書いているこの著者、実は第2次世界大戦と前後したフランス滞在時に、シュルレアリスト達と交流し、霊感を得、思想的支柱としていたのである。以上。(2001/10/05)
服部まゆみ著『この闇と光』角川文庫、2001.08(1998)
-
現代思潮社美学校出身の作家・服部まゆみが1998年に発表した長編の文庫版である。実に直木賞候補作。森の奥に囚われた盲目の王女・レイア。父が用意してくれる物語に耽溺する日を過ごすうちに、9年の歳月が過ぎる。そして、驚くべきことが明らかになり…、というお話。タイトルが示す通りの、闇と光の物語。凄まじい展開と、語られていることの奥深さには本当に目を瞠らされた。コンパクトな作品ながら、実に芳醇な、恐らくは1990年代終盤を代表する作品の一つと見なされることになるだろう、傑作である。以上。(2001/10/05)
築島謙三著『「日本人論」の中の日本人 上・下』講談社学術文庫、2000.9-10(1984)
-
本書は、文化心理学者である築島謙三が、室町期末のFrancisco Xavierから1970年代に大流行となった「日本人論」を、時代順を追って紹介したもの。そう、個々の「日本人論」者や「日本人論」のテクストに関する言及はあくまでも「紹介」と若干の「感想」に過ぎず、別段それらを時代順に並べることで何らかの命題なり何なりを取り出そうというような試みは一切なされていない。例えば、H.Passinの『遠慮と貪欲』について、築島はこう述べている。「著者の日本理解は、文化人類学者として異文化理解の確実な方法論に立っているので、記述は円滑であり、全編安心して読めるし、おもしろいし、どうしてこれが有名にならなかったのかふしぎである。」(下、259頁)他の部分はこれほどひどくは無いとしても、大同小異なもので、この一文からこの著作の「次元」は推し量れるであろう。以上。
二階堂麗人著『人狼城の恐怖 第一部=ドイツ編』講談社文庫、2001.06(1996)
二階堂麗人著『人狼城の恐怖 第二部=フランス編』講談社文庫、2001.07(1997)
二階堂麗人著『人狼城の恐怖 第三部=探偵編』講談社文庫、2001.08(1998)
二階堂麗人著『人狼城の恐怖 第四部=完結編』講談社文庫、2001.09(1998)
-
名探偵「二階堂蘭子」シリーズ第一部の掉尾を飾る巨編の文庫・改訂版の登場である。数年前に約3年にわたって講談社ノベルスで刊行されていた本書だけれど、これはやはり「一つの作品」なのだから、一週間くらいで一気に読んでしまうのが最も合理的かつ効率的なのであり、今回のような一ヶ月おきの出版は誠に喜ばしい限り。
-
さて、内容へ。本書はフランスとドイツの国境付近(所謂アルザス=ロレーヌ地方)に位置する双子の城である「人狼城」を舞台にした連続殺人事件と、それらが二階堂蘭子の活躍によって解決されていくプロセスを描く。扱われるライト・モティーフは「ハーメルンの笛吹男」、「人狼伝説」、「ロンギヌスの槍」といったおなじみのもの。こうしたヨーロッパの民間伝承的意匠に、「アルザス=ロレーヌ問題」、「ホロコーストにおけるユダヤ人虐殺」、「ナチスドイツによる秘密実験」等々に含まれる今日的なテーマ群(「人種」・「民族」・「生命倫理」といったもの。これ以上具体的な表現で書き込むとネタバレになるので自重する。)を重ね合わせつつ、物語は息を付く間もなく急ピッチで進行する。原稿用紙換算で4,000枚を超えるという圧倒的な分量を一気に読ませる手腕は、「第四部」の解説で笠井潔が述べているごとく驚異的としか言いようがないものである。取り敢えず、「一つの作品」としてのまとまりを持つ本格推理小説としては現時点で世界最長という本書は、ミステリ・ファンであれば(に限らず、と言いたいところだが…。)一応目を通しておくべきものである、ということを述べておきたいと思う。
-
最後に一つだけ著者も気付いているはずの問題点を指摘したい。すなわち、最終的に登場する「真犯人」が、余りに類型的なのにはやや不満であった次第。本書で扱われているのは、二階堂麗人自身が「第四部」末の「好事家のための後書き」の中で言及している笠井潔や京極夏彦等が追求しているテーマなのであり、更に言えば、二階堂は明らかに彼等ほどこのテーマに踏み込んでいない。以上、ネタ晴らしを避けるべく、ちょっと抽象的な言い回しになってしまったが、一つだけ具体的なことを述べると、例として、「何故にこの『真犯人』には『密室』を作る必要性があったのか?」という点についての掘り下げが不十分である、というようなことになる。笠井潔の『哲学者の密室』(光文社、1992)がとんでもなく優れた作品であるのは、この点をこれ以上不可能かも知れないくらいまで掘り下げてしまっていることにある。こういう点については、やはり「後書き」で予告された二階堂蘭子シリーズ・第二部で解消されていくのだろうことを期待しつつ、この辺で終わりにする。(2001/10/23)
金裕鴻(kim yuhong)著『ハングル入門』講談社学術文庫、2000.03
-
随分前に買って、その後ソウル旅行と前後して拾い読みしてきたのだけれど、結構難しい。これを読んだだけでは、韓国語なり朝鮮語なりは身に付きません。でも、必要なことが一応網羅されているので、おおざっぱに全体像をつかむのには良いでしょう。何しろ、文庫なので旅行に携帯するのに極めて便利なところが本書が持つ最大の利点です。以上、簡単な紹介のみ。(2001/11/07)
William Butler Yeats著 島津彬郎訳『幻想録』ちくま学芸文庫、2001.10(1925→1969)
-
アイルランドが生んだ偉大なる詩人、W.B.Yeats(本当に「イェイツ」と読むんでしょうかね?)が、1925年に出版し、1969年に出たその第2版の、1987年にパシフィカから出ていた邦訳版の文庫化である。読む暇がないので、パラパラと頁をめくっただけなのだけれど、なるほどこれは面白そうだ。うーん、暇を作らねば、と思った次第。全然書評になっていないけれど、いつものことなのでご勘弁。ということで(文体が「メール」的になっている…。)。(2001/11/07)
村山修一著『日本陰陽道史話』平凡社ライブラリー、2001.09
-
そのご健在を、本書の「あとがき」を通じて知って誠に嬉しく思った日本宗教史の大御所的存在、村山修一による簡にして要を得た陰陽道史概説である。何しろ、陰陽道ブームの昨今で、講義でも取り上げないといけない状況なのだが、この人の著作以外には十分な学問的達成度を持つ文献が存在しないとすら言えるこの分野、そしてこの人の著作が高額または極めて入手しにくい状況での、今回の文庫化は誠に有り難かった。さて、本書は、中国で誕生したと村山氏が言う陰陽道の、古代におけるその伝来と、ほぼ鎌倉期頃までに至るその発展プロセスを丹念に記述したものである。その後の変遷や、今日行なわれている神道の行事や各地の民間信仰への浸透などの記述がほとんど無いのが残念なのだけれど、それは無い物ねだりというものであろう。そういう仕事は、我々に残された、とも言いうるものだ。
-
なお、村山氏は上述のように「陰陽道とは、太古に発生した中国の民間信仰」(p.9)である、と概念規定しているのだけれど、中国には「陰陽道」という言葉も宗教体系もないはずで、確かにそのエッセンスを持つ道教や周易といったものは中国に古来から存在したとしても、「陰陽道は中国において発生したものである。」としか読めないこういう記述は、要らぬ誤解を招きかねないものだということは述べておかねばならない。より一般的には、陰陽道とは、例えば窪徳忠氏によって、「中国の讖緯説(しんいせつ)や陰陽五行説などに主な淵源をもつ、古代日本における吉凶禍福を判断する呪法,もしくはその信仰をいう.」と概念規定されている。更には「文字の類似から,中国の陰陽説(いんようせつ)もしくは陰陽思想と陰陽道とを混同して,同一視したり,陰陽説を陰陽道と呼んだりする人がいるけれども,これは誤りで,両者ははっきりと区別しなければならない.」(以上、窪徳忠「陰陽道」『宗教学辞典』東京大学出版会、1973、p.75)とも述べられているのだけれど、村山氏は、正しくそういう混同をしてしまっている張本人なのである。以上。(2001/11/07)
宮本常一著『女の民俗誌』岩波現代文庫、2001.09
-
在野の民俗学者・宮本常一によって、1937年から1971年に書かれた「日本の女性」をテーマとしたテクスト群を再編集したものである。思想史上極めて重要なこの民俗学者の女性観を知る上での誠に参考になる本書のような書物の出版は、そのこと自体が大変ありがたいと同時にまた、初期の論考において柳田國男のエピゴーネンであった宮本が、それこそ日本各地を「歩き回る」ことにより、思想的な「師」を乗り越えて独自の視座を獲得していく様が明瞭に読み取れ、その点が極めて興味深かったことも記しておく。
小泉文夫・團伊玖磨『日本音楽の再発見』平凡社ライブラリー、2001.11(1976)
-
民族音楽学者・小泉文夫と、作曲家・團伊玖磨による対談である。元本は1976年に刊行。「日本音楽の」というタイトルにも関わらず、内容は世界中の音楽についての誠に多岐にわたるもの。博識をもってなる二人の議論はさすがにかなり専門的な領域にまで踏み込んでいて、大変参考になった次第。なお、小泉が日本における西洋中心主義の音楽教育を改革すべし、と言い続けていたのは周知のことであるのだけれど、その死後十数年を経ても、結局こと音楽教育については何も変わらなかったのもこれまた周知の通り。でも、カラオケ等の普及による「独自」の音楽文化の進展と、西洋以外の音楽文化が何時の間にかどんどん入り込んでしまった状況は、要するに別段音楽教育がどういうものであっても、それとは関係なく世の中は動いていくのだということを図らずも証明してしまっているわけだ。そうそう、私個人としては、小学校や中学校でやっている「音楽教育」なんていうものは全く無用の長物なのであって(何と言っても、教師のレヴェルが低過ぎるのが最大の難点。でも、それを育てる教師自体が数少ないというのが現状なのだ。)、あんなものはやめてしまえば良い、と本気で考えている昨今である。そうそう、あんなものは愚劣の極みであると同時にまた、日本の音楽文化形成に何の影響も与えていないのだから。(尚、そうだとすると、「人畜無害だから許せる」、というのもあるのかも知れないが…。)ついでに言うと、その時間を使って英語でも教えた方が、後で役に立つこと請け合いである。ということで、終わり。(2001/11/29)