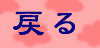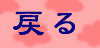島田雅彦著『忘れられた帝国』新潮文庫、2000.1(1995)
-
少年時代の作者本人とおぼしき人物が語り紡ぐ自伝的郊外小説である。島田氏は1961年生まれなので、時期的には高度経済成長期の真っ直中であった1960年代から70年代前半頃の、さらに地理的には東京近郊(多摩川周辺)が舞台となる。タイトルからして、民俗学者・宮本常一の『忘れられた日本人』(岩波文庫だと思う。どっかに埋もれているのだが、発行年を調べる気にならない。)を彷彿とさせるものなのだが、中身も同様。そう、番号をふられた174の節からなり、妖怪や異人が跳梁跋扈するいにしえの東京近郊を描いた本書は、あたかも柳田國男の『遠野物語』のごとく、「こちら側」と「あちら側」の「間」に関する、民俗学的(ないしは都市民俗学的)なスケッチ、とでも言うべきものなのである。なお、本書のラストにはこの本から始まると作者自身が述べる「帝国シリーズ」の、盲目の語り部「アンジュ」が登場することを付け加えておこう。蛇足ながら、『まぼろしの郊外』の著者である宮台真司による解説もなかなかに面白いものであった。
宮台真司著『世紀末の作法 終ワリナキ日常ヲ生キル知恵』新潮文庫、2000.3(1997)
-
本書は、社会学者・宮台真司が、1990年代前半の日本において重要な都市民俗の一要素であった「ブルセラ」や「テレクラ」(これは一発で変換された。)などを中心的モティーフとして論じたコラム・エッセイを集大成したものである。タイトルに従えば、本書は既に終わってしまった世紀末に生きる知恵を提示するもの、とも取れるのだけれど、著者の立場はそういうものではなく、むしろ世紀末の日本をしたたかに生きる「女子高生」その他に学べ、とでもいうもの。繰り返しになるけれど、世紀末はもう終わってしまったので、本書には問題提起の書としての存在価値はもう無いのだけれど、随所に見られるあまりお説教臭くないお説教は別として、1990年代前半の都市民俗論として読めばそれなりに貴重なデータを開示しているとも言える。それは端的には、98ページから始まる、「東大生」へのアンケート調査結果のことである。逆に言えば、その他のデータ提示(要は「女子高生」や「主婦」などに関するもの)が雑なのは、コラム・エッセイとして公表されたものであるということからやむを得ないのかも知れないとは言え、全く残念である。それは、全ては事実の可能な限りの客観的把握から始まる、と考えるが故。それは置くとして、「援助交際」をある種の諦念をもって〈容認〉する宮台にはある程度共感できるのだが、「レイプ」について否定も肯定もせず、更にはバクシーシ山下のレイプ・ヴィデオのような愚劣なもの(というのは、作者がそれを自覚的かつ確信犯的に行なっているからである。必ずしも私の評価ではない。)を手放しで〈礼賛〉してしまうのは余りにもまずい。私もいわゆる「有害映像」のごときものへの規制は無意味ないしは結局のところ負の効果しかないと考えるのだが、そうしたものの存在は認めつつも、それはあくまでも事実としてのことに過ぎず、そこに価値判断を持ち込む愚を犯す気にはならない。アカデミシャンでもあるはずの宮台の上記のような態度・姿勢は断罪されるべきものであると考える。
大原まり子著『アルカイック・ステイツ』ハヤカワ文庫、2000.11(1997)
-
大原まり子によるスペース・オペラ。太陽系を統べる卑弥呼のごときカリスマ性と予見性を備えた「ジェネラル・アグノーシア」と、宇宙航行種族の機関・「権威評議会」との間の、権謀術数に満ちた駆け引きを中心に描く。アグノーシアという名前から分かる通り、本書は端的にグノーシス主義をメイン・モティーフにしている。直線的時間論と、28世紀の太陽系に出現した古代銀河帝国の蜃気楼であるアルカイック・ステイツの持つ円環的時間論の対立がなかなかに興味深い。なお、68頁では「マルセル・モース」を「文化人類学者」、143頁では「マリノフスキー」を「経済人類学者」として表現しているけれど、どちらも社会人類学者である。28世紀においてはそういう区分は厳密さを失っている可能性もあるけれど、それならどちらも「人類学者」と表現するべきでしょう。それは兎も角として、登場人物たちが巡らせる、アルカイック・ステイツが太陽系に与える、見返りがあるのかどうかはっきりしないある恩恵に関する経済人類学的な思考はこれまたなかなかに興味深いものであった。(2001/04/14)
島田雅彦著『そして、アンジュは眠りにつく』新潮文庫、2000.8(1996)
-
盲目の語り部、アンジュを主人公とする表題作を含む9作品からなる短編集。「茶の間」、「郊外」を基本モティーフに、官能的で感傷的な島田ワールドが展開する。取り敢えずは、表題作が重要である。(2001/04/17)
島田雅彦著『君が壊れてしまう前に』角川文庫、2001.2(1998)
-
このところ近年の島田雅彦作品を連続して読んできたけれど、これが一番面白かった。郊外に住む14歳の中学生により、1975年の一年間にわたって綴られた日記という体裁をとる本作品には、表現者である島田雅彦のパワーの全てが注ぎ込まれているように思う。「ダダ・クラブ」なるバンドを結成してダダ的インプロヴィゼーションの録音に取り組み、『愛のダダ』なるダダ映画を創ってしまう主人公とその悪友たちには、爆笑と同時に羨ましさを感じることを禁じ得なかった。こういう「濃い」中学生活が送りたかったものである。現実はこんなには楽しくないものだ。それは兎も角、本書は基本的に、現実世界との整合性を持つことを余儀なくされ始める時期である14-5歳位の少年少女たちが、その現実の前で右往左往し、迎合か破壊(他者と同時に自己破壊も含む。)かを迫られ、揺れ動いている状況を描いている訳だけれど、そういう誰もがいつの間にか通過してきたはずの地点を、うまく作り出せないでいるかのような今日の社会フレイムみたいなものにはやはり問題があるのだが、かといって1970年代に戻れだの、もっとひどいのになると1945年以前に戻れ、などということを言っている場合でもない。ではどうすれば良いのか、という問いには、私自身何も回答を与えることができないし、する積もりもないのであった。(2001/04/17)
藤原伊織著『ひまわりの祝祭』講談社文庫、2000.6(1997)
-
電通社員である超寡作作家・藤原伊織の1997年に刊行された長編である。フィンセント・ファン・ゴッホがアルル滞在時に描いた8枚目の『ひまわり』(基本的には存在しないことになっている。)を巡って、銀座1丁目の持ち家に住み無為徒食の生活を送る元商業デザイナの周辺で繰り広げられる権謀術数を描く。テンポ、台詞の妙味、文体の3拍子が揃わないとどうにもならなくなるのがハード・ボイルドだと思うのが、本作品はそれを難なくクリアし、極上のエンタテインメント作品に仕上がっている。特に、甘党の、高校時代には天才の呼び声もあった元絵描きであり、しかも極めて洞察力に富む主人公の人物造型が楽しい。この「甘党」、という設定がラスト近くできちんとした意味を持ってしまうあまりの作為性も、まあ、お茶目ということで、単純に楽しむべきところなのかも知れない。(2001/04/27)
Edward Sapir著、安藤貞雄訳『言語 ことばの研究序説』岩波文庫、1998.11(1921)
-
少々刊行から時間が経ったけれど、教育的な意味を少しばかり持っている本サイトで紹介すべき基本的な文献なのでここに掲げることにする。本書は人類学との関わりの深い天才言語学者E.Sapirによる生前刊行された唯一の著作であり、かつまた言語学上の普及の名著の安藤貞雄による新訳である。第2章から第8章までの、微にいり細にいりといった言語の諸要素に関する定義付けや分析については、参照されている膨大な数の諸言語に通じている訳でもなく、ましてや言語学を専攻している訳ではない私にとっては読むのが大変なのだが、第1章「序論 ―言語の定義」、及び第9章から第11章までの言語社会学的あるいは言語人類学的な考察は誠に参考になるものであった。
山口雅也著『ミステリーズ《完全版》』講談社文庫、1998.7(1994)
-
これも刊行から時間が経っているけれど、エポック・メイキングな作品なので紹介しておく。本書はミステリ作家山口雅也による10編の短編からなる作品集である。メタ・ミステリ、変格ミステリ、純粋ホラーといった多彩な内容で、しかも全体が一つのコンセプトによってまとめられている。確かに良く出来た短編集であると思う。それはそうとして、奥付にある「MARK BEYER氏の連絡先をごぞんじの方は下記出版部までおしらせ下さい。」というのはどういう意味なのだろう?ご存じの方はご一報下さい。
川田順造著『口頭伝承論 上・下』平凡社ライブラリー、2001.04・2001.05(1992)
-
個人的には、20世紀後半における人類学上の成果として最も重要なものの一つなのではないかと考える、川田順造の論文「口頭伝承論」を含む著名な論文集の文庫化である。元になった河出書房新社版は長らく絶版で、私も図書館で借りて読んだ口なのだが、手許に置いておきたい書物の、こういう形での再刊は誠にありがたい。西アフリカや日本における音声によるコミュニケーションの諸相を丹念に読み解いた本書の分析手法とその誠に深い考察は、私の学位論文にも多大な影響を与えていることを述べておきたいと思う。下巻末には藤井貞和による書き下ろし解説「暮れようとしない太陽」が付いていることも付記しておく。以上、簡単ながら。(2001/05/09、06/02に追記。)
歌野晶午著『死体を買う男』講談社文庫、2001.01(1991→1995)
-
ミステリ作家・歌野晶午が「家」三部作に続いて書いたミステリ長編の一つである。カッパノベルス→光文社文庫という流れを経て、今回講談社文庫に入ることになった。江戸川乱歩の未発表作品が発見され、雑誌に掲載される、という発端で始まるこの作品、乱歩と詩人の萩原朔太郎が謎解き役となる本格推理ものなのだけれど、ある意味とても文学的。山田正紀などが書いているいくつかの作品とも通じ合うような、気品漂う優れたミステリ作品だと思う。(2001/05/10)
笙野頼子著『極楽・大祭・皇帝 笙野頼子初期作品集』講談社文芸文庫、2001.03(1994)
-
群像新人賞を受賞した1981年の作品「極楽」と、その同年に発表された「大祭」および1984年発表の長編「皇帝」という3作品からなる文字通りの「初期作品集」である。「私小説性」、「純文学性」を極限まで煮詰めた、という感さえある文体とモティーフは、ある意味ですさまじい。最早「文壇」において一定の地位を占めるに至ってしまったこの著者の、文学的出自や系譜を考える上で貴重な本書の文庫化は、純文学作品があっという間に絶版になりがちなご時世において誠にありがたいことではあるのだが、300頁足らずで1,300円という値段は一体何なの、という詰まらない苦言も述べずにはいられないのであった。(2001/05/29)
蓮實重彦・山田宏一著『傷だらけの映画史 ウーファからハリウッドまで』中公文庫、2001.03(1988)
-
1988年に出たヴィデオ・シリーズ『リュミエール・シネマテーク』全十巻に付録として収録されたブックレットに収められていた幻の対談集の、待望の文庫化である。そもそもこんなものが存在していたことすら知らなかったのだが、その内容は主として1930年代から1950年代までのドイツ−フランス−英国−米国を中心とした、近年(1980年代ということになる。)再評価された監督・プロデューサ達や、或いは既に巨匠として認められて来た監督達の隠れた傑作群に新たな光を当てつつ、同じく既に評価の定まった作品群にも新たな視点から切り込み直す、というもの。対談者の圧倒的な知識量には驚嘆するばかりだけれど、まったく、世の中にはまだまだ未見の、しかも観なければならない映画が山のようにあるのだな、と思い知った次第。こういうものを読んでしまうと、このサイトで私自身が行なっている映画評なんてしょうもないものだ、と自分が惨めになって来たりもするのだが、まあ、この二人は別格なのだから、と開き直りつつ、私自身もさらに研鑽を積みながら、より高度な評論を目指したいものだ、などと、気分を改めたところである。(2001/05/29)
Jorge Luis Borges著 土岐恒二訳『永遠の歴史』ちくま学芸文庫、2001.03(1953→1986)
-
アルゼンチンの文筆家、J.L.ボルヘスによる珠玉のエッセイ集である。何が言いたいのか今ひとつ良く分からない「永遠の歴史」はともかくとして、集合論やF.ニーチェにおけるそれぞれ無限、永劫回帰について批判的に論じた「循環説」および「円環的時間」、あるいは翻訳という作業を論じつつ、オリエンタリズムにも密かに言及しているかのようにさえ読める「『千夜一夜』の翻訳者たち」の計3本は大変興味深く読んだ。短編小説家として有名なボルヘスであるが、その小説技法の根っこにあるものを知る上で、極めて示唆に富む文献である、と述べておきたい。(2001/06/11)
山口昌男著『天皇制の文化人類学』岩波現代文庫、2000.01(1989)
-
タイトルに相反して、現実に存在する「天皇制」への言及が、やや遠回しかつあくまでも象徴論的レヴェルにとどまっているのが気になったのだが、権力や政治一般についての象徴人類学的考察として読めば、私個人としては1960年代後半から1980年頃まで日本の文化人類学をリードしていたと考える山口昌男の、一つの到達点を体現した好著である、と言って良かろう。「一つの」、というのは、山口は1990年代以降、歴史人類学に参入し、浩瀚な活動を繰り広げ、今日に至っており、もう一つの到達点が1990年代の後半に存在すると考えるからである。以上。(2001/06/22)
Georges Dumezil著 丸山静・前田耕作編『デュメジル・コレクション 1』ちくま学芸文庫、2001.05
-
20世紀最大の神話学者の一人、G.Dumezil(例によって、eは右上がりアクサン付き)の、『ミトラ=ヴァルナ』(中村忠男訳、1940年初版、1949第2版)及び『ユピテル・マルス・クイリヌス』(川角信夫他訳、1941年刊行)の本邦初訳を、廉価な文庫にまとめたものである。「廉価」とは言え、1,700円(税別)もするのだが…。それはともかく、今後更に3冊が加わることになっているこの全編本邦初訳という「デュメジル・コレクション」には期待している。なお、ついでではあるが、20世紀神話学の精髄とも言うべきC.Levi-StraussのMythologiques全4巻も早く邦訳を出していただきたいところ。無理かな?英訳版については、既に絶版となっているFrom Honey to Ashes(これについては中古本が7月中には入手できそう。)以外の3冊を手に入れているが、何しろ読むのは大変。翻訳に当たっているみなさん(これについては、みすず書房の本に付された広告を見ると名前が分かってしまうのである。)、よろしくお願いします。(2001/06/22)
Robert Hertz著 吉田禎吾・内藤莞爾・板橋作美訳『右手の優越 宗教的両極性の研究』ちくま学芸文庫、2001.06(1907-1909→1980)
-
本書は、垣内出版から1980年に邦訳が出版され、その後版切れとなり、再版もされず、更にひどいことには私が在籍していた3大学の図書館に入っていない関係で(なんでなんだー!!!)、上智大学図書館に赴いてコピーする他はなかった、第1次世界大戦で若くして戦死を遂げた、フランス社会学派の重要極まりない一員であるR.Hertzによる、象徴人類学の先駆的論文2編からなる著作の、待望久しい文庫化である(あー、長いセンテンス…。)。その2編とは、「死の集合表象研究への寄与」(1907)および、「右手の優越」(1909)であり、これらの論文が20世紀後半の象徴人類学に与えた影響力は計り知れないものがある。なお、文庫化に際しては、吉田禎吾氏による45頁にもおよぶほとんど一論文とも言うべき「文庫版解説」が付されており、私はこれを読むために購入した次第。そんなところで紹介を終える。(2001/06/22)