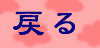まあ、それは兎も角、箱抜けマジシャンの草分け的存在であった初代・引田天功へのオマージュとも言える本作品は、誠に良く出来た密室トリックごり押しの本格ミステリである。(とは言え、のシリーズでは本作以降、「トリック」の扱いに大きな変化が生じることになる、ということも述べておきたい。)尚、カヴァーの写真と、冒頭の埴谷雄高『死霊』からの引用の対応関係もなかなかに爆笑ものである。ついでながら、二代目・引田天功を解説「魅力はミスディレクション」の執筆者として引っ張り出した講談社・文芸図書第三出版部の力業にも驚嘆した次第。(2000/12/21)
舞台は22世紀の太陽系。色々な意味で絶滅寸前のケニアに住むキクユ族の一部は、あらゆる害悪をもたらし続けると彼等が考えるヨーロッパ文明(勿論全ての近代文明の発明は必ずしもヨーロッパ人の手によるものではないけれど、本書の語り手、後述のコリバに従って以下全ての近代文明を「ヨーロッパ」という語で表象する。)から離れ、自分達の「伝統」的生活様式が実践可能なユートピアを求めて小惑星に集団移住する。(移住の際の宇宙空間の移動や、小惑星にかつてのキクユ族の生息地を模して造られた居住地・キリンヤガの設計・施工・管理・保全は全てヨーロッパ人乃至ヨーロッパの技術によるものである。これがこの物語の最大の皮肉となっている。)こうして創り出された「ユートピア」を統轄し、キクユ族の「伝統文化」がヨーロッパ文明に冒されることから守ろうとする、祈祷師にしてキクユ族の民俗知識のただ一人の伝承者・コリバによって紡がれるこの物語は、次第にヨーロッパ文明に浸食され、ヨーロッパ化していく「真の」キクユ族の終焉を冷徹な眼で見据えつつ、描き出す。
ところで、この物語は実は既に現実のものである。例えば南米のネイティヴ・アメリカン居住地などでは、人工的に保護された区域内に、それこそ旧来の生活様式を守り続ける人々が存在する。これは、人類学を専攻する私のような者にとっては特に、真剣に考えるべき問題を孕んでいる。その問題とは、要するに、旧来の生活様式を守り続け、その社会成員としてのアイデンティティを貫き通すか、或いは別の社会の生活様式(近代テクノロジー、文字、その他)を取り入れ、当該社会の成員としてのアイデンティティを捨てるか、という二者択一にある。食糧の生産性や安定性、或いは医療の効率性や安全性などの点においては、近代テクノロジーに勝るものはないと思うのだが、問題はそれを受け入れることによって失われる、例えば〈キクユ族〉の一員として存在していること自体の持つ意味なのである。
ケンブリッジ大学を出、イェール大学で二つの博士号を取得したエリートという設定の主人公・コリバは、当然のことながら、上記のようなディレンマにぶち当たる。コリバの選んだ道は明快である。それは、頑なに前者の道を貫くことを自らに、そして一緒に移住したキクユ族の同胞達にも強要するということ。ちなみに、それを強要出来るのは彼が小惑星の軌道に変更を加えてキリンヤガの気象を思い通りに出来る、即ち住民の生殺与奪権と、外部世界についての情報を一手に握っていることによるのだが、これはコリバが、ポスト・コロニアル批評などで良く取り上げられるW.Shakespeare作の『テンペスト』におけるプロスペロー的立場にあることを意味する。
ヨーロッパ人にして入植者であるプロスペローを主人公とする『テンペスト』とは異なり、ヨーロッパで知識を得た植民地エリートを主人公とするこの物語においては、前述のようにして殆ど無理矢理に構築されたユートピアは、コリバの威信が失われることによっていとも簡単に崩壊する。即ち、物語は、キリンヤガがヨーロッパ化し、「真の」キクユ族の終焉を暗示して終わる。
この作品において、著者Resnickは、上記二者択一のどちらかが正しい、などということを安易に語ったりは決してしていない。それは、コリバが、キクユ族の「伝統」を守るべく孤独な闘争を続けながら、時折「私は正しいのだろうか?」的な自己懐疑を記述の中に挟んでいることからも伺い知ることが出来る。こうして、この誠に寓意に満ちた物語を、物語の当事者に、自らの行為についての悔恨や自嘲までも織り込みながら語らせる、というスタイルを採ることによって(殆ど離れ業である。)、あくまでも問題提起に徹したこの作者のポジションの取り方には共感する。それは、最終的には、例えばキクユ族が自ら決定すべき事柄であると、私個人は考えるからだ。(2001/01/09)
ところで、動物行動学や寄生虫学の勉強にもなってしまう本書は、色々な意味で推薦したい書物であるのだが、惜しむらくは、参考文献リストが省略されている点である。私のように、〈あとがきから読み始める〉などという愚行を決して働かない読者も存在することも忘れないで欲しい。尚、作中にかなり怪しげな文化人類学者とその助手が登場するけれど、こんな人は私の周りにはおりませんので、ご安心の程。変な先入観を持たれてしまうと困るので、ここにはっきりと言明しておく。というのも、最近学生のリポートを大量に読んだのだが、彼女等がその読んだ本の内容を鵜呑みにしているケースが誠に多いのにショックを受けたからである。批判・批評精神を養って欲しいものだとつくづく思う次第。(2001/02/24)