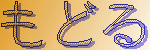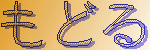Mircea Eliade著 堀一郎訳『シャーマニズム 古代的エクスタシー技術 上・下』ちくま学芸文庫、2004.04(1951→1968→1974)
-
数あるシャマニズム研究書の中でも最重要にして恐らく最大のヴォリュームを持つ本書だが、冬樹社から出ていた日本語訳は長らく絶版。古書店でも7万円で売られているのを見たことがあったのだが、この度ようやく文庫という最も手に取りやすい形で再刊の運びとなった。上下で3,000円(税別)はちょっとばかり高いかも知れないが、一応シャマニズム研究史上の転回点というか、要はシャマニズム研究は「エリアーデ前/エリアーデ後」みたいな分け方さえ出来るものなわけで、それくらい重要な書物だということを強調しておきたいと思う。(2004/06/18)
John Dickson Carr著 田口俊樹訳『仮面劇場の殺人』創元推理文庫、2003.09(1966)
-
本格ミステリの大御所的存在ディクスン・カーが1966年に発表した長編の本邦初訳ということになるらしい。原題は‘Panic in C Box’。結構長い作品なのだが、要するにとある劇場で衆人環視のもとに行なわれた石弓を用いた女優殺しを巡っての、ご存じフェル博士等による推理の過程を描いたもの。実のところ本作品は余りにも冗長、即ち余計なことがたくさん書き込まれているような気がしたのだが、逆に言えば登場人物の造形に物凄くこだわった結果とも言えるわけで、基本的に人物像はさほど細かく描かない純粋パズラーとは違うややコメディ仕立ての本格ミステリに仕上がっている次第。そのキャリアの最終段階に、こういう方向性を打ち出すような境地に到達していたのか、と感慨に耽ったのであった。(2004/06/21)
井上夢人著『メドゥサ、鏡をごらん』講談社文庫、2002.08(1997)
-
ジャンルを特定できない、などという言い方があちこちでされている本書だけれど、要するにメタ・フィクショナルな意匠を持ったホラーなのだ、と言い切ってしまいたい作品。この作品を読み進めるうちに、メタ・フィクションの作り手には二種類あって、読者を思考の迷宮に誘う難解なものを志向する人たちと、井上のように一応純粋なエンターテインメント作品として読める分かり易いものを志向する人たちがいるのかな、などと考えた。そうそう、本書に記述されているのは決して難しい話ではない。実のところ、この人が大半を書いたことになっているらしい岡嶋二人の『クラインの壺』辺りの方が、物語としての複雑さとか、インパクトといった点で遙かに上のような気がする。まあ、決して詰まらない本ではない、というか面白い本なので是非ともご一読の程。以上。(2004/07/04)
J.M.Coetzee著 土岐恒二訳『夷狄(いてき)を待ちながら』集英社文庫、2003.12(1980)
-
2003年度のノーベル文学賞受賞者である南アフリカ共和国出身の作家J.M.Coetzeeが1980年に発表した作品Waiting for the Barbariansの邦訳+文庫化である。何とも凄まじい小説だな、というのが個人的な感想。ちょっとだけ概要を示すと、とある「帝国」の辺境が小説の舞台。辺境に元々住む人々や、それを実効支配する為に駐屯している軍人その他の間に蔓延する「夷狄」(=野蛮人)が攻めてくる、という噂がまことしやかに説かれる中、時折捕捉される「夷狄」達には日夜凄惨な拷問が繰り返され、そんな中彼らにシンパシーを感じつつ、帝国の在り方に疑問を抱く主人公の民政官も、夷狄達に通じているのではないかという疑いをもたれてやがては捕われの身となり、拷問を受ける羽目に、というような何とも陰惨な物語。ポスト・コロニアル文学というジャンルの恐らく顕在化し始めた時期の作品だけれども(先行者には1961年にLes damnes de la terreを書いたFrantz Fanonがいるわけだが…)、植民地支配なり、あるいはそもそもがそれを行なう国家なるものが、この小説では「夷狄」という形で措定されるような外部あるいは他者の存在無しには立ち行かないという、何とも皮肉なロジックとでも言うべきことを見事に活写した作品として読んだ次第である。以上。(2004/07/25)
二階堂黎人著『悪魔のラビリンス』講談社文庫、2004.06(2001)
-
「二階堂蘭子」と「魔王ラビリンス」なる悪党との熾烈な闘いを描く中編2作を中心とした作品集。両者の激突はこの2作(+オマケ)では完結せず、『メフィスト』での連載が終了した『魔術王事件』(仮題?)というこの秋刊行予定の作品に引き継がれることになるのだが、それはさておき、江戸川乱歩へのオマージュともいうべきこの2作品、どちらも密室状況での人の死を巡る謎解きが本題で、純然たる本格ミステリとなっているところがミソなのだと取り敢えず述べておこう。第1部の素晴らしく精巧なトリックに比べ、第2部は「うむう、これってバレバレじゃん…」という位見劣りするものな所が難点といえば難点なのだが、取り敢えず続編に期待したいと思う。以上。(2004/07/26)
藤木 稟著『テンダーワールド』講談社文庫、2004.06(2001)
-
『イツロベ』(講談社文庫、2002(1999))の一応続編という位置づけになるのではないかと思われるけれど、そうそう一筋縄ではいかない基本設定を持つ大長編サイバー・パンク小説である。「非同期式量子コンピュータ」=「タブレット」なる、今日の情報化社会に更なる変革をもたらすこととなる装置が発明され、大量に出回るようになったAT(アフター・タブレット)という時代設定のもと、アメリカ合州国で多発する変死事件、その背後にちらつくカルト「ハイネスト・ゴッド」、どうやら鍵を握るらしい『イツロベ』にも登場したゲーム・ソフト『ゴスペル』等々の謎を解くべく活躍する、FBI捜査官やジャーナリストが出逢い、見出すことになる驚嘆すべき事実とは…。というお話。まあ、兎に角この作家の持っている情報量は途轍もないものだし、AT初期のアメリカという舞台設定の細かさにも賛嘆を禁じ得ない。この作品においても解明されていない謎も多々あって(というか、増えてしまった感が…)、まだ続きがあるような感じなので、楽しみにしておこうと思う。以上。(2004/08/13)
森博嗣著『恋恋蓮歩の演習 A Sea of Deceits』講談社文庫、2004.07(2001)
-
Vシリーズ第6弾の文庫化。かなり長い前置きの後で本編が開始。それは伊勢湾を航行する豪華客船での名画及び男性消失事件の謎に瀬在丸紅子らお馴染みの面々が挑む、という内容。まあ、それだけではないのだが…。私見では、第5弾辺りからこのシリーズもかなりその様相を変えてきているように思うのだけれど、それは要するに何らかの殺人事件に関する紅子による謎解きよりも、元々は謎解き役の一人でもあったはずの保呂草潤平の本職である泥棒稼業の方に記述の重心がシフトしている感がある、ということである。ちなみに、本シリーズ全体の記述者がそもそも保呂草に設定されている辺りはかなり凄いことなわけで…。まあ、先入観を持たれるのもなんなので、この辺にしておきます。以上。(2004/08/15)
坂本龍一・天童荒太『少年とアフリカ』文春文庫、2004.04(2001)
-
世界をまたにかけて活躍するご存じ坂本龍一と、家族をテーマとする作品群で多くの読者に圧倒的な支持を受けている天童荒太という、言ってみれば両者がそれぞれ持ちうるグローバルな視点とドメスティックな視点がうまくマッチした対談。企画者の意図もその辺にあるのだろう。単行本収録の2000年に行なわれた2回の対談に加え、あの「911」後の、そして相変わらずイラク国内では戦闘が続く2004年という年に行なわれた語り下ろし対談を含む。さほど深いことは述べられていないのだが、坂本氏が柄谷行人に極めて近い立場にいるらしいこと、天童氏が実にいい人だ、ということは良く分かった次第。家族社会学などというものにも手を染めている私としては、天童の書いた『家族狩り』も読まなければならない。以上。(2004/08/23)
山口雅也著『続・垂理冴子のお見合いと推理』講談社文庫、2004.08(2000)
-
著者の出身地である横須賀市がモデルの「観音市」に住む垂里家の面々が活躍する本格ミステリ短篇集第2弾の文庫化。同著者の作品である『日本殺人事件』や『キッド・ピストルズ』シリーズに似た、ほのぼのとしてなおかつ卓抜なトリックを含む、という独特のテイストを持つ、ある意味この人のお家芸的作品群となっている。こういうものを書かせたら、この人の右に出るものはいないわけで、誠に貴重な存在なのである。以上。(2004/08/15)