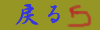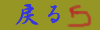上野千鶴子編『構築主義とは何か』頸草書房、2001.02
-
結構昔からそういう考え方、見方はあったのだが、近年「構築主義」という名前で大体まとめられるようになってきた人文社会学系の一大パラダイムのようなものを振り返り(回顧し)、今後の方向性を示そう(展望しよう)とする、論文集である。
-
さて、「構築主義」という視座が基本的前提とするのは、我々が生きている、ないし認識している「現実」というものが、「自然」にそうなったものでも、もともとそのようにあるものでもなく、<社会的に構築されたものである>、ということになる。これは、特に新しい見方・考え方ではなく、その淵源を辿っていけばカント(I.Kant)が行なった認識論上のコペルニクス的転回だの20世紀初頭における言語論的転回だのに行き当たる事柄。
-
それは措くとして、20世紀後半において基本的にこういうことを前提として行なわれてきた、人文社会学において実のところかなり大きな部分を占めていたのではないかと私などは考えてしまう、<社会的に構築されたものの構築のされ方>を問題にした研究実践が、次第に「構築主義」の名の下にまとめられ、それと対立する立場である「本質主義」との対決という図式で論争がなされてきたようなのだけれど、そのあたりのことが本書では主として社会学を、加えて文学、心理学、人類学、歴史学等々を専攻する論者達によりつぶさに語られる。
-
「あとがきに代えて」の部分で編者自身が述べているように、本書に収められた論考が、主として社会学的内容を持つのは、「構築主義」という立場が上に述べた通りものごとの「社会的構築性」を問題にしてきたのだから、ごくごく「自然」なことではないかとも思う。これに加えてもう一つ、こちらの方がより気になったのだが、実のところ本書に掲載された大部分の論考が、ジェンダー論ないしフェミニズムに言及するか、そのものを扱っているのだけれど、これは本書の内容が余りに限定されている、ないしは偏っていないだろうか、といういわば誰でも出来る形式上の批判を許す事柄ではある。
-
その点について、上野氏は「フェミニズムとそのインパクトのもとに成立したジェンダー概念こそが、構築主義の大きな理論的推進力となったから」(p.282)と述べて本書がそのような構成となったことを説明しているのだが、それはそれとして、むしろジェンダー論ないしフェミニズムという領域に集中して議論がなされていることが本書が持つ最大の利点でさえあるのではないか、とも思う。それは、<現実のほぼ全てが構築されたもの>であることを前提とする以上、恐らく何でも扱えることになるのであろう「構築主義」だからこそ、散漫化を避け、充実したアンソロジーにするためには特定の事柄にこだわった方が良いと考えるが故である。実際問題、一応フェミニズムやジェンダー論に常々関心を持ってきた私にとって本書は、誠に充実した読書経験を与えてくれるものなのであった。
-
ただし、その点から言うと、どうせなら本書を、『構築主義とフェミニズム』のようなタイトルにして、議論を更に限定し、ついでに本書ではほとんど言及されていない法社会学・法哲学・生命倫理学辺りの議論を取り込むと良かったのでは、という気がするのだが、いかがなものだろう。やや蛇足めいたことを述べてしまったが、この辺で終わりにする。(2003/06/05)