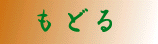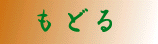Jean-Luc Godard監督作品 Eloge de l'amour
-
Histoire(s) du cinemaを撮り終えたGodardが1999年に製作した劇場用長編。相も変わらず何とも晦渋なこの作品だけれど、大体のところを要約すると本作品は、主人公であるEdgardという「大人になろうとしている」青年が、Godardの分身であるかのごとく何らかの作品を作製しようとし、そのための女優選びを行ないつつ結局は破綻を迎える、というモノクローム35mmフィルムによる第1部と、その2年前、第2次世界大戦においてレジスタンス活動をしていた夫婦に関する調査を行なっていた同じくEdgardが、そこで見た同夫婦とその回想録の映画化権を巡るハリウッド映画界のエージェントとの結局は決裂する交渉が、ディジタル・ヴィデオによるカラー映像によって描かれる第2部からなる。
-
原題を意訳した邦題である『愛の世紀』という言葉とは裏腹に(直訳なら、『愛の称賛』とでもなろう。)、「戦争の世紀」であった20世紀を回顧しつつ、歴史を持たぬ北アメリカ大陸の連邦=アメリカ合州国やハリウッド映画が持ついわば「文化帝国主義」に対する呪詛とも言うべき言説をぶちまけたこの作品、何やらこの監督にしてはこのところとみに保守化し右傾化するフランス共和国に迎合しているような気がしたのだが、多分そう解釈してはいけないのだろう。
-
さよう、この作品からはむしろ、グローバリゼーションというよりもそれが持つ帝国主義性の蔓延を回避しつつ、アンチ・グローバリゼーションというよりもそれが持つ拝外主義=民族浄化主義の危険性をも回避するという極めて困難な道を、模索すべし、とでもいうような、極めて政治的メッセージを読み取るのが恐らくは正しいのだろうけれど、それは実のところ、極めて大変なことである。大変なことなのだけれど、とっくの昔に超右傾化しそれがこのところ更に強まっているこの日本という国の行く末を憂いつつ、上記のようなことは最終的に人類が達成せねばならないそれこそ「未完のプロジェクト」なのである、という自己主張を述べて、極めて政治的な短評を終えたいと思う。以上。(2002/05/07。ちなみに、原題のelogeにある頭のeは右上がりアクサン付きです。)