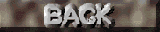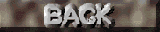高橋源一郎著『ゴースト・バスターズ-冒険小説』講談社、1997
- 著者久々の長編である。といっても、もちろんこの人の作品を「小説」という範疇でくくるのは不可能である。366ページにもおよぶ「作品」としかいいようがない。
- この作品は今や市民権を得た言葉を用いればいわゆる「饒舌体」とでもいうべき文体で書かれており(太宰治の「駆け込み訴え」のパロディが面白かった。そもそも太宰こそが饒舌体の発明者だったりする。)、あっという間に読了出来た。但し、その解釈を巡っては、大いに悩まねばならないことになった。これについては後で述べたい。
- 冒頭から、映画『明日に向かって撃て(すごい邦題である。)』の二人組ギャングであるブッチ・キャシディとサンダンス・キッドが登場し、以後「旅する二人組」が作品世界を徘徊し、その正体が最後まではっきりとは明かされない「ゴースト」と「対決」していくことになる。順に挙げると、松尾芭蕉と河合曾良、『イージー・ライダー』の二人組、ドン・キホーテとサンチョ・パンサ、パンサとアントニア、さりげなく喚起されるJ.L.ゴダールの『勝手にしやがれ』のJ.P.ベルモント・G..セバーグの二人組や『ピエロ・ル・フ』のベルモント・A.カリーナ二人組、宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』のジョバンニとカムパネルラ、そして松本零士の『銀河鉄道999』の星野テツロウとメーテル…。旅はしないが他にも重要な二人組として、則巻千兵衛博士とニコチャン大王、パーザンとはるばあさん、タカハシさん(要するに作者自身)とナカガワマユ(誰なんだ?)などが登場する。作品の冒頭でブッチとサンダンスの銃によって死んでいく(?)少年と、中盤で彼ら二人と共に「ゴースト」退治に出かける少年が同一人物であるか、はたまた作品の最後の部分においてブッチとサンダンスの銃によって死んだかに見えたが命拾いをする少年が彼らとどう関係するのかが問題なのだが、これらの少年が相方を伴わずに登場することなどからみて、この作品の中で特権的な位置を占めることだけは間違いない。なお、他にも単独で登場する重要な人物として砂漠を旅するJ.A.ランボーがいるのだが、師匠のP.M.ヴェルレーヌと放浪していたことからして、これもまた旅する二人組の一事例として用いられていると解釈したい。
- 以下、本書に関する、私的な分析に入ることにする。私個人としては、p.208で述べられていることが大変面白かったし、実はこここそが本書理解の要ではないかとも思う。この部分で述べられているのは、かつて富岡多恵子が高橋の作品を「内輪受けねらいだ。」、と批判したのに応えたものであるが、高橋が書いている通り、内輪受けねらいでない作品などあり得ないと私自身も考えていて、逆にそのことを肝に銘じつつテクスト生成を行うことこそが重要なのであると思う。それはあらゆる作品が、基本的には作品作成者とは異なる人間がそれを読んで(あるいは聞いて、見て、触って)理解できることを前提として作られているものだからである。さらに言うなら、独り言ですら自分という他人に向けられた言葉と見なすことも可能である。ただ、J.ジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』に関しては何とも言えない。あの作品は必ずしも独り言ではなく、何かに向かって開かれたテクストを模索したもの、ともとれるからである。このことは本書の理解にも役に立つのではないかと思う。先に進もう。
- さて、先ほど大いに悩まされる、と書いたが、それはこの作品が一般的な小説に見られるような起承転結その他の物語的構造を持っていないからである。この辺りについては、要約することなどとても出来ないので、実際に手にとって読んで頂くしかない。では、私は本書をどう解釈したか。本書読了後に感じた印象として、この作品は「プログラム」に似ているな、と思った。そう、今あなたが見ているその画面を表示させているようなコンピュータ内を走る「プログラム」である。読解上の最大のヒントはおそらく「Ⅶ ペンギン村に陽は落ちて」にある。これも「ゴースト」の一つの現れとして読むことが可能なわけであるが、ここで行われることは、永劫回帰=「世界」からの脱出である。永劫回帰とは、強引に解釈すれば、プログラム上では無限ループのことである。例えばBasicで
- 10 GOTO 10
- と書いてこれを走らせれば、第10行を永遠に繰り返すことになる。もちろん、繰り返しの内容をもっと複雑にすることもできる。さて、そこから抜け出すにはどうすればよいか?コンピュータ上ではハードウェア割り込みを行えばいい。PC/AT互換機ならばCtrl+Shift+Deleteのように。Ⅶではそれは少年の「ペンギン村」という永劫回帰する世界への介入により果たされる。しかしそれは逆に言えば「ペンギン村」を消滅させることにもなる。これは、大きな哀しみを伴うこととして語られることになる。
- 実はこの作品自体が、そういう無限ループ的な繰り返し、すなわちⅦにおける「ペンギン村」のような「世界」取り込まれており、それは実は本書が大量に印刷され続けることによって繰り返されることにもなるのであるが、本書の最後の部分で冒頭部が繰り返されしかもわずかな差異をもって終わるという文章技巧によって表されていると考えて良いと思うが、そうした繰り返しには終止符を打ちうることが暗に示される。
- では、果たして「ゴースト」とは何なのか?私見では、それは「世界」のことである。但し、その場合の「世界」とは、我々が言語その他を用いて認識している「世界」のことである。ここではそうした「世界」から我々は自由になれるのかが問われているのではないかと思う。ゴースト退治(笙野頼子『レストレス・ドリーム』で描かれた「言語国家」との死闘が喚起される。)とは、いってみれば「認識論的超越」のことであろう。それはジョイスによる、ジョイス独自の文体の発明によって成し遂げられた文学技法・表現の拡張、あるいは本書にある「内輪を破るのは内輪の内輪からではないか」という高橋の宣言からも分かるような「文学による文学の超越可能性の提示」なのではないだろうか。そう考えれば、本書は、作者である高橋源一郎を含む世界における、その世界=ゴーストと高橋の戦いを通じて産み出されたものであり、そのことによって、読者である我々自体も、その戦いに巻き込まれることになるのである。果たして、本書がこの頑強な「世界」を少しでも揺るがしたか、あるいは揺るがせるかどうかについては、ひとえに読者個々人の本書、あるいは彼ら=我々の住む「世界」へのコミットメントのあり方にかかってくるのではないかと思う。(1997/7/21。7/22に若干の追加。)