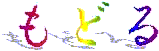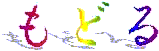蓮實重彦著『ゴダール革命』筑摩書房、2005.09
-
著者の説明によると本書は、「それがかりに錯覚であるにせよ、『アメリカ的』であることと『偉大』であることとが矛盾なく共存しえた一時期に、『ハリウッド映画』に目が眩んでしまった二つの個体が、『アメリカ的』であることと『偉大』であることをともに放棄してしまった『ハリウッド映画』の半世紀をどのように過ごしたかをめぐるいささか陰惨な『ドキュメンタリー』」[p.240]ということになるのだそうだ。二つの個体とは勿論ゴダールと本書の著者である蓮實自身ということになるのだが、いかにも蓮實重彦らしいというか、要するにこの本に実際には書かれていないことをもって、何とも見事にこの本の中身を数行で説明してしまっているところが全くもって素晴らしい。
-
さて、そういうものであるという説明を著者自身がしているこの本は、実際にはというかより客観的にはJ.L.ゴダールという名のフランス語で映画を作り続けている人物とその作品について、著者がここ40年ばかりの間に書いてきたことを一堂にまとめたもの、という形をとっている。そういうこともあり、ゴダールという映像作家に関する全体的な議論をする、というよりは、一つ一つの作品に関する記述が大半で、その辺が物足りなさでもあり、逆に言うと個々の作品について語る以外何が出来るのか、ということを考えさせるような構成でもある。
-
今回この書物を一読し、結構観ている積もりでその実かなり抜けのある私自身の映画鑑賞歴に唖然とし、あるいは一見正面から語っていないようでその実基本的なデータはきちんと文章内に収めつつ、きっちりと本質的な批評を紡ぎ出してきた蓮實重彦という映画評論家の力技に改めて感嘆した次第である。「ゴダールを見て映画を撮れなくなる」云々、という話が黒沢清との対談の中で出てくるのだけれど、例えば「蓮實を読んで映画について語れなくなる」、ということも確かにあり得ることだ。しかし、それでも私は映画について語るのをやめません。以上。(2005/11/06)