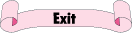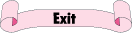摗揷彲巗挊亀峴偲偼壗偐亁怴挭慖彂丄1997
- 僼僅僩僕儍乕僫儕僗僩丒摗揷彲巗巵偺嵟怴姧偱偁傞丅埲壓丄11寧29擔偵搶梞戝妛偵偰峴傢傟偨乽嬤尰戙廆嫵尋媶斸昡偺夛丒彂昡夛乿偱偺巹偺僐儊儞僩偵丄庒姳偺壛昅丒嶍彍傪峴偄偮偮榑昡傪壛偊偨偄偲巚偆丅
- 偝偰丄杮彂偑偄偐側傞栚揑傪傕偭偰幏昅偝傟偨彂暔偱偁傞偺偐偼乽僾儘儘乕僌乿偺嵟屻偵婰偝傟偨師偺尵梩偐傜撉傒偲傞偙偲偑弌棃傞丅偡側傢偪丄乽廆嫵偲偼壗偐丅廋峴偲偼壗偐丅廆嫵偑偼傜傓亀嫸婥亁偲偼壗偐丅偩偑丄敄偭傌傜偵亀嫸婥亁側偳偲尵傢偣側偄廆嫵幰偺幚慔偲巚椂偲偼壗偐丅帺栤傪偔傝曉偟側偑傜丄廋峴偵摨敽偟丄榖傪暦偒丄傑偲傔偨偺偑杮彂偱偁傞丅乿乮p.19丅亀亁偼尨暥偱偼乽乿丅埲壓摨條丅乯
- 傕偪傠傫偙偺暥復偼摗揷巵偑庢嵽丒幏昅丒敪尵傪峴偭偰偒偨乽僆僂儉恀棟嫵乿偺堦楢偺帠審傪擮摢偵抲偄偰偄傞栿偱丄偙偙偱栤戣偲偟偰採婲偝傟偰偄傞偺偼丄乽杮暔偺廆嫵乿偲乽婾暔偺廆嫵乿偺堘偄偼壗張偵偁傞偺偐丄偦偟偰傑偨乽杮暔乿偲乽婾暔乿傪尒暘偗傞偵偼偳偆偡傟偽傛偄偺偐丄偲偄偆偙偲偵側傞偺偱偼側偄偐偲巚偆丅偦偟偰丄偦偺摎偊偼丄戝曄側帪娫偲懱椡傪旓傗偟偨偼偢偺庢嵽偲丄偦傟偵婎偯偄偰側偝傟偨揤戜廆憁椀偨偪偺壗偲傕惁傑偠偄乽峴乿偺丄拪徾壔傪壜擻側尷傝旔偗偨嬶懱揑偐偮徻嵶側婰弎偵傛偭偰丄撉幰偵偼帺偢偲尒偊偰偔傞偼偢偩丄偲偄偆慜採傪傕偭偰幏昅偑側偝傟偨偺偱偼側偄偐偲巚偆丅傕偪傠傫丄揤戜廆偵強懏偡傞堦晹偺憁椀偺峴偆乽峴乿偺傒傪庢傝忋偘傞偺偱側偟偵丄懠偵傕椺偊偽廋尡幰偨偪偺乽峴乿偱偁傞偲偐丄偁傞偄偼僆僂儉恀棟嫵偺乽峴乿側偳傪暪抲偡傞偲偄偆偙偲偵傛偭偰愢摼椡偲懨摉惈偼傛傝憹偟偨偺偱偼側偄偐丄偲偄偆斸敾傕摉慠婲偒偰偔傞偲巚傢傟傞偺偩偑丄杮彂偼偲偵偐偔乽敄偭傌傜偵亀嫸婥亁側偳偲尵傢偣側偄廆嫵幰偺幚慔偲巚椂乿偺嬶懱椺傪帵偡偙偲偵庡娽偑偁傞偺偱偁偭偰丄偦傟偼妋偐偵堦椺傪嫇偘傟偽偡傓偙偲側偺偩偐傜丄偙傟偼偙傟偱丄惓摉側偺偱偼側偄偐偲巚偆丅撉幰偲偟偰偼丄摗揷巵偺彮偟慜偺巇帠偱偁傞亀堎奅傪嬳偗傞亁乮妛尋丄1995乯傗亀僆僂儉恀棟嫵帠審亁乮挬擔怴暦幮丄1995乯摍傪嶲徠偡傞偙偲偵傛偭偰丄杮彂偺尵傢傫偲偡傞偲偙傠傪偝傜偵怺偔擣幆偱偒傞偺偱偼側偄偐偲巚偆丅
- 巹尒偱偼丄杮彂偺拞怱傪側偡偺偼戞嘪復媦傃戞嘫復偵偍偗傞丄揤戜廆憁椀丒摏堜塨娤巵偑暉搰導戝徖孲夛捗崅揷挰偺夛捗栻巘帥偵偍偄偰峴偭偨乽廫枩枃戝岇杸嫙乿偺摗揷巵偵傛傞嶲梌娤嶡偺婰弎媦傃偦偺堛妛揑怱棟妛揑暘愅偱偁傞丅偙偙偱偼丄摨戝岇杸嫙偵娭偟偰偺廆嫵妛揑暘愅偼嵟彫尷偺傕偺偵偲偳傑偭偰偍傝丄摿偵偦偺幮夛揑懁柺偵娭偡傞暘愅偼傎偲傫偳奆柍偱偁傞偙偲偵拲堄傪姭婲偟偨偄丅幮夛揑懁柺偵娭偟偰杮彂偑弎傋傞傋偒偙偲偼丄戞嘪復偱偺摏堜巵偲夛捗崅揷挰偺恖乆偲偺岎棳偺婰弎偱偮偒偰偄傞丄偲偄偆柺傕斲傔側偄偺偱偁傞偑丄椺偊偽屻偵弎傋傞傛偆側乽壗屘庴偗擖傟傜傟偨偺偐丠乿偲偄偆揰傪柧傜偐偵偡傞偵偼丄幮夛妛揑側暘愅傕昁梫側偺偱偼側偄偐偲峫偊偰偟傑偆偺偱偁傞丅彮側偔偲傕丄堛妛揑怱棟妛揑暘愅偵娭偡傞婰弎偑側偝傟偨偺偩偐傜丄幮夛妛揑暘愅傪庢傝崬傓偙偲偵傛偭偰乽暘愅乿偺偨傔偵偍偐傟偨偲尒偰椙偄偩傠偆戞嘫復偺撪梕偵傛傝僶儔儞僗姶偑弌偨偺偱偼側偄偐偲巚偆丅
- 偝傜偵偙偺揰偵偮偄偰尵偆偲丄巹偲偟偰偼丄乽偁偲偑偒乿偵偍偗傞乽杮彂偺撪梕偲娭學偺側偄乿偲柧婰偝傟偨巐偮偺栤戣丄偡側傢偪乽惛恄揑丄擏懱揑丄嵿嶻揑偵恖傪彎偮偗傞慻怐揑廆嫵偺弌尰乿乽慖嫇偲廆嫵抍懱偺堦懱傇傝乿乽廆嫵偲崙壠丒峴惌偲偺偐偐傢傝丄偲傝傢偗愴杤幰偺堅楈丒捛搲偺偙偲乿乽帺傜傪廆嫵偱側偄偲婯掕偡傞亀廆嫵亁偺搊応乿偺採帵傪偟偰偟傑偭偨埲忋偼丄偙傟傜偺乽彅栤戣傪峫偊傞僸儞僩偑丄偠偮偼杮彂偑昤偄偨揱摑暓嫵偺悽奅偵偁傞偲巚偭偨乿偵傕偐偐傢傜偢丄乽偙偙偱偦偺榑傪揥奐偡傞偮傕傝傕側偄偟丄偦偆偟偨応偱傕側偄丅乿偱偁傞偲偐丄乽幮夛偺側偐偱廆嫵偑婋尟帇偝傟偨傝丄寉曁偝傟傞孹岦偑嫮傑偭偰偄傞崱丄偦偺崕暈偺偨傔偵傕杮彂偑偄偝偝偐偱傕栶偵棫偮偙偲偑偁傟偽偆傟偟偔巚偆丅乿乮埲忋丄乽偁偲偑偒乿pp.311-3傛傝丅乯側偳偲傗傗摝偘崢乮偲偄偆偺偼懠彂偲偺斾妑偐傜巹偑偦偆姶偠偨偲偄偆偙偲偱偁傞丅摉擔偺摗揷巵偺僐儊儞僩偱偼丄偁偲偑偒偵偙偺傛偆側偙偲傪嵹偣偨偺偼傓偟傠挧敪揑側堄枴崌偄偑偁傞丄偲偺偙偲偱偁偭偨丅乯偵弎傋傞偺傒偱偼側偔丄偦傟傜偺栤戣傪棫偪忋偘偨埲忋偼丄偁偔傑偱傕杮彂偺撪梕乮偮傑傝偼揤戜暓嫵偵偍偗傞乽峴乿偺惉棫偵娭偡傞楌巎揑攚宨媦傃尰忬偺徻嵶側婰弎乯偵懄偟側偑傜丄壗傜偐偺夝摎丒巜恓丒寢榑偺採帵傪栚巜偟偰丄廆嫵幰偲幮夛偲偺娭學傗丄乽峴乿偲偄偆傕偺偺帩偮幮夛揑側堄枴偵娭偡傞暘愅偑偝傜偵怺傔傜傟側偗傟偽側偐偭偨偺偱偼側偄偐丄偲峫偊傞偺偱偁傞丅
- 偦偺揰偵偮偄偰丄巹屄恖偺尒夝傪弎傋偝偣偰傕傜偆偲丄偦傟偼椺偊偽丄乽偙偺巇帠偺娫丄偦偟偰崱傕丄斵傜偺偙偲偑擼棤偐傜偼側傟偨偙偲偼側偐偭偨丅乿乮p.19乯偲偄偆僆僂儉恀棟嫵偲偄偆嫵抍偑壗屘忋嬨堦怓懞偺恖乆偁傞偄偼擔杮幮夛偵庴偗擖傟傜傟偢丄斀懳偵揤戜憁椀丒摏堜塨娤巵偑夛捗崅揷挰偺恖乆偵庴偗擖傟傜傟偨偺偐丄偲偄偆栤戣偵婣拝偝偣傞偙偲傕壜擻偱偁傞丅偦傟偼偁傞摿掕廆嫵偁傞偄偼廆嫵幰偺乽惓摑惈乿偺崻嫆晅偗傪弰偭偰偺媍榑偵娨尦弌棃傞傕偺偲峫偊偰傒傞丅偦傟偼摗揷巵偑偦傟偲側偔樅傔偐偟偰偄傞乽揱摑乿偺椡側偺偱偁傠偆偐丅偁傞偄偼嵟嬤偺僔儍乕儅僯僘儉榑偑巜揈偟偰偄傞傛偆側廆嫵幰偺峴偆乽僷僼僅乕儅儞僗乿偺帩偮椡側偺偱偁傠偆偐丅乽揱摑乿偲偄偆傕偺偡傜傕乽嬤戙乿偺乽敪柧乿偱偁傞丄偲偄偆傛偆側媍榑偑側偝傟偰偒偨偑丄偦傟偼慬偔偲偟偰傕丄巹屄恖偑廋尡摴傗柉娫涋幰偺尋媶丄偁傞偄偼奺庬乽峴乿傊偺嶲擖傪捠偠偰姶偠庢偭偰偒偨乽揱摑乿惈偺婬敄偝偐傜偟偰丄偳偆傕屻幰偺斾廳偑戝偒偔丄媡偵尵偊偽乽揱摑乿側傞傕偺傕幚偺偲偙傠廆嫵幰傗廆嫵廤抍偺乽僷僼僅乕儅儞僗乿偵傛偭偰乽惓摑乿壔偝傟摼傞傕偺側偺偱偼側偄偐偲峫偊偰偄傞偺偱偁傞偑丄偄偐偑偱偁傠偆偐丅乮1997/12/02乯