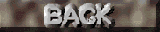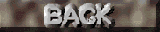京極夏彦著『嗤う伊右衛門』中央公論社、1997
- これは怪談でも推理小説でもない。強いて言うならば恋愛小説である。
- さて、本書はいわゆる「四谷怪談」をベースにし、これを京極夏彦流の同作品への解釈、及び京極夏彦流の文章技法(泉鏡花や永井荷風あるいは石川淳を彷彿とさせる。)をもって構成・構築し直したものである。
- 京極は、このあまりにも有名な怪談に、これまでに刊行された5冊の推理小説と基本的には同様のスタンスをもって臨んでいる。すなわち、まず第1に、妖怪や幽霊の出現といった怪異現象は人の心の産み出す心理的な現象として一応解釈できる、というスタンスである。本書でもお岩は化けて出たりするようなことはない。
- そしてまた第2に、ここで用いられている現実というものがいかにして形成されていくか、あるいは何らかの事件というものがいかにして成立するのかということに対する京極の解釈もまた、5つの推理小説に通底するものである。つまり、本書ではお岩を含むいく人かが、あることを発端にして始まる一連の事件に巻き込まれて死んでいくプロセスが描かれるのであるが、結局のところそれは、始まりはほんの些細なことであっても(ちなみにこの物語ではその発端はそれほど些細なことではない。)、いったん歯車が回り出すと、事態は当事者それぞれの抱く思惑や意図を越えて混乱・混迷し、最終的には誰もが当初は予想し得なかった破局を迎える、ということである。簡単に言うなら、例えばある種の犯罪では、それが誰の責任によるものかを問うことは、因果関係が複雑に絡み合った人間社会においては実際のところ極めて困難な場合があるということである。本書においては狂言回し的人物である「御行の又市」が一応事件全体を見渡す視点に立っているのだが、事態は彼の思惑を遙かに逸脱してしまうことになる。これは『姑獲鳥の夏』において同書の語り手である関口巽がある犯罪に全く無自覚に荷担してしまうことや、『絡新婦の理』において謎解き役の「京極堂」が下手をすれば事件に自ら関与してしまいかねないことを自覚しつつ、結局関与してしまうこととも一脈通じるところがある。
- 本書のラストは『嵐が丘』を思い起こさせるものである。しかもそれは、E.ブロンテの原作よりもむしろ吉田喜重監督、松田優作主演の同小説の翻案による映画を、である。悲しい結末ではあるが、美醜という認識論上のカテゴリーを超越してしまった伊右衛門が、家格や身分の上下や男/女という差異を徹底的に強調する封建社会に抵抗し死んでいったお岩の遺骸を抱きつつ、桐箱の中で嗤いながら死んでいるという最後の場面は、全ての邪悪なものが放出された後に唯一希望だけが残されたというパンドラの箱のイメージとも重なる。伊右衛門とお岩は、あまりに深い互いの愛故に、ついには死を持ってしか結ばれることはないのであるが、そこでは徹底的に絶望的かつ暗澹としたヴィジョンの中に、わずかながらも希望が顔をのぞかせているのである。(1997/7/21)