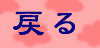さて、21世紀の初頭に刊行され、今後長らく語り草になるだろうこの「歴史」的作品は、それ自体が「歴史」についての問いかけをメイン・モティーフとしているという点を強調せねばならない。何度も繰り返し引用される小説内小説『赤死病館殺人事件』の、「世の中には異常(ルビ:アブノーマル)なもの、奇形的(ルビ:グロテスク)なものに仮託することでしか、その真実を語ることができない、そんなものがあるのではないか。……この世には探偵小説でしか語れない真実というものがあるのも、また事実であるんだぜ」という一節こそが、それを端的に示す。
即ち、「歴史」とは単なる事実の集積に他ならないのだが、その「事実」を完膚無きまでに集積することが不可能なのも確かなのであり、そうであるが故に「歴史」の語り方については、1.それを恣意的かつ意図的に構築し得るもの、ないしは構築すべきもの、という立場と(いわゆる「自由主義史観」の立場がこれに当たるだろう。)、2.可能な限り客観的に捉え得る事実のみを提示することしか出来ないという諦念に基づきつつ、前者の立場から発する言説を解体・脱構築しようとする立場という大まかに分けて二つの立脚点が存在するのだと思う。本書では両者の立場の対立が「陰陽師」・占部影道(うらべえいどう)と「検閲図書館」(説明省略)・黙忌一郎(もだしきいちろう)の対決という形で描かれていくのだが、先に引用した「探偵小説でしか語れない真実というものがあるのも、また事実である」という言説に基本的に則ってミステリ=探偵小説を紡ぎ出した山田氏は、当然のごとく後者の立場を取っているのであり、私もまた、それを全く妥当なものであると考えるのである。
ところで、基本的にメタ・ミステリの体裁を持つ本書には、作為的なもの、という可能性もなくはないとは言え、だからといって許されるものでもない記述上のミスが結構目立つことも一応指摘しておきたい。以下私が気付いた範囲で列挙すると、19頁下段「一節には」は「一説には」の誤記。157頁上段「ダイヤのクイーン」は「ハートのクイーン」が正しいはず。378頁下段「ミノリという日本名」は「ミノル」だったはず。460頁下段の記述は366頁の記述と重複しており不自然。572頁から573頁にかけて三楽堂の主人が「平行世界」論に言及した云々、とあるけれど、そんな記述はどこにも存在しない。641頁末尾以下における記述は、この小説の中心的記述者・萩原桐子が持つある身体的特徴とは矛盾する。特に、最後に挙げた点は致命的とも言えるもので、そのような身体的特徴がありながら、何故に本書の大部分をなす手記をワード・プロセッサで作成し得たのか、という点は、全く理解不能、という他はない。以上の点に付き、本作を真に空前絶後の傑作とするべく、第二刷以後には改善されることを望む。なお、こんなことを書き連ねたのも、あながち無駄とも言えないのは、本書の末尾近くの記述(680頁)に従えば、私もまた、終わることのない『宿命城殺人事件』の作者の一人となり得るからである。(2001/4/29)