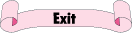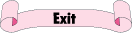中沢新一著『ポケットの中の野生』岩波書店、1997
- 宗教人類学者・中沢新一による「ポケットモンスター(以下「ポケモン」)」論である。「ポケモン」について簡単に述べると、これは任天堂の携帯型ゲーム機である「ゲームボーイ」専用のロール・プレイング・ゲーム(RPG)であって、1995年の発売以来かなり長期間にわたって爆発的なヒットを飛ばしているものである。対象年齢をかなり低く設定しているらしいことから来ると思われるのだが、RPGとしてみた場合には最近とみに複雑になりすぎたRPG群の中ではひときわ目立って易しいものになっている。ただし、このゲームの場合にはその目的が通り一遍のRPGという枠を越えた別のところにあるということがポイントで、それは主人公が捕まえ育てたポケモンを駆使して「ポケモン・リーグ・チャンピオン」を倒すことにあるのではなく、あくまでも150種類存在するポケモンを全て集め「ポケモン図鑑」を完成させることが最終目標となる。そして、これには大変な労力を要するのである。何故なら、3タイプ(赤箱・青箱・緑箱の3ヴァージョンが売り出された。ちなみに青箱は現在入手不可能のようだ。)出ている「ポケモン」のうち一つを買って来て一人でプレイしたとしても、集められるのは精々124匹位のもので、それぞれの箱には絶対に入手できないポケモンもあるのだし、さらには一回のプレイで全てを網羅できないような仕組みも施されている。すなわち最終目標を達成するには独りゲームの世界の中に閉じこもるのみではなく、現実世界の人々とポケモンを交換することが必要になってくるのである。まあ、取り立ててお金に困っていないのならゲームボーイを2台買ってきて、「ポケモン」も赤箱と緑箱を揃えてしまえば、一人で全部集めることも可能ではあるのだが、対象年齢はあくまでも小学生が中心なのだから、それは杞憂とでも言うべきものである。
- さて、中沢はこのようなゲームを精神分析学者S.フロイトの「エロス」「タナトス」及び精神分析学者J.ラカンの「対象a」、人類学者C.レヴィ=ストロースの「野生の思考」「今日のトーテミズム」「贈与交換」などといった概念を駆使して分析している。この本の対象年齢が幾つ位なのかは結局よく分からなかったのだけれど、こうした概念を理解出来るとすればやはりそれはこのゲームの主たる対象ではなく精々中学生(無理かな?)以上ということになってしまうのではないかと思う。そうするとここには例えばレヴィ=ストロースをはじめとする人類学の持っている、これまでもさんざん批判されてきた「主知主義」的な「研究者の独りよがりな概念の構築」が反復されているような気もする。つまり、例えばレヴィ=ストロースが様々な社会の民族誌のうちの親族に関する記述の中に「一般交換」だの「限定交換」だのといった形で現れてくる「構造」を見出したとしても、そんなことは現地の人々にとっては実際のところはあずかり知らぬところであって、それは実はレヴィ=ストロースの頭の中にしかないのではないか、というようなことである。まあ、構造主義の立場に立てば、そうした構造は普段意識されているものではなく、あくまでも無意識的なものであって、それを見出すのが構造主義人類学なのだ、ということになるのだろうから、それはそれでいいのだけれど、その場合、構造人類学者の分析を対象とした社会の人々に見せることによって評価して貰い、再度の分析、さらには対象社会による再度の評価を繰り返して分析をより精緻なものにする、というようなプロセスがほとんど踏まれてこなかったことはやはり問題になっていて、ここでも小学生がおそらくこの本を読むことは無い、あるいは不可能であることから来る批判不可能性という、文化的に上位(批判不可能性から来る一種の非対称性からそう見なせると思う。)に立つもののある種の特権性が出来してしまっているように感じる。
- そもそも人工的なゲームである「ポケモン」を、本来は「所与の自然」と「人間=文化」の関係を分析しようとする時に用いるべきだろう「野生の思考」や「トーテミズム」などの概念で分析することが果たして有効なのかどうかが問われなければならないだろう。もちろんゲーム制作者が「野生の思考」を無意識のうちに持っていて、それが「ポケモン」に反映し、子供たちが持つ「野生の思考」と相互作用した、ということなのだろうけれど、「ポケモン」はあくまでも人工物なのであって、こうした議論の地に着かず浮き足立った感じは拭い得なかったし、さらに言えばそれはやはり研究者の創り出した概念の当てはめに過ぎないような気もしてくる。中沢が属していると言われていた思想潮流であるポスト構造主義と呼ばれる文脈では、そうした当てはめ主義を乗り越えることが目指されていたはずなのだが、何となく一歩後退を感じずにはいられなかった。
- さらには、子供たちが「ポケモン」を通じて「流動的な生命の流れ」あるいは「背後に連続して流れる何かの潜在的な力を直感している」(p.126)とか、ポケモンの交換とはまさしく「人類学が探求してきた」(p.148)「贈与交換」なのであって、「そのとき、ものといっしょに『人格』と呼ばれるなにか、ひょっとしたら『たましい』などと呼んでもいいかもしれないなにかが、ケーブルを通して行ったり来たりしているように、ゲームのテキストに積極的に参加している人には感じられる。」(p.145)というのはいささか買いかぶり過ぎなのではないだろうか。高々150種類程度の作者達によってアプリオリに類型化がなされたポケモンと、マップ上に散りばめられた町や草っぱら、あるいは洞窟といったこれまた極めて類型的な領域には「現実世界」や「所与の自然」に対して私が感じる途方もない複雑さは全く感じられないし、逆にこんなに類型化された「自然」が、個々人は極めて個性的であるに違いない子供たちに一律に押しつけられている現状には嫌悪感すら催してしまうのだがどうだろうか。もっと端的に言えば、「ポケモン」を持っていない、持てない(ゲームボーイにしろ「ポケモン」にしろそれなりに値のはるものである。)、あるいは持つ気のない子供たちは「いじめ」られてしまうことになるのは明らかなことなのである(まあ、製作者の意図に反して売れ過ぎた、という側面もあるにはある。)。さらには、希少価値のあるポケモンが子供たちの間で「貨幣」によって売買されているという事実を知らないわけではないだろうが、当然そこには「階級」のような関係が生じてしまう危険性が常に存在し、おそらく実際にそうなのではないかと思うのである(もっと単純に「暴力」によって「搾取」する、というようなこともありそうだ。)。
- もちろん、「生命とは何か?」という問題には明確な解答が与えられていない以上、ポケモンたちが結局はROMやRAM内に常駐し、しばしば液晶の画面に表出し、ケーブルを通して移動する電気的パターンに過ぎないとしても、そこに子供たちを含めて我々人間が「生命」を感じ取ってしまうとするならば、それは我々人間の持つ自然観の一端を表しているわけで、アリストテレス以来の自然哲学、あるいは現象学や認識論に寄与する新しい事例となっているらしいことは間違いないと思う。なお、これは当然のことながら、本年のもう一つのヒット商品「たまごっち」その他のいわゆる「育てゲー」や、さらには随分前から研究されているがさっぱり成果の上がっていない「人工知能」みたいなものにも共通して言えることである。
実はG.スピヴァックのような人はレヴィ=ストロースを「現象学者」であるとすら言っているのだが、それは例えば、「自然」なるものは所詮人間が言語その他の記号を用いて構築した文化体系の中で恣意的な形で捉えられるものに過ぎず、結局のところそこにあるのは我々人間の認識体系だけなのだ、といっているとも見なせるからである。そう考えると、本書は実は「生命」や「自然」なるものに関する現象学的認識論なのだな、などと考えてしまった。
- ただ、それでもなお最後に一ついっておかねばならないことがある。本書はある意味で「ポケモン」の全面的肯定なのだが、ほとんど全てのRPGで主人公たちが「死んで」しまっても簡単に生き返るという設定になっていることの影響があるという指摘もあるような(ちょっと疑わしいのだけれど。)、子供たちが人生をリセットするためにあっさりと自殺してしまったり、反対に他人の人生をリセットするためにあっさりと殺してしまったりというようなことが現実に起きている以上は、「生命」なんて高々電子的な記号と変わらない、というように読み替えられかねないような、電子ゲームにも「生命」が宿り、それを子供たちは敏感に感じ取っている、などといった主張が孕む危険についても言及すべきではなかったかと思う。それはもちろん子供だけの問題ではなくて人類全体が特に今世紀において幾度となく経験してきたことにもつながってくるのである。中沢は自身のタナトスに忠実に従って本書を執筆してしまったのかも知れないけれど、それが拡大解釈されたときに持ち得る危険性は十分に分かっていらっしゃるはずなのだから。(1997/12/09)