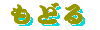さて、物語の舞台はネパールの小国。日本の大手電機メーカーに勤務する男性エンジニアが、基本的にはビジネスのために、半ばヴォランティア精神で、灌漑用の小型風力発電機を現地視察後に開発、再び現地に赴いてこれを設置し、かつまたそのメンテナンスが自力で出来る程度にまで現地の人々を教育するシステムを何とか立ち上げるまでを描く。
他にもいくつか楽しいエピソードがあるのだがそれは省くとして、ここではいわゆる先進国が開発途上国に対して行なう開発援助の在り方そのものが問われており、それは「開発人類学」などでも提唱されているような、先進国側からの一方的な押しつけではなく、あくまでも途上国側の人々の利益や関心を尊重しつつ、更には彼らの識字能力やテクノロジー利用能力をも勘案しつつ、もう一つ加えるとその土地の環境にも配慮しつつなされるべきもの、という視点が貫かれている。
これはこれで納得できるものであるし、その通りだと思うのだが、この小説では、そういう持続可能な、かつまた現地の人々や環境を考慮した開発援助がつつがなく成功するプロセスが描かれているだけで、それを権力闘争に使おうとする勢力だの(要するに「利権がらみ」というやつですな。)、よりディープなエコロジー思想の立場から発電器の破壊を試みる勢力だのが登場して、主人公が右往左往するような血沸き肉踊る展開を期待した私としては物足りなさも残った次第である。
ついでに言うと、ティベットと中華人民共和国の間にある政治的・宗教的対立軸を含め、第14世ダライ・ラマまで登場させたのにも関わらず、そのことが風力発電機設置の話とはあたかも別のプロットであるかのように物語が展開されており、この点についても不満を禁じ得なかった。開発ないし近代化と政治の絡み合いこそ、池澤が『マシアス・ギリの失脚』(新潮社、1993)以来追求してきたはずのテーマであると考えるからである。以上。(2001/06/12)