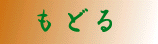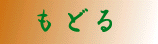Jean-Luc Godard監督作品 Notre Musique
-
本作は英語圏では Our Music 、日本では『アワー・ミュージック』というタイトルで上映された、フランス語を母語とする映像作家Jean-Luc ゴダールによる劇場版長編映画である。Forever Mozart (1996)辺りから始まる旧ユーゴスラヴィアでの民族紛争への言及を継続しつつ、未完であるためその作品リストにも載らない『勝利まで』という1970年頃PLO(パレスティナ解放戦線)からの依頼で製作し始めたという、そういうことからしてパレスティナ問題を扱ったに違いない殆ど観た人はいないだろう映画との連続性も感じさせるような、一見するところでは政治的メッセージが色濃く出ているかのように見える作品となっている。
-
さて、本作はダンテの『神曲』に倣って、「地獄篇」・「煉獄篇」・「天国篇」の3章構成をとる。地獄篇ではどうやら後半に登場するロシア生まれのユダヤ系フランス人女性オルガが作った、後に本人として登場するJ.L.ゴダールに渡されることになるDVDに収録されているのであろう過去に起こった戦争についての、ドキュメンタリとフィクショナルな映像がごた混ぜの作品らしきものが流され、煉獄篇では映像とテクストの関係について講演するためにサライェヴォを訪れたゴダールによるレクチャー風景を中心としてスペインの作家、パレスティナの詩人、ユダヤ系ジャーナリスト、破壊されたあの橋の修復者等々の諸活動が描かれ、天国篇ではエルサレムで亡き人となるオルガが赴く「米兵にガードされる湖畔」という意匠を持つ「天国」が描かれる。
-
地獄篇における誠におびただしい数の映像提示に始まるこの作品、レヴィナス、J.グリーンといった著述家によるテクストの、あるいはロマン派(例えばシベリウス)からコンテンポラリー(例えばA.ペルト)に至る雑多とも言える音源の相変わらずぶつ切りの引用を通じてゴダールが示そうとしたものは何であるのか。全体を通じ、あるいは天国篇などを見れば明らかなように、確かに「反米」・「反暴力」という政治姿勢の表明もなされてはいるのだが、事の本質はその辺にあるのではないだろう。私が最も重要だと考えたのは何と言ってもゴダール自身がそのレクチャーの中で示す映画における「ショットの切り返し」がもたらす効果についての説明なのである。
-
それを私になりに解釈すれば、例えば本作品でも言及される、溺れることなくエルサレムに辿り着くユダヤ人という虚構の映像と(史実、という人もいるのだろうけれど)、エルサレムに帰ろうとして溺れ死んだパレスティナ人という現実の映像の、あるいはまた地獄篇で交互に現われる虚構の戦争映像と現実の死が映された戦争映像の、もっと言えば前作 Eloge de l'amour であからさまに揶揄されたハリウッド映画が描く戦争と現実の戦争そのもののいわば「切り返し」が、虚構と現実の間にある差異を隠蔽する効果をもたらす、ということになるだろうか。
-
そう解釈すると、ゴダールは自分が自作の中で使っている「切り返し」をふんだんな形で含む映像について、それ自体を自ら否定するようなスタンスに立っていることをその作中で語っている、ということになるのだが、事はそれほど単純ではあるまい。「ショットの切り返し」というのは、そこに潜む隠蔽作用を自覚的に回避しながら用いること、あるいはそれを自覚的に回避しながら観ることで、むしろ映像間相互の関係性を明確なものにしその差異性を強調していくものでもあるだろう。そもそも映画という大部分が虚構の映像で作られたものは、結局のところそれ自体が「切り返し」でしかあり得ないわけで、それが何かの意味作用を発揮するには現実との差異を隠蔽することなくむしろさらけ出しつつ、更にはまた現実との関係性を明示するという意味で現実に対して開かれたもの、という形をとるべきなのだろうと思うのだ。要するに私個人としてはこの映画を、それ自体が現実の政治に関わるもの、というよりはより広く「映画」というものが、現実の政治にどのような形で関わり得るのか、ということを鑑賞者に考えさせるもの、として観た次第である。以上。(2005/11/02。なお、蓮實重彦著『ゴダール革命』筑摩書房、2005.09を大いに参考にしています。)