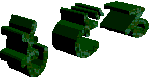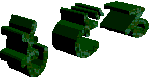笠井潔著『オイディプス症候群』光文社、2002.03
-
笠井潔による大長編本格ミステリ連作である「矢吹駆」シリーズの約10年振り第5弾である。これまでの4作は基本的に密室殺人事件を中心に物語が構成されていたのだが、今回はミステリのこれまた王道である「嵐の孤島」ものという趣向になっている。そうそう、巻末の文献リストにある通り、あたかもAgatha Christieのあの有名な作品をなぞるがごとく、ギリシャはクレタ島に近い本当にあるのかどうか良く分からない「ミノタウロス島」に、様々な理由で集まった矢吹駆とこのシリーズの語り手「ナディア・モガール」を含む10数人からなる滞在者達が、次々と死んでいき、というお話である。
-
このシリーズの時代設定が1980年頃ということもあって、ちょうどその頃主としてホモ・セクシャルないしゲイの男性が罹患するという「噂」のある伝染性疾患として注目されつつあった、今日ではAIDSないしHIV感染症と呼ばれている疾病が本作品のメイン・モティーフとして物語の基調をなす。すなわちこれが、タイトルともなっている「オイディプス症候群」である。勿論、その後異性間の性交渉その他でも感染することが分かったこのレトロ・ウィルス性疾患だけれど、奇しくもこの病で数年後死亡することになるフランスの思想家Michel Foucaultが、「ミシェル・ダジール」という名前で本作品には登場し、現象学派である矢吹駆等と、主として視線の政治学および現象学、死の権力論および生の権力論等々にまたがる侃々諤々の議論を繰り広げるのだが、これこそが本作品の要となっている。そう、Foucaultの提示した、Jeremy Bentham発案による一望監視方式=パノプティコンによって19世紀のヨーロッパで完成をみる「監視と処罰」形態が、近代的自我だの近代的相互監視社会を生み出す元となった、という例の議論が、絶海の孤島に閉じこめられ、不可視の殺人者による権力の行使=殺人行為に脅えることを余儀なくされる本作品の主要登場人物群、という舞台設定に、見事な形で結実しているのである。誠に素晴らしい。
-
こんなことを述べると、「Foucaultって誰?」なんていうことを言い出しかねない「一般読者」の皆様は買う気も読む気も喪失してしまうかも知れないのだが、本書でなされる議論はMartin HeideggerとEmmannuel Levinas(後ろのeにはアクサンあり。)を登場させ、〈存在〉ないし〈実存〉の現象学を徹頭徹尾論じ尽くした前著『哲学者の密室』(光文社、1992。現在は創元推理文庫で読めます。これは必読書。)ほど難解ではないし、後半はジェット・コースター的エンターテインメント作品と化すので、3,200円という値段や約860頁というヴォリューム、あるいはまた上記のようなやや晦渋気味の議論に尻込みする必要は、さほどないように思う。本当に、純然たる本格ミステリとして大変面白く、優れた作品であることは保証する。
-
とは言え、そこに本書の問題点もあるのであって、全体として個々の議論は多岐に渡りすぎており(権力論から暴力論、果ては同性愛を含む恋愛論まで、という具合。)、かつまたそのせいもあって全てが中途で投げ出されているように思えたし、古代ギリシャおよびクレタ島の神話や伝承に関する記述もやや衒学的にすぎ、端的に言えば冗長である。それとは別に、最後の方で明らかになる「真犯人」の犯罪動機もこのシリーズ中最も凡庸な気がするし、そもそもこの「真犯人」像は「掟破り」に近い。特にこの最後の点は方々で批判の対象となるはずなので、私がここでわざわざ言わなくても良いことなのかも知れないけれど、一応述べておく。ついでに言うと、手持ちの初版本、誤字脱字が大変多いのも気になった次第である。以上。(2002/05/19)
追記:ちなみに、本書巻頭にはあの「十二国記」が映像化されTVで放映されてしまうという物凄いことになっている小野不由美作図による、この物語の舞台である「ダイダロス館」見取り図が付されている。無茶苦茶手間のかかる作業だったろうけれど、私はこれを一度も見ないで読了した。実のところ、あってもなくても同じように思うこれがなければ、本体を3,000円以下にできたのではないか、などと詰まらぬことを考えたのであった。ということで。(2002/05/21)
-