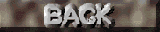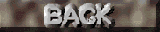奥泉光著『プラトン学園』講談社、1997
- 本書の主人公は木苺惇一という名前を持っており、これは同じ作者による作品『バナールな現象』(集英社、1994)の主人公木苺勇一と極めて似ているし、さらには第17章の章題が同書タイトルからそのまま取られていることなどから、両書は姉妹関係にあると見て良さそうである。実際には、同じ作者によるその他の作品からもいろいろと引っ張ってきているようなのでのであるが、そうしたことは細かいことなので、いちいち示さないことにしたい。いずれにせよ、本書は一連の著作から読みとれる「奥泉ワールド」の一つの現れと見なして良いと思うし、その中でも特に『バナールな現象』との対応関係を示すことは、なかなかに厄介な両書の解釈のために極めて有効なものであるからである。
- 余りネタばらしをするのは作者に申し訳ないので、最小限の記述にとどめることにしたいのだが、それではこの文章が意味不明になりそうなので、これをお読みの篤志はまずは本書をご一読下さった方が良いかも知れない。以下、最小限とは決して言い得ないかなりのネタばらしを行うことにする(ごめんなさい。)。
- 本書では『バナールな現象』において主人公とその分身がOASYSという商標名のワープロを用いて書いていた日記が、主人公と「プラトン学園」のマドンナ(ちなみに本書は同著者による『吾輩は猫である殺人事件』に続く漱石作品のパロディである。)その他の共同執筆による日記に拡張され、さらにそれは学内(さらにはプラトン学園がある象島島内)LANを構成しているマッキントッシュという商標名のパソコンを用いて記述、改編がなされていくという基本的な設定がある。ワープロからパソコンへ、さらにそれがネットワークで結びつけられており、そしてまたプラトン学園の地下には「次世代型」のスーパーコンピュータもあるようで、こうしたテクノロジー=メディアの拡張が、作品自体も拡張している。ここではマクルーハンのいう「メディアはメッセージである。」という格言を思い起こそう。
- さて、本書から私が読みとった最大のテーマは「ヴァーチュアル・リアリティ(VR)時代の死」とでもいうべきものである。タイトルの「プラトン」から想起される通り、ここでもまた、形而上学的な精神の進化というヴィジョンが提示される。それは例えば「PLP−プラトン・ライフ・プロジェクト」のような名前で呼ばれるような、肉体を失った精神がおそらく電脳空間(VR)の中で得る永遠の生命の実現のようなものが想定されていることに現れている。これは昨年来爆発的なヒットとなったアニメーション作品である『新世紀エヴァンゲリオン』でも扱われたテーマであり、実は両作品には「人間の持つ根源的暴力性」や、「自己とは他者との関係によって成立する」とか「自己あるいは現実とは他者が作り出すものである」というようなテーマ群が随所に見出せる。同じ時期に制作され、書かれたものがこうした類似性を持ってしまうのは致し方ないのであろうが、VR的なTVゲーム(VRは今のところ完成にはほど遠いのだけれど。今のところそれらと現実との区別は誰でも付けられると思う。)だのその一変奏としての「育成型ゲーム」が隆盛を極め、同時にまた、ゲーム的なテロや連続殺人事件が多発する90年代の時代感覚が如実に反映されていることになる。
- ここでも主人公はどうやら結果的には、プラトン学園による、意図的か無意志的かが明確に示されない洗脳(洗脳者が主体として名指されていないし、被洗脳者自身もそれに荷担している。)を受け、肉体を失って永遠の生を得るようである。さらにはこれもまた『エヴァ』の第弐拾六話で描かれたごとく、仮想的な現実は現実と化し、さらには(仮想)現実内存在となった人々はその現実を勝手に改竄することも可能になっているらしい。それは「自由」といえば言えないこともないが、私は小谷真理の著作の評論で述べたごとく、それは強制された自由なのであって、肉体という人間の根本的な条件を欠いているのだからむしろそれは恐ろしいことなのではないかと、実は良識派を装っているだけなのかも知れないことを自覚しつつ、考えてしまう。頻繁に引っ張らせて頂くが、かの詩人も「ああ、肉体は悲し。」と詠んでいる訳だが、近代において書物やテクストによって現実が構成されるようになったとしても、さらにはそれが1と0の並ぶ文字列=テクストで表されるプログラムやデータによって構成されるVRとなってしまっても、だからこそ我々は肉体というものをテクスト化出来ないものとしてもう一度見直しておく必要があると考えるのである。プラトン以来の精神や理性の肉体に対する優位性を標榜する形而上学が孕む危険とはそこにある。その極限としてのデカルト的な心身二元論と資本主義の行き着く先は臓器の切り売りである。身体は物と化し、経済システムに組み込まれる。私自身はどちらが正しいのかをここで言い切ることは出来ないのであるが、少なくともそれでよいのかどうかを現時点で問いつめておくべきではないかと考えている訳だ。奥泉もおそらくはそう考えているはずで、そのためにこそこうした「虚構」を構築し、想像力を喚起しつつ、精神の肉体に対する優位性や、テクノロジーの圧倒的な突出に対しての警戒感を持つように促しているように感じた。これは『バナールな現象』において、いわゆる「湾岸戦争」があたかもTVゲームのようであったこと、つまりはそれが「肉体なき」戦争時代(実際には肉体は存在している。)への突入を指し示すものであることに対する強烈な忌避感を表明していることなどとも通じるものである。
- VRの中では誰も死なない。さらにはVRの中のVRで自分自身を殺害したり、殺害させたりしても何らの害はない。木苺は次第にそれが快感になっていく。こうして行き着く先は「世界の終わり」である。そこでは時間も経過しないし何の事件も起きない。「ただ歳月は過ぎ」ていく。あくまでもVRの中での歳月が。つまりは何も存在していないことと等価である。この辺りは『エヴァ』第弐拾四話において渚カヲルが「生と死は等価なんだ。」と述べていることを思い出させる。『バナールな現象』の世界が「一面の砂漠」という不毛なる場所における始まりも終わりもない閉じた虚構であったとすれば、やはり「砂」によって閉じられる本書もまた、不毛なる閉じた虚構には違いない。木苺たちなど、別に始めから存在せずとも良いのである。虚構なのだから。しかし本書345頁に書かれている通り、「虚構でしか描き出せない真実」を描くことを目的にしているのだから(この章は「洞窟の比喩」と題されている。)、何が真実であるのかを読みとることが、読者に課せられた義務であろう。私の読みとった真実とは、上に示したようなものである。
- 付け足しであるが、この作品では「地下」とそれを巡る謎、そしてそこへの侵入ということが極めて重要なモチーフなのであるが、若干の論理の飛躍をお許し頂くとこれは例えばギリシャのエレウシスの儀式にも見られるかなり普遍的なものである。エレウシスの儀式では魂の浄化のために参加者は地下に潜り、様々な秘儀を行い、やがて地上に再生してくる。これは宗教学では「死と再生」の儀礼の典型とも見なされている。そしてまた魂の浄化とはプラトンを始めとするギリシャ哲学においてはカタルシスのことである。ここでは、こうしたモチーフが村上春樹の『ねじまき鳥クロニクル』シリーズにおける「井戸」を巡る挿話や、もちろん『エヴァ』におけるネルフの地下最深部「ターミナル・ドグマ」を巡る挿話でも形を変えて奏でられていることを指摘しておきたい。
- なお、この評論も含め、このホームページ上のテクストも初稿時以降の私の発見や思考を反映して随時書き換えられていることを最後に述べておく。(1997/8/8)