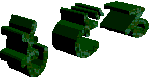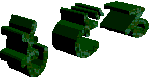山口雅也著『奇偶』講談社、2002.10
-
ヴァーチャルな世界の中で繰り広げられるさまざまな事件とその解決等々を描くことをお家芸としてきた山口雅也が放つ大長編ミステリである。右目の視力をほとんど失った作家の「手記」、という体裁をとる本作は、渋谷で遭遇する二つの事故とも他殺とも判断のつかない事件、同棲する女優がその精神障害を深めていく過程、「奇偶」教団という宗教団体で起きるゴタゴタへの巻き込まれ、等々を描いていく。
-
片目とはいえ視力をほとんど奪われ、同棲相手もどうかなってしまった作家の、鬱勃とした状況が暗澹とした筆致で描かれていくのだけれど、最後は<爆笑>。それは措くとして、とある登場人物がメタな形で次のように総括している通り、この作品では「連続する人の死に絡めて、偶然事象が頻発する――というような不可解な出来事が描かれていて、他の登場人物たちと、事件そっちのけで、蜿々(えんえん)と抽象的な議論が交わされる。《偶然》を俎上に載せて、物理学、数学、神学、哲学、文学、民俗学、心理学など――あらゆる分野からの検討がなされる。」(p.574)ことになるのだけれど、本書の各部において披瀝される「偶然」という現象をめぐりこれまでに諸学においてなされてきた諸議論自体が、そもそも誠に興味深いものだらけで、目から鱗なことも多々あるのであった。
-
そうそう、この本と同時並行的にRoger Penrose著 中村和幸訳『心は量子で語れるか』(講談社ブルーバックス、1999(1997→1998)。この本も「目から鱗」です。ご一読を。)を読んでいたのだけれど、この本がそもそも「偶然」という現象に言及している「偶然」は兎も角として、この宇宙が現在観測できるような「均一な膨張」を続ける形態になる確率は「10の10の123乗乗分の1より小さい」(表記のしようがない。まあ、取り敢えず途方もなく小さな確率である。)ということになるらしい(p.87)。うーむ、そうだとすると、『奇偶』なる書物のオチは、「あり得ない」ことではないのかも、などとも考えた次第。まあ、それでも爆笑できることには変わりないのだけれど、何故物凄く低い確率で存在している我々が、「起こり得ることは起こり得る」(何とかの法則というやつですな。)というよりは「起こりにくいことは起こりにくい」という常識を携えてその行動原理としているのか、ということ自体に改めて疑問を感じるに至ったのであった。
-
そろそろまとめよう。変格ミステリとしては究極の形態なのかも知れない本書は、一応今世紀初頭に書かれたミステリのなかでもそれなりの位置と意味を持つものなのではないか、と思う次第。取り敢えず山口雅也が書いてきた諸作品を含め、夢野久作のあの作品や竹本健治の諸作品みたいなものがお好きな方には一読を強くお薦めする次第。(2003/04/24)