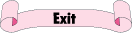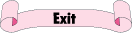篠田節子著、『斎藤家の核弾頭』朝日新聞社、1997
- 平成9年11月の現時点における篠田節子の最新作ということになるのだろう、約300頁に及ぶ書き下ろし長編である。近年乗りに乗るこの作者の作風は極めて幅広いものになりつつあり、本作品は「成慶五八年(2075)」の「日本国」の首都近郊を舞台とした近未来SFである。
- 私見では本作品に於いて篠田が意図したのは筒井康隆のパロディなのであり、一部のフェミニストから批判される筒井の諸作品に見られる「家父長制」的で「男根中心的=ファロサントリック」な部分を故意にデフォルメし、強調し、さらにはまたそうしたものの矛盾や馬鹿馬鹿しさ、あるいはそれが瓦解していく模様を描くことによって、笑い飛ばそうとしているかのように思われた。
- 物語の舞台となる成慶五八年の「日本国」では、「国家効率主義」とでも呼ぶべきものとされる主権者不在の超管理体制が引かれており、人々は「国民能力別総分類制度」によってランクづけられ、そんな中で女性達はよりよい遺伝子を持つ子供を大量に産み育てることが最大の「美徳」であるという意識を共有するに至っている。何となくハードコア・フェミニスト作家であるM.アトウッドの『侍女の物語』を思わせる設定だが、そこまで陰惨なものではなく、『女たちのジハード』と同様に篠田の筆致はあくまでもコミカルで、哄笑に満ちたものである。
- 物語の中心である斎藤家は、100階を超える超高層建築が当たり前になった東京の中心に近い文京区の東京大学の近くに相も変わらず一戸建てを構えている「旧家」であり、また、この時代においてはむしろ「美徳」と見なされる「伝統」的な「家父長制」的な家風を古くから維持して来たのだが、「日本国」の「高度土地利用法」の実施のために超高層ビルへの建て替えを強要され、それに「保守的」な土地所有観から反発したために「日本国」の奸計によって東京湾に浮かぶ「ベイシティ」への移転を強制される。ここでは、土地の私有を禁止することによって「家父長制」は瓦解する、というマルクス主義的なヴィジョンが暗に示されているのはいうまでもないが、それは措くとして、その後斎藤家はさらに「日本国」の都合によって千葉のある場所(ここも「国家とは何か?」、という問題を考えるためにはとても重要な場所である。)への移転を強要されるのだが、様々な偶然その他の事情によって斎藤家は移転反対派と共にベイシティにとどまることになり、元々「日本国」に遵奉してきた斎藤家当主・総一郎は「日本国」の度重なる立ち退き勧告その他の嫌がらせに最終的には激怒し、「日本国」に対し「宣戦布告」をし、最終戦争を挑むに至る。後は読んでのお楽しみである。
- 本作品においては、この時代の基本設定として、ある種のフェミニストが理念型として取りだし批判してきた「家父長制」的道徳観が「復活」し、広く行き渡っている、というものがあり、斎藤家の人々も一部を除けば女性を含めてほぼこれに準じていて、特に総一郎は徹底的に「家長」としての立場や体面に拘る。ただ、私などはそうした理念型的な「家父長制」的社会あるいは「家」というのが実際に存在している、あるいはしてきたということを実証するのは大変困難なことだと考えているわけで、そうしたものを誰にでも分かるような形で批判するには、恐らく現実には存在しないステレオタイプな人々を創出して、物語世界を構築するという方法が有効なわけである。ただ、そうすると物語はリアリティを失ってしまい、その結果批判力を自動的に喪失してしまうことにもなりかねないのだが、それは作品が書かれていること自体が虚構であるということを陰に陽に示すことによってある程度回避することが出来るのだと思う。すなわち、こういう極端な設定は本作品が実は現時点において作者によって虚構された話者によって創られた虚構であることを意識して書かれていることを匂わせることによって、20世紀末という現時点でのリアリティ、あるいはそれに基づいて湧出してくる批判力を回復しうるのではないかと考えるのである
- 以下、こうした点について本作品に即して簡単に考察を加えてみよう。作品の冒頭の部分では総一郎の妻・美和子の視点から、成慶五八年に至るまでの「日本国」の社会変動が「20世紀末」から述べられ、さらには成慶五八年の「日本国」の在り方が「20世紀末」との対比によって説明されている。実はこういう「説明」はその時代に生きている「当事者」には恐らく行い得ないことなのであって、だからこそ美和子も総一郎も「家父長制」的な諸制度に従っているわけだ。まあ、美和子は6人目の子供を身籠もることによって、こうした諸制度の理不尽さに気付くわけだが、それにしてもこういう管理体制を引くためには、たとえそれが誰か一部の人間の明確な意図を持ったものではなくとも、何らかの形での情報操作が不可欠であって、そうであれば当然「女性解放史」やフェミニズム思想などは「歴史」や「民間伝承」から抹消されているように思われ、そう考えると美和子が20世紀のフェミニズムに関する知識を一体何処から仕入れてきたのか?という疑問も湧いてしまうのである(昭和40年生まれの総一郎の祖母だったりして。でも、それはないよね。)。こうしたことから、本作品は篠田の旧作である『聖域』や『イビス』と同様に、篠田によって虚構された作者が書いている虚構内作品であるという前提があるのではないかと私などは考えてしまうのである。これは確かに篠田擁護かも知れないけれど、「読み方」の「自由」(「読み方=批評」、「自由」というのは、極めて政治的な概念である。)もまた我々には保証されていると一応考えれば、こういう読みも可能なのではないかと思うのだ。
- 実のところ、「未来人」の視点で「未来史」を、反対に「過去」の人々の視点で「歴史」を記述するなどということは不可能なこと、さらにはそれが妥当なものであるかどうかを現時点で判断することもまた不可能であることは「現時点」においては誰でもが知っていることである。それ故に本作品は実はメタ・フィクショナルなものであると考えた方が、作者の意図をうまくすくい上げることになるような気がするのである。
- 勿論、これは作者の技量による、という見方も出来なくはない。例えばC.スミスの『人類補完機構』シリーズにおける「未来史」や、あるいはW.フォークナーの一連の作品のように、それらが前提とする世界が個々の作品をあらかた読み尽くした上でようやくはっきりとした輪郭をもって読者に現れるというような、相互参照的な作品群を書き上げたとんでもない技量を持った作家もいないわけではないのだが、これを今日の日本で行えば、ベストセラーには成り得ないし、出版社も困ってしまうという実状があるわけで、それを踏まえて、あえてメタ・フィクショナルな面をさりげなく見せつつ、今日に生きる誰かがあたかも未来に於いて未来の誰かが語っているような文体を用いて「日本国」の「近未来史」を記述した、ということを考えていたのではないかと考える。実のところ、本作品が批判の対象としているのは、今日の「家父長制」的諸制度や、土地行政及び環境行政、あるいは偏差値主義、近代的効率主義などなのである。
- その他若干細かい点を述べると、例えば斎藤家の女性の名前の多くが今日でもかなり珍しくなった「−子」である点や、斎藤家当主が「−一郎」を代々祖名継承している点が面白かった。しかし、斎藤家の「長男」の名は「敬」であり、文京区の太田道灌から「下賜」された土地を追われ、さらにはやむを得ず美和子の出産の手伝いをさせられる「家長」総一郎の姿を考えると、実のところ本作品は「家父長制」が少しずつ解体されていくプロセスを描いているのだな、と考えてしまった。他に、「女性原理」を標榜する古典的フェミニストの末裔と見なしてよい「レサ」という女性の描き方は見事なまでに類型的かつ戯画的で、その悲惨な最期と共に非常に印象に残る。篠田の立場は、決して「本質主義」的なものではなく、現実に即したものであって、敢えていうならば「実存主義」的なものなのである。
- なお、本作品の主役と言っていいだろう美和子については、そのモデルはG.スピヴァックがベンガーリー語から英語に訳し、その邦訳書に所収されている、マハスウェータ・デヴィの「乳を与える女」(所収『文化としての他者』紀伊國屋書店、1990(1987))に登場する「ジャショーダ」という名の乳母のような気もする。彼女は自分の主人(夫という意味ではない。)の子供たちに乳を与えるべく、それだけのために産みたくもない子供を産ませられ続けるのである。
- 最後に、どうでもいいことだが、同著者による『女たちのジハード』が幾つかの書店で内田康夫などと一緒に「ミステリー」の棚に置かれているのには笑わせられた。「ミステリー」は極めて広義なものであるという観点から、鈴木光司や板東眞砂子の作品がそういうところに置かれているのと同様に、そうした系列に属する本作品ならまだ分かるのだけれど、『女たちのジハード』は絶対に「ミステリー」ではない。(1997/11/09)