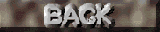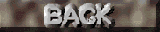小谷真理著『聖母エヴァンゲリオン-A New Millennialist Perspective on the Daughters of EVE』マガジンハウス、1997
- 本書は、いよいよ今週末(7/19)に「完結」するらしい『新世紀エヴァンゲリオン』(以下慣例に従って『エヴァ』。)を、D.ハラウェイのサイボーグ・フェミニズム、J.クリステヴァのアブジェクシオン論、A.ジャーディンが提示した「ガイネーシス(女性的なもの)」という概念、及びグノーシス主義の視点から論じたものである。他の『エヴァ』研究書その他を全く読んでいないので何とも言えないのだが、本書はあくまでもそうしたアカデミックな姿勢を貫き通すことによって、ある程度一般性を持ったテクストになっているのではないかと思う。以下、大まかに要約するならば、本書では『エヴァ』というアニメーション作品が、家父長制的社会構造及び世界観と、基本的にはそれに基づいているという電気中心主義(本書に従えば「電気的物語学」。)がクリステヴァのいうような、そうした体制においては常に抑圧されているべきはずの「おぞましきもの(アブジェクト)」=「女性性」の止めどもない侵犯によって解体されていくプロセスを示すことによって、1990年代のフェミニズム(ここでは「同性愛的サイボーグ・フェミニズム」ということになろう。)及びテクノロジー(遺伝子工学及び電子・情報工学の急速な発達は、確かにサイボーグ時代の到来を予感させる。)と反響しあう作品と見ることが可能であることが述べられ、上記のような視点からの解釈が行われている。大変示唆に富む本書を私は、本来ならば「女性学」コーナーなどにD.ハラウェイなどと並んで置かれていてもおかしくない内容を持つものであるにも関わらず、そのやや派手な装幀やふんだんに散りばめられたカラー図版、及びタイトルからして致し方ないのかも知れないが、結局某大書店のコミックコーナーに平積みになっているものを購入する羽目になった。
- まず始めにこの書評を読んで下さっている篤志に申し上げておかねばならないが、本書評はこれを読まれる方が『エヴァ』のいくつかのヴァージョン(TV版、コミック版、劇場公開版、CD-ROM版、その他おそらく存在している膨大な数の同人誌版)のうち少なくともTV版の内容をある程度知悉していることを前提に書かれているために、そうでない方には極めて分かりにくいものになっている可能性がある。まあ、少なくとも誰にでも了解可能なテクストを生成することは至難の業なのであり、私は誰にでも開かれたテクスト生成を目指している訳ではないので、『エヴァ』の要約や登場人物のプロフィールや術語設定などはあえて記さないことにする。それはおそらくどこかのホームページに載っているはずである。TV版を見ておられない方は、そちらを先にご覧になって欲しい。なお、ここでは早くも『エヴァ』自体が誰にでも開かれたテクストなのか、という問題が生じてしまっているし、『エヴァ』の中でも「他者」と「自己」の弁証法的相互認知プロセスによる社会的自我形成が一つの主題になっているために、これについても詳細に論じたいところなのだが、それらのことは私の社会人類学的日本文化研究の中で形を変えて扱っているつもりなのでそちらを参照して頂きたい。
- もう一つ断っておくと、私は『エヴァ』については劇場公開「完結」編である『The End of Evangelion Air/まごころを、君に』の評論を、もし観る機会があれば本ホームページの「映画評」のところに載せるつもりであったが(少なくとも相当先の話になると思う。)、個人的にはこの作品は後でまた触れることになるがTV放映時に一つの「完結」を迎えてしまったと考えており、実際に劇場版第1弾『DEATH/REBIRTH』が別ヴァージョン的な展開をしている、つまりそのことからも第2弾では別の結末が用意されていることが予測されるわけであるし、さらにまた私は未見だがCD-ROMドラマではさらに別のヴァージョンが展開されているようなので、ここではあくまでも「完結」直前の際どいタイミングで出版された小谷の著作から受けた印象を示すと共に、それとはまた別の私的TV版+劇場版第1弾『エヴァ』解釈を加えてみたいと考えた次第である。なお、そういった様々なヴァージョンへと進化あるいは変化を遂げる『エヴァ』は、元になった作品自体(TV放映版)が、主人公の一人碇シンジの父・碇ゲンドウの所属していた「人工進化研究所」が「人類補完委員会」=国際機関「ゼーレ(Seele:魂)」の下部組織である実行機関ネルフ(Nerv:神経)の前身であった、あるいは吸収合併されたらしいことなどからも分かる通り「進化」を一つのテーマにしていたことを考えると、作品世界外部をも含んで複雑な入れ子構造を持っていることになり、大変興味深い(なお、ゲンドウの旧姓は「六分儀」である。碇はシンジの母・ユイの姓であり、このことは小谷の指摘する通りネルフが疑似家父長制的組織であることを示唆する。)。現実と虚構は後にも述べる通り、極めて見分けにくいものなのである。
- さて、私見では『エヴァ』はおそらく日本初のメタ・フィクショナルかつポリ・フィクショナルかつノン・フィクショナル(「物語性」を回避している、という意味である。)なアニメーション作品であり、それは日本のアニメーションが、多義的テクストの総本舗J.ジョイスの影響下にあるT.ピンチョン、J.バーンズ、U.エーコ、I.カルヴィーノ、P.オースター、J.バースといった人々の作品群に現れているいわゆるポストモダン文学的な手法をついに手にしたか、という感慨を抱かせる作品である。これまでのアニメーション作品はあまりにもモダン(アニメーション自体、複製文化の象徴でさえある。)かつ分かりやすいものであり、本作品も第拾参話まではそれなりにそういう構造を保持しているわけだが(実は『ウルトラマン』、『ウルトラセヴン』のパロディである。)、第拾四話におけるクローン少女綾波レイの「自己懐疑」(これをR.ヴァーグナーの『神々の黄昏』におけるブリュンヒルデと比較しても面白いと思う。近代とは、A.ランボーに乱暴に従うならば「自己」という名の「他者」の創出・発見に他ならないのだから。少し付け加えると、『エヴァ』には同じくワーグナーが死の一年前に書いた舞台神聖祝典劇『パルジファル』からのモチーフ及びプロットの借用が顕著に見出せる。この劇の中心となる舞台はモンサルヴァトと呼ばれる聖杯の地、すなわちかつて十字架上のキリストを刺した聖なる槍とその血を受けた聖なる杯を守護する騎士達の住む城とその付近である。しかし騎士の一人クリングゾールの謀反によって、その平和と秩序は乱され、王位継承者であるアンフォルタスはクリングゾールとの戦いの中で聖槍により脇腹に傷を受ける。後にモンサルヴァトの救済者となる主人公パルジファルはまず何も知らない愚かな若者として登場する。彼は自分の名も、その出生にまつわる事柄も忘れている。かろうじて思い出せるのは母の名前のみである。そしてその愚かさ故にモンサルヴァトを追い出された後、クリングゾールの魔法の城に迷い込み、パルジファルを恐れるクリングゾールから彼をかどわかせという命令を受けた、純潔な改悛者と邪な誘惑者という二面性を持つ美女クンドリに誘惑されるがこれをはねつける。焦ったクリングゾールはパルジファルに聖槍を投げつけるが空中で静止してしまう。聖槍を奪ったパルジファルがこれを持って十字を切ると魔法の城は崩壊する。その後モンサルヴァトに戻ったパルジファルは聖槍の力によりアンフォルタスの脇腹の傷を治す。シンジをパルジファルに見立てることはたやすいし、第弐拾話でのエヴァンゲリオン(以下、エヴァ。)初号機に取り込まれたシンジの意識内における葛城ミサト、綾波レイ、惣流・アスカ・ラングレーら3人による誘惑のイメージは、明らかにクンドリの誘惑を意識しているように見える。そしてまた『エヴァ』の主要なアイテムとして現れる「ロンギヌスの槍」とは、ここで登場する聖槍に他ならない。なお、ここではH.クナッパーツブッシュ指揮『パルジファル』フィリップス、PHCP-1358〜61の解説を参考にした。)から一転してメタ・ポリ・ノン・フィクション化する。ちなみに第弐拾話ではシンジの「自己懐疑」が示されるわけだが、第拾四話が英語ではweaving a story、第弐拾話が同じくweaving a story 2:oral stageと題されているが(これらはCMを挟んで2回表示される。)、この辺りはピンチョンの『競売ナンバー49の叫び』で引用されたレメディオス・バロの絵画『大地のマントを織り紡ぐ』を喚起させる。脱線している。話を小谷の著作に引き戻そう。
- 小谷は永井豪の『デビルマン』を引き合いにして、そこにおいて現れ、かつまた『エヴァ』にも濃厚に見られるグノーシス主義的世界観に言及することによって、2作品をつなぐ。小谷は荒井献の著書『トマスによる福音書』の議論を援用しながら、グノーシス主義が持つ、メインカルチャーでありまたフェミニズムが乗り越えんとする家父長制の根元であるキリスト教へのカウンターカルチャー的側面を強調しつつ、これが1970年代の日本及び1990年代の日本において、フェミニズム的言説やテクノロジーの変化を反映した形で、つまり別の形で現れたのであるとする。すなわちそれは、基本的にはどちらの場合も、西洋文化に染まりながらも、内なる他者としての西洋に対する東洋を抱え込んだ自己のアンビヴァレンスの発見であり、その解決のために西洋=デーミウルゴス(善・悪の二面性を持つ世界の創造者。『デビルマン』では西洋文化、あるいはキリスト教的神、『エヴァ』ではゼーレがこれにあたる。)を相対化してさらに上位の至高者(「プロパテール=原父」ないしは「プネウマ=霊」。C.G.ユンク的には「全きアイオーン」。)と合一するというようなヴィジョンを描くのであると。そしてここからが本書の最も重要な提言なのだが、そうしたある種弁証法的なプロセスはどこまで行っても際限がなく、そうした「信仰の繰り返し構造が立ち現れるばかり」なのであり、そういう永劫回帰のジレンマを乗り越える手段の一つとして、「人類の敵」として現れた「使徒」の目標と考えられていたネルフ本部地下の「セントラル・ドグマ」内に置かれている「アダム」(男性性を象徴する。)が実は男装する女性「リリス」(女性性を象徴する。)であったことが第弐拾四話において暴露されるのであると。このようにして『エヴァ』は、予期せぬ女性性の噴出によって西洋キリスト教的二元論に揺さぶりをかけ、そうすることによりそれを根元に持つ家父長制を乗り越えようとする、クリステヴァの提示した戦略を持つフェミニズムの分脈において読みうる、というわけである。
- 誠に面白い解釈である。こんな読み方も出来るのか、と思わず感心してしまうわけであるが、野暮であることは自覚しつつも3つばかり問題点を示したい。まず第1に、ここで小谷はどういう訳か「セントラル・ドグマ」という生物学上の基本タームについてきちんと論じていない(奇妙なことにp.33ではあるSF小説からの引用という形で説明がなされている。何故『生物学事典』のような本からではないのか?)。これは「遺伝情報は細胞の外部から入り込むことはない。」というかつての生物学における「教条=ドグマ」であり、それはその後逆転写酵素を持つエイズウィルスなどのレトロ・ウィルスの発見によって覆されてしまったわけである。つまり、「遺伝情報は細胞外のウィルスが媒介しうる。」というのが現在の生物学における「教条」である。使徒の体現する外なる他者性、あるいは内なる他者性という両義性を論じているのだから、レトロ・ウィルスや、それを媒介にして生物は進化した、という現在かなり有力になっている学説についても触れて欲しかったと思う。この作品の一つのテーマは先述の通り「進化」なのだから。
- 第2に、小谷は本書の中でE.サイードの『オリエンタリズム』まで援用し、サイボーグ・フェミニズムやアブジェクシオン論による西洋的な男性/女性、西洋/東洋という二元論の乗り越えを模索している訳だが、実のところかなり西洋的な二元論に忠実に従っているようにも見える。私は男性/女性の二分法を乗り越えるためには、女性性というものを男性性に対立するものとしてたて、後者による前者の抑圧の図式、及び抑圧すればするほど鮮明に現れてしまうという女性性について語るだけでは不十分であると思うし、これはある意味で本質論への回帰でさえあるように思う。せっかくクリステヴァを出してきたのであるから、小谷が『エヴァ』において随所に見出しているように思われる多形倒錯的なものをもっと強調すべきだったのではないかと思う。また、小谷は「同性愛」という言葉を盛んに用いるが、これは近代において「異性愛」と同時発生的に、後者を特権化し前者を抑圧するために現れた概念であるというのが一般的な見解であろう。この言葉にこだわっているうちは西洋的二元論からの離脱は困難である。むしろ小谷のいう「新・千年王国」において実現されると考えているらしい、本書でもその一端が伺えるが言表されていないタームであるクリステヴァのいう「多形倒錯的なエロス」への希求というヴィジョンを打ち出すべきだったのではないかと考えてしまう。私自身は『エヴァ』の最後の2話はまさにそういう状況を示していると見ていたのだけれども(そこに現れていることはまさにクリステヴァが『ポリローグ』で示したようなヴィジョンである。)。
- それとの関連で、小谷が本書で基本的に従っている、グノーシス主義はキリスト教内部の異端派である、という解釈はユンク・秋山さと子・P.K.ディック・大瀧啓裕その他多くの著述家が指摘するようにキリスト教の側からのものであり、それとは逆に、例えば『ナグ・ハマディ写本』を基にすれば、グノーシス主義はキリスト教とは独立した宗教体系であるという解釈も成り立つ、という見解が存在することも付け加えておきたい。もちろん、キリスト教徒の中の周辺化された人々が、そうした外部の宗教体系を取り込むことによってメインカルチャーに抵抗した、という見方も可能である。この辺りの各解釈の複雑な関係をきちんと示しておかなければ、問題を一元化してしまい、さらにはあらぬ誤解を生じることになるように思う。さらにもう一つ、小谷は瀬名秀明の『パラサイト・イヴ』をやたらと誉めているのだが、あの小説は「意識」や「意志」を持ち得ないミトコンドリアを擬人化し、さらに罪深いことにはそれに女性という性を当てはめてしまった、つまり「隷従するもの=女性」という瀬名の性差別的女性観を表明しているに過ぎないように思われた点で、私にとっては必ずしも納得のいくものではなかったことを述べておきたい。これに比べれば、明らかに瀬名批判を意識して書かれた村上龍の『ヒュウガ・ウィルス』の方が遙かに説得力がある。なお、ミトコンドリアとは我々も含む酸素呼吸によってエネルギーを得ている生物がそのエネルギー源として各細胞に内蔵しているものである。瀬名の本にも出てくるが、一説では本来嫌気性であった微生物がミトコンドリアの原型である好気性の微生物を体内に取り入れ共生するようになったのが我々のような酸素呼吸生物の起源である、ともいわれている。この辺りのことは後に述べるS-2機関とエヴァの関係のようで、面白いと思う。
- さて、第3の問題点であるが、そこで対象となる最後の2話、第弐拾五話及び第弐拾六話については、私は同書p.144にある「奇妙に腑に落ちる」という表現に近い感覚を、小谷とは全く異なった思考過程から導き出していた。『エヴァ』が放映終了後しばらく経ってから多くの人々の注目を集め出し、その後幅広い年齢層にわたる人々による過剰なまでの議論が行われ、数多くの謎解き本が出回るようになったのは、もちろん作品が恐ろしく情報過多であることや作品中で提示された様々な謎が結局何の説明もないまま残された、ということももちろんであろうが、やはりなんと言っても侃々諤々・賛否両論の論議を呼んでしまったのは最後の2話であると思う。第弐拾四話で、シンジは最後の使徒と見なされる渚カヲルを殺害する。カヲルは人間と同じ姿をしており、同話ではシンジが生まれて初めて心を通わせることが出来た「友」であるような描写がなされる(小谷はこれを同性愛に引きつけている。)。最後の2話はそのカヲル殺害の正当性その他を巡って逡巡するシンジの魂の彷徨を描く。そして、それこそが人類の「補完」というプロセスの一環であり、シンジはどうやら補完の作業が進むにつれ産み出されつつある意識の集合体の中で彼自身の魂の補完を施されている、というようなヴィジョンが示される。この2話はかなり唐突なものであるし、一般のアニメーション作品の文体・語法からは大きく外れているし、これまで提示されてきた謎にさらに輪をかけるもの、というような印象を抱いた視聴者が大勢を占めたであろうことは想像に難くない。しかし、私にとってはむしろ、「これはこれでいいんじゃないの?」、と納得してしまえるものであった。それは第弐拾六話を見終わった段階で私が思い浮かべた作品を並べてみればはっきりするであろう。S.キューブリックの『時計じかけのオレンジ』及び小谷も言及している『2001年宇宙の旅』、ディックの『ユービック』、『ヴァリス』、『高い城の男』、さらにはR.スコットによって映画化された『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』(自分が人間であるかどうかに疑問を抱く主人公デッカード=デカルトが追うのは人工的に作られありもしなかった幼少時からの記憶を植え付けられたレプリカント達。その中で最も完成度の高い女性型レプリカントの名はレイチェル。)、同じく彼の原作に基づく映画『トータル・リコール』、T.ギリアムの『ブラジル』、村上春樹の『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』、長野まゆみの『テレヴィジョン・シティ』、夢野久作の『ドグラマグラ』、C.D.シマックの『都市』、B.W.オールディスの『地球の長い午後』、O.ステイプルドンの『スターメイカー』、A.C.クラークの『地球幼年期の終わり』、J.G.バラードの『夢幻会社』及び『太陽の帝国』、S.レムの『浴槽で発見された手記』、G.オーウェルの『1984』、E.クストリッツァの『アンダーグラウンド』、P.J.ファーマーの「リヴァー・ワールド・シリーズ」、岡嶋二人の『クラインの壺』、M.プルーストの『失われた時を求めて』、M.エンデの『はてしない物語』、そしてもちろん、H.エリスンの『世界の中心で愛を叫んだけもの』(どうやら私はこの作品をハヤカワ文庫の初版が出版された1979年に読んだらしい。)。
- これらの作品群のうちの幾つかに見られる共通点は、「現実とは何か?」という根本的な問題に対して、悲観的あるいは楽観的に、様々なヴァリエーションを持ちながら基本的には「それは意識が作り出すものである。」、あるいはまた「それはテクストである。」、さらには「現実と虚構をはっきりと区別することは不可能である。」というヴィジョンを打ち出していることである。さらにまた、もう一つ重要な点としてこれらのうちの幾つかの作品中には「全人類の意識の統合」あるいは「意識の進化」とでも言うべきヴィジョンが見出せることを述べておかねばなるまい。さて後者については後回しにすることにして、ここで前者のヴィジョンを持つ作品群に少々こだわるならば、こうした作品の中にあっての悲観の極みは『ブラジル』、『1984』辺りで、ここでは洗脳・管理社会の恐怖が描かれる。反対に楽観の極みは『夢幻会社』である。主人公は飛行機事故に遭うのだが、その後彼は全てが彼の思い通りになる世界に移行し、その事実に彼自身が気付くまでの過程が描かれる。なお、『時計じかけのオレンジ』においても『エヴァ』第弐拾四話で用いられたL.V.ベートーヴェンの第9交響曲がふんだんに使われている。この映画で主人公に施される洗脳は、レイプや殺人といった内容の暴力性に富んだフィルムを強制的に見せ続け、それによって暴力への忌避感を植え付けるというものであり、小谷も言及しているD.クローネンバーグの『ヴィデオドローム』にもかなりの影響を与えている(オリエンタリズムと異装趣味を持ち出している以上、D.H.ウォンの手による戯曲をクローネンバーグ監督が映画化した『M.バタフライ』にも深く言及するべきではなかったのだろうか。あるいは編集上の都合でカットされたのであろうか?)。そう考えると『エヴァ』の第弐話から第弐拾参話までが実はシンジを洗脳するためのヴィデオ作品である、という解釈も不可能ではない(背筋が凍るような解釈だ。)。また、脱線している。話を戻そう。
- ここでの問題は、以下では先ほど後回しにした点に引きつけて考えるならば、いわゆる「人類補完計画」が小谷の言う「新・千年王国 New Millennialism」のような明るい未来を約束するものなのか否か、あるいはさらに後者もまた何らかの危険性を孕んでいないかということである。人間あるいはヒトが不完全なものであり、いずれは完全なものに進化する、あるいは進化せねばならない、という思想は基本的にはベートーヴェンと同時期のドイツ啓蒙主義時代の最大の哲学者であったG.W.F.ヘーゲルのいうような唯物論的弁証法による絶対精神という完全性への希求、あるいはヘーゲルの否定的継承者G.バタイユのいう至高性への希求と酷似するイメージである。『エヴァ』ではそれは人工的に行われる進化として現れてくる。ここで注意しなければならないのは、そうした思想は19世紀以来ずっと唱えられてきたということ、そしてC.ダーウィンの進化論や、G.J.メンデルの創始した遺伝学の発達によってそれらの思想の一部は「優生学」と呼ばれるものに変貌し、人体実験や「完全」とは見なされないものたちの排除という悪しき結果を生んでしまったということである。私は小谷とは全く反対に、『エヴァ』はそうした優生学や選民主義、あるいはウルトラ管理社会の恐ろしさを描くことによって、『ブラジル』や『1984』と同じようなメッセージを放っているものと解釈した。つまり、私の解釈では「人類補完計画」とは人類自身による、何らかのテクノロジー(エヴァの身体へのユイの人格移植、あるいはそれとは逆にエヴァの身体に溶け込んでしまったシンジの引き揚げ作業に用いられた「サルベイジ」、あるいはネルフを統御するスーパー・コンピューターである「マギ」のオペレーティング・システム開発に用いられた「人格移植」ということになるのだろうか。)による意識の集合体への進化をいうのだろうと想像していた。そして『エヴァ』は「そんなものが進化といえるのか?ファシズムではないのか?」という問いを突きつけているのだと。そう考えれば、その続編(そんなものは別になくてもいいと思ったのではあるが。)はシンジその他の人々の補完からの脱出(あるいは外部からの救出?)を描くことになるのではないかと考えていた。あるいはまた『ユービック』で描かれたような、補完された世界内での闘争が描かれるのではないかと。(ちなみに、村上春樹は『ハードボイルド・ワンダーランド』の続編を書き始めたらしいが、これもまた「世界の終末」からの脱出の物語になることが推測される。そんなこともあって、『エヴァ』にもそういう展開を期待したのだが、私の予測を大きく外れたものになるらしい。まだ何とも言えないが。結局補完されてしまったりして。ただし、そういう私を含む視聴者による自分勝手な物語の創出に対しては、『エヴァ』は限りなく寛容である。筒井康隆が行ったようなインタラクションは見受けられないが。私もまた、自分勝手な解釈を施すことによって補完されているということだろうか?)
- 話が深刻になってしまった。ここから先は付け足しである。あくまで深刻なテクストにならないための。
- 五つの章の中でずば抜けて面白かったのは『エヴァ』の変態論的読解(クィア・リーディング)を試みている第弐章である。シンジが男性同性愛的(イヴ・セジウィックの言うホモソーシャルな)政治学を、最後の使者(第17使徒)であるカヲルが「やおい的同性愛」(同じく、ホモセクシャルな)の政治学を体現する、という下りには爆笑してしまった。私は両性具有的な名前を持ったカヲルが登場し、何故か現れたレイとの視線での対話をしつつあっさりと死んでいくというシーンから、続く第弐拾五、弐拾六話に示された「世界の終わりの物語」の別ヴァージョンとして、そしてまた「光の巨人」のコピーであるエヴァの物語、すなわち『エヴァ』の別ヴァージョンとして、「闇の少年」カヲルを中心とする物語が存在するのではないかと邪推した。その物語とはもちろん、『源氏物語』のあの素晴らしい末尾である「宇治十帖」(これまた、唐突に終わるのだが。)のパロディになるはずのものであり、そこでは同じ姿形をした3人のレイへの永遠に叶うことのない儚い恋慕の物語ということになるのではないかなどと想像をたくましくしてしまった。ちなみにTV放映版のうちの第壱話から第弐拾四話のダイジェストである劇場版『DEATH』では、シンジが第3新東京市に来る前に通っていた中学校の音楽練習室におけるJ.S.バッハの弦楽四重奏曲(バロック音楽は概してポリフォニックである。)の練習風景が挟み込まれており、これはどうやら第弐拾五、弐拾六話とはまた別の「終わりの物語」を示すものとして語られているらしく、そこにおいてカヲルは第1ヴァイオリン奏者として現れる。
- 話はずれるが、『源氏』を仏教的輪廻観に根ざした光源氏の転生の物語として見るならば、それを直接応用した三島由紀夫の『豊饒の海』4部作や(特にこのシリーズの第3巻『暁の寺』は一種の仏教思想論でさえある。これを『エヴァ』のほとんどわざとらしいともいえるキリスト教的モチーフの多用と対比するのも面白いだろう。)、あるいは遠回しに応用したP.K.ディックの『ヴァリス』を中心とした4作品(『アルベマス』『ヴァリス』『聖なる侵入』『ティモシー・アーチャーの転生』)との関係を考えてもよいだろう。この辺りは将来『エヴァ』とは無関係に論じる用意があるので、期待して頂きたい。なお、『ヴァリス』シリーズは『エヴァ』でも主要モチーフとなっている『死海写本』(ただし、あくまでも『裏死海写本』である。)、及びグノーシス主義研究上の基本文献『ナグ・ハマディ写本』を大フューチャーした作品であり、『T.A.の転生』ではさらにディックの捏造と思われる『サドク文書』なるものが現れる(実在していたらごめんなさい。なお、『ヴァリス』巻末にまとめられている同書の翻訳者大瀧の手による用語解説集「Adversaria」はグノーシス主義やカッバッラー、さらにはヤコブ・ベーメ神学などを知る上で大変参考になる。『エヴァ』のオープニングに現れる「セフィロト樹」についての記述のないのが残念であるが、これについてはU.エーコのオカルト百科全書小説『フーコーの振り子』を参照するとよい。当然それらは『エヴァ』解釈にも有用である。)。
- 最後に一つだけ付け加えておきたいことがある。小谷は第弐章の中の葛城ミサト論においてせっかくヴェジタリアン・フェミニズムを持ち出したのだから、『エヴァ』の総監督である庵野秀明がかつて手掛けた作品『ふしぎの海のナディア』にも言及して頂きたかった。これは『エヴァ』の5年前にNHKで39回にわたって放送されたものである。舞台となる時代はヴィクトリア朝の時代と呼ばれる19世紀の末期、主人公ナディアはアフリカ系フランス人であり、ヴェジタリアンである。そのためかどうかは不明だがひどく痩せている。あたかもエヴァのように。この物語の中では父との葛藤と和解、正義の名の下での殺人及び腹を満たすための動物の殺害の正当性への問い掛けというモチーフが執拗に繰り返される。小谷の『エヴァ』論読了後の私見を述べるなら、エヴァは肉を食い始めたナディアである(エヴァ初号機は第拾九話において、使徒を倒し、その肉を食らい、S-2機関と呼ばれるエネルギー源を自らに取り込む。エヴァはケーブル経由の外部電源あるいは内蔵の電池でしか動くことが出来ない不完全な生命体=兵器である。ちなみに電池は3分、だったら笑えるがどちらにせよ5分しか持たない。この辺りの図式は、エヴァと使徒がほとんど同類であることが明らかにされた以上、このシーンが共食い、すなわちカニバリズムであることや、さらにはそれが実は臓器移植の問題とも密接に絡められて扱われていることを示している。どうです、深いドラマでしょう?)。ちなみにナディアNadiaはダイアナDianaのアナグラムである。さらに言うならダイアナはローマ神話では月の女神であり、女性と狩猟の守護神でもある。人類学者J.G.フレーザーの大著『金枝篇』はここからスタートする。この調子で続けていたらライフワークになってしまいそうだ。それについては、S.T.コールリッジのひそみに倣って、そういうテクスト(『聖槍篇』とでも題すればよいのだろうか?)の将来における存在可能性のみを示しておこう。そんなことよりも先に、今の私には私にとっての良い意味での「人類学補完計画」とでも言うべきものの構想を練らなければならないというやむにやまれぬ事情があるのである。
- この書評もまた、TV版『エヴァ』最後の2話に倣って、何らの結論も示すことなく、ここいら辺で唐突に終えたいと思う。(1997/7/14。7/15に若干の変更。7/18にかなりの追加。8/22に4文字の修正。)