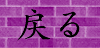怴彂憂姧儔僢僔儏偲傕尵偊傞嶐崱偺弌斉嬈奅丅梋傝偵傕揰悢偑懡夁偓傞偺偱埲壓偱偼娙扨側徯夘偲僐儊儞僩偺傒晅偡偙偲偵偟傑偡乮偳偙偑丠乯丅
嵅摗椙柧挊亀J-POP恑壔榑亅乽儓僒儂僀愡乿偐傜乽Automatic乿傊亅亁暯杴幮怴彂丄1999.3
惤偵夋婜揑側彂丅婎杮揑偵偼屘丒彫愹暥晇偺巇帠偺墑挿慄忋偵偁傞偺偩偗傟偳丄彫愹偑堄恾偟偰偐偳偆偐偼崱偲側偭偰偼暘偐傜側偄偗傟偳丄寢壥揑偵暥壔僫僔儑僫儕僘儉傪巙岦偟偰偟傑偭偰偄偨偺偵懳偟偰丄嵅摗偼傛傝僌儘乕僶儖側帇揰傪堐帩偟偮偮丄嬤戙壔傗僐儘僯傾儕僘儉偺栤戣偵傑偱尵媦偟側偑傜嬤擭偺J-POP惉棫傑偱偺乽擔杮戝廜壒妝100擭巎乿乮乽戝廜壒妝乿偲偄偆岅偼傑偢偄偐側丅偱傕丄懠偵偄偄尵梩偑晜偐偽側偄丅乯傪儊儘僨傿丒僐乕僪丒儕僘儉偺挌擩側丄杦偳儅僯傾僢僋偲傕尵偊傞傛偆側暘愅偵婎偯偄偰婰弎偡傞丅寢嬊偺偲偙傠丄偦傟偼E乮uropean乯丒B乮lack乯丒J乮apanese乯偺偣傔偓崌偄偵傛偭偰愢柧偝傟傞偺偩偗傟偳丄E偲B偺娭學偑暷塸偲擔杮偱偼慡偔媡偱偁偭偨丄偲弎傋傞嵅摗偺宒娽偵嬃偔丅妋偐偵丄乽崱峏擔丒墷斾妑側傫偰乧丅乿丄偲偄偆堄尒傕偁傝偦偆偩偗傟偳丄偙偲擔杮崙撪偺嬤戙壒妝偵娭偟偰偼埑搢揑偵E偲丄E傪宱桼偟偨B偺塭嬁傪旐偭偰偒偨傢偗偩偐傜丄偙傟偼偙傟偱惓偟偄偲巚偆丅偨偩丄挊幰偺尵偆乽嫻乿乽暊乿乽崢乿偲偄偆恎懱乮嵅摗揑偵偼乽儃僨傿乿乯偲偺娭傢傝傪丄彮側偔偲傕墘憈庡懱偵娭偟偰偼挻墇偟偰偟傑偭偨偐偵巚傢傟傞僐儞僺儏乕僞丒儈儏乕僕僢僋偺怹摟偵偮偄偰偺尵媦偑偁偭偰傕椙偐偭偨偐傕抦傟側偄丅梫偡傞偵丄僥僋僲丅嵅摗偵廗偭偰丄T乮echno乯偲偱傕偟偨偄偲偙傠丅偦傟偙偦丄乽噣僴僀僷乕儕傾儖噥乿乮p.215乯側壒妝宍懺偱偁傞僐儞僺儏乕僞丒儈儏乕僕僢僋偑丄偙偙20擭埵偺娫偺壒妝揑抧恾偺昤偒姺偊偵壥偨偟偨栶妱偼柍帇偟摼側偄傛偆偵巚偆丅嵟憗丄墘憈偵偍偄偰丄杮彂偱嵅摗偑愢柧偺偨傔偵戝検偵採帵偟偨傛偆側妝晥傕僐乕僪傕梫傜側偄忬嫷偵側傝偮偮偁傞偺偩丅偦傟偑丄杮棃偺宍偐傕抦傟側偄偗傟偳丅傕偆堦偮晅偗壛偊傞偲丄摿偵塸暷偵偍偗傞傾僀儖儔儞僪弌恎偺儈儏乕僕僔儍儞偺妶桇怳傝偼栚妎傑偟偄傕偺偩偟丄偦傕偦傕嵅摗偑壜惉傝偺暸傪妱偄偰偄傞The
Beatles偐傜偟偰丄働儖僩乮Celt丅嵅摗揑偵偼C偲偱傕側傞偺偩傠偆偐丅乯偲傑偱偼尵傢偢偲傕丄僗僐僢僩儔儞僪丒傾僀儖儔儞僪偦偺懠偺乽揱摑乿壒妝偺塭嬁偼寁傝抦傟側偄傕偺偩丅偙傟偵懳偟偰丄擔杮偺暥柆偱偼丄壂撽導弌恎偺壧庤払偺妶桇怳傝偼偙傟傑偨惤偵栚妎傑偟偄傕偺偱偼偁傞偺偩偗傟偳丄斵摍偑峴偭偰偄傞偺偑壂撽乽揱摑乿壒妝偱偼側偄丄偲偄偆僘儗傕傑偨丄惤偵嫽枴怺偄偲巚偆偺偩偗傟偳丅埨幒撧旤宐傗SPEED偵傑偱尵媦偟偨偺偩偐傜丄偦偙傑偱彂偄偰梸偟偐偭偨偲偙傠丅傑偁丄柍偄暔偹偩傝偼椙偔側偄偺偐傕抦傟側偄偺傕妋偐偩傠偆丅乮偁乕丄挿偄丅乯
媨揷搊挊亀姤崶憭嵳亁娾攇怴彂丄1999.9
惗慜姧峴偱偼嵟屻偺挊嶌丄偲偄偆偙偲偵側傞偺偩傠偆偐丅偦偺梋傝偵傕憗夁偓傞巰傪搲傓丅偝偰丄杮彂偵偍偄偰挊幰偼丄乽楈嵃娤乿傪僉乕僞乕儉偲偟側偑傜丄擔杮偵偍偗傞恖惗媀楃偺嵼傝曽偵偮偄偰偺柉懎妛揑暘愅傪峴偭偰偄傞丅奺復偼乽榁恖偺廽偄乿乽抋惗偲堢帣乿乽惉恖偲寢崶乿乽憭憲偲嫙梴乿偲偄偆弴偵暲傋傜傟偰偄傞偑丄偦傟偧傟偺抜奒偼楈嵃偺堏摦丄曄壔偺惗偠傞帪婜偵摉偨傝丄偦偙偵偍偄偰峴傢傟傞奺庬媀楃偼丄楈嵃偺埨掕壔丄僐儞僩儘乕儖傪栚巜偡傕偺丄偲偄偆帇揰偑壖愢偲偟偰帵偝傟傞丅側偍丄乽偁偲偑偒乿偱偼乽恖惗偺媀楃偺婎掙偵偐偐傢傞擔杮恖偺楈嵃娤偺媶柧傪傕堄恾偟偨偺偱偁傞偑丄側偐側偐偦偺傛偆偵偼帄傜側偐偭偨偙偲偼巆擮偱偁傝丄崱屻偺壽戣偵巆偟偰偍偒偨偄丅乿乮p.197乯偲弎傋傜傟偰偄傞丅変乆偼丄偦偺堚巙傪堷偒宲偑偹偽側傜側偄丄偲巚偆丅乮2000/02/21乯
惗嬵岶彶挊亀僀儞僞乕僱僢僩偺拞偺恄乆亅21悽婭偺廆嫵嬻娫亅亁暯杴幮怴彂丄1999.10
傾儊儕僇崌廈崙偺廆嫵帠忣偲儊僨傿傾偺娭傢傝傪傑偲傔偨忋偱丄嬤擭偺奺廆嫵抍懱偺僀儞僞乕僱僢僩棙梡傪奣妵揑偐偮栐梾揑偵婰弎偟偰偄傞丅妛栤揑側彂暔偱偼側偔丄僕儍乕僫儕僗僥傿僢僋側懱嵸傪偲偭偰偄偰丄峫嶡傜偟偒傕偺偼杦偳側偄偺偩偗傟偳丄庢傝姼偊偢丄帪愜嶲徠偡傞僀儞僨僢僋僗揑側傕偺偲偟偰朤傜偵抲偄偰偍偔偺傕椙偄偲巚偆丅195暸偐傜偺婰弎偵偁傞丄乽僀儞僞乕僱僢僩傪妶梡偡傞偲丄偁傜備傞廆嫵偺峫偊曽偼傕偲傛傝丄惌帯傗宱嵪丄堛妛側偳偺忣曬偑偡偖偵摼傜傟傞丅偦偺寢壥丄懡曽柺偐傜暔偛偲傪峫偊丄懡條側幮夛栤戣偵廮擃偵懳墳偱偒傞怴偟偄恄妛偑昁梫偩丄偲偄偆偺偱偁傞丅乿偲偄偆暥柆偱弌偰偔傞乽挻恄妛乿偲偄偆奣擮偼丄堜忋弴岶巵偺尵偆乽僴僀僷乕廆嫵乿偵傕捠掙偡傞丅偙偺曈傝偺媍榑偑丄崱屻戝偄偵怺傔傜傟傞傋偒偩傠偆偲丄庢傝姼偊偢巚偆丅乮2000/02/24乯
抾壓愡巕挊亀僇儖僩偐廆嫵偐亁暥弔怴彂怴彂丄1999.11
僼儔儞僗偵偍偗傞乽僇儖僩乿栤戣媦傃偦傟偵懳偡傞惌嶔偺嵼傝曽側偳傪拞怱偵丄崱擔偵偍偗傞僇儖僩栤戣堦斒傪榑偠偰偄傞丅偲丄偙偙傑偱懪偪崬傫偩偩偗偱丄杮彂偺栤戣揰偑弌棃偟偰偟傑偭偰偄傞偙偲偵婥晅偔帠偵側傞丅偦偆丄杮彂偱偼乽僇儖僩乿偲偝傟丄僼儔儞僗偱偼幚偺偲偙傠乽僙僋僩乿偲屇偽傟偰偄傞傕偺偼丄崱擔丄偮傑傝偼乽抧壓揝僒儕儞帠審乿屻偺擔杮崙撪偱乽僇儖僩乿偲屇偽傟偰偄傞傕偺偲偼摓掙摨堦帇偟摼側偄傕偺側偺偱偁傞丅壗偟傠丄幮夛丒暥壔丒楌巎揑暥柆偑椉崙偱偼戝偒偔堎側偭偰偄傞偺偩偐傜丅椉幰偼庢傝姼偊偢偒偭偪傝偲暘偗偰媍榑偡傋偒傕偺偱丄偦偺忋偱帡偰偄傞丄側偄偟摨偠偩丄偲偄偆偺側傜暘偐傞偺偩偗傟偳丄偦偆偄偆怲廳側巔惃偼杦偳尒傜傟側偄丅偦傟偼偝偰偍偒丄杮彂偱偼妋偐偵僼儔儞僗偺廆嫵側偄偟僙僋僩帠忣偵偮偄偰偼帠嵶偐偵弎傋傜傟偰偄傞傛偆側婥偑偡傞偺偩偗傟偳丄擔杮偵偮偄偰偼壜惉傝戝偞偭傁丅偦傕偦傕丄偳偪傜偺丄側偄偟偼偳偙偺崙偺壗偲偄偆廆嫵廤抍側傝壗側傝偺榖側偺偐傛偔暘偐傜側偄婰弎偑昿弌偡傞丅報徾偱傕偺傪岅傞掱婋尟側偙偲偼側偄偺偱偁偭偰丄摿偵丄偙偆偄偆旝柇側栤戣偵娭偟偰偼偦偺偙偲偑懨摉偡傞傛偆偵巚偆丅栜榑丄栤戣偑旝柇偱側偄応崌乮梫偡傞偵丄惌帯惈傪泂傫偱偄側偄応崌丄偲偱傕側傞偩傠偆偐丅乯偱傕傑偢偄丅偳偆傕抾壓偼僼儔儞僗偵偍偄偰儅僕儑儕僥傿偱偁傞僇僩儕僢僋嫵抍偼惓偟偔偰丄乽儅僀僲儕僥傿偱丄斀幮夛揑側廆嫵僌儖乕僾乿乮p.17乯偱偁傞偲偄偆僙僋僩側偄偟僇儖僩偼偍偟側傋偰慡偰娫堘偭偰偄傞丄偲峫偊偰偄傞傜偟偄丅偩偐傜偙偦丄娫堘偭偨傕偺偼偙偺悽偐傜枙徚偡傋偒側偺偱偁傞丄偲嫲傜偔偦偆峫偊傞偐傜乽僇儖僩偺尒暘偗曽乿側偳偲偄偆丄儔儀儕儞僌峴堊傪幚慔偟偰偄傞偲偟偐巚偊側偄婰弎偵懡偔偺暸傪旓傗偟偰偟傑偆偺偩偟丄枩偑堦抦傝崌偄乮摿偵壠懓丅擔暓椉崙偺壠懓峔憿偺嵼傝曽側偄偟曄壔偵娭偡傞幮夛妛揑側尋媶側偳偑嶲徠偝傟傞偲媍榑偼嬌傔偰柺敀偔側偭偨偩傠偆丅偟偐偟丄偙偺挊幰偵偼偦偆偄偆帇揰偼懚嵼偟側偄丅乯偑僙僋僩側偄偟僇儖僩偵擖偭偨応崌偵偼扙戅偝偣側偗傟偽側傜側偄偺偱偦偺曽朄傪帠嵶偐偵偍嫵偊偡傞丄偲偄偆抧揰偵傑偱峴偒偮偄偰偟傑偆丅撉傫偱偄偰丄晐偔側偭偨丅壗偟傠丄巹屄恖偲偟偰偼丄斀幮夛偱偼偁偭偰傕朶椡揑偱偼側偄廤抍側傝巚憐偺懚嵼傪丄僇僂儞僞乕丒僇儖僠儍乕偲偟偰偦偺堄媊傪廩暘偵擣傔偰偄傞偺偩偐傜丅
垻枮棙枦挊亀恖偼側偤廆嫵傪昁梫偲偡傞偺偐亁偪偔傑怴彂丄1999.11
偙傟傕丄撉傫偱偄偰晐偔側傞杮丅乽撉幰偺曽乆偵丄朄慠傗恊阛偺暓嫵傪愰揱偟偨傝丄傑偟偰傗擖怣傪姪傔傞偮傕傝偼偁傝傑偣傫丅乿乮p.193乯偲彂偄偰偼偄傞傕偺偺丄偳偆峫偊偰傕忩搚廆丒忩搚恀廆楃巀偱慡暸偑杽傔恠偔偝傟偰偄傞傛偆偵偟偐撉傔側偄丅杮彂偼寢嬊偺偲偙傠丄乽恖偵偼廆嫵偑昁梫偩丅乿偲偄偆挊幰偺堄尒傪丄傗傫傢傝偲丄乽偱偡丒傑偡乿挷偱岅偭偰偄傞偵夁偓側偄傛偆偵巚傢傟傞丅側偍丄怴廆嫵傪乽憂彞廆嫵乿偲傒側偟偨傝丄乽帺慠廆嫵乿側傞傛偔暘偐傜側偄傕偺傪丄偦傟偵偼慶愭嵳釰傗擭拞峴帠偲偄偭偨傕偺偑娷傑傟傞偲弎傋偮偮丄偦傟偼乽帺慠敪惗揑乿側傕偺偩丄偲偟偰偄傞偗傟偳乮p.8曈傝乯丄乽帺慠敪惗揑乿側廆嫵側傫偰傕偺偼偦傕偦傕懚嵼偡傞偺偩傠偆偐丠乮斀懳偵丄僀僄僗傗暓懮偑柧妋側堄巙傪帩偭偰乽僉儕僗僩嫵乿傗乽暓嫵乿傪憂傝弌偟偨偐偳偆偐偵偮偄偰偼傕偭偲夦偟偄偺偩偗傟偳丅乯扨偵壗帪壗張偱巒傑偭偨偺偐偑偼偭偒傝偟側偄偐傜偲偄偭偰乽帺慠敪惗揑乿偱偁傞丄側偳偲弎傋傞偺偼丄巚峫掆巭偵懠側傜側偄偩傠偆丅梫偼丄恖偑惗偒偰偄偔偵偼巚峫掆巭偑昁梫偩丄偲偄偆儊僞丒儊僢僙乕僕側偺偩傠偆偐丠傗偭傁傝晐偄丅乮2000/02/25乯
媏抮憦挊亀挻忢尰徾偺怱棟妛亅恖偼側偤僆僇儖僩偵傂偐傟傞偺偐亅亁暯杴幮怴彂丄1999.12
擣抦怱棟妛丒恄宱怱棟妛幰偺挊幰偵傛傞乽挻忢尰徾乿側偄偟乽僆僇儖僩乿斸敾偺彂丅斸敾偲偼尵偭偰傕丄挊幰偼UFO偩偺楈帇偩偺挻擻椡偩偺偲偄偭偨挻忢尰徾帺懱偺懚嵼偼擣傔偨忋偱丄偦傟偼乽怱棟揑嶖妎乿乮p.11乯側偺偱偁傝丄偦傟屘偵怱棟妛偺懳徾偲側傝摼傞丄偲偄偆棫応傪偲偭偰偄傞丅擩傠恀偺栤戣偼丄偦傟偵傛傞幚奞偑惗偠偰偄傞偙偲偵偁傞丅傎傏慡柺揑偵巀惉丅乽傎傏乿傪晅偗偨偺偼丄暔惁偄掅椏嬥乮柍椏丄偲偄偆恖偝偊偄傞丅栜榑丄乽暔惁偄掅椏嬥乿偲偄偆昞尰偼巹偺庡娤偵婎偯偄偰偄傞丅傑偁丄悢愮墌丄偲峫偊偰捀偒偨偄丅乯偱埶棅偵墳偊傞乽楈擻幰乿偦偺懠傪壗恖傕抦偭偰偄傞偐傜丅峏偵偼丄幚奞偳偙傠偐丄斵摍偺懚嵼偑抧堟幮夛偦偺傕偺偺懚棫傪巟偊偰偄偨傝偡傞応崌偡傜偁傞丅寢嬊丄掱搙栤戣側傫偩傠偆偐丠傕偆堦偮尵偆偲丄偦偺庤偺尰徾偺拞偵偼乽嶖妎乿偲偄偆傛傝偼丄乽幮夛丒暥壔揑僐儞僥僋僗僩偵傛偭偰宍惉偝傟偨埶棅幰偺悽奅娤傗楈嵃娤偐傜昁慠揑偵弌尰偡傞怱棟尰徾乿丄偲偱傕尵偆傋偒傕偺傕懚嵼偟偰偄傞傛偆偵巚偆丅乽嶖妎乿偲偄偆岅偵偼偳偆偟偰傕僱僈僥傿償側僀儊乕僕偑晅偒傑偲偆偗傟偳丄偁傞尰徾偵偮偄偰偺愢柧尨棟偑強堗乽嬤戙崌棟庡媊乿偵斀偡傞偐傜偲偄偭偰丄柍奦偵斲掕偡傞帠傕側偄偩傠偆丅擣幆偺嵼傝曽偦偺傕偺偑崻杮偐傜堎側偭偰偄傞偺偩丅偦偟偰丄偳偺傛偆側擣幆偺嵼傝曽偑乽惓偟偄乿偺偐側傫偰偄偆偙偲偼丄側偐側偐寛掕偟偵偔偄帠暱側偺偱偁傞丅孞傝曉偡偑丄寢嬊偼掱搙栤戣側偺偐傕抦傟側偄丅偦傟偼偍偄偲偄偰丄偙偺挊幰偼儔僀僞乕偲偟偰傕桳擻偱偁傞丅拞偱傕丄乽楈帇幰乿偲偺懳寛傪昤偄偨戞4丄5復偼惤偵柺敀偐偭偨偟丄乽寣塼宆惈奿敾抐乿偑恖尃栤戣偵宷偑傞乮寣塼宆偵傛傞廇怑嵎暿偑峴傢傟偰偄傞傜偟偄丅妋偐偵桼乆偟偒栤戣偩丅乯丄偲偄偆偙偲傪嫵偊偰偔傟偨戞6丄7復傕嫽枴怺偔撉傫偩丅偲偄偭偰丄偙偺杮偼巹傒偨偄側傕偺乮乽夰媈攈乿偲偱傕尵偄傑偟傚偆偐丅乯偑撉傫偱傕偟傚偆偑側偄傕偺偱丄挻忢尰徾傪捠忢尰徾偲乽嶖妎乿側偄偟偼乽擣幆乿偟偰偄傜偭偟傖傞曽乆偙偦偑撉傓傋偒傕偺偩偲巚偆丅挊幰偺幏昅堄恾傕偦偙偵懚嵼偡傞丅
堜忋弴岶挊亀庒幰偲尰戙廆嫵亅幐傢傟偨嵗昗幉亅亁偪偔傑怴彂丄1999.12
挊幰帺恎偑拞怱偲側偭偰峴偭偰偒偨乽庒幰偺廆嫵堄幆挷嵏乿摍偺嬶懱揑側挷嵏僨乕僞偵婎偯偒丄嬤擭偺乽廆嫵乿奅偵尒傜傟傞曄杄偵偮偄偰偺峫嶡傪峴偭偰偄傞丅堜忋巵偺僗僞儞僗偼揙掙偟偰幮夛妛揑偱偁傞偲巚偆丅僉乕儚乕僪偼乽忣曬壔乿偲乽僌儘乕僶儖壔乿丅偙傟傜偑恑傓拞偱丄乽揱摑廆嫵乿偼偦傟傪巟偊偰偒偨乽嵗昗幉乿偑幐傢傟傞偙偲偵傛偭偰乽晽宨壔乿偡傞丄偲丅偦偆偟偰尰傟傞偺偑乽揱摑廆嫵偲偺抐愨偑尠挊乿偱乽柍崙愋揑側暤埻婥傪昚傢偣偨乿丄乽僴僀僷乕丒僩儔僨傿僔儑僫儖乿側乽廆嫵乿丄棯偟偰乽僴僀僷乕廆嫵乿乮pp.160-1乯偲偄偆偙偲偵側傞丅梋傝偵傕柧夝偵岅傜傟偨榑巪偵丄壗偰暘偐傝傗偡偄傫偩丄偲巚傢偢旼傪懪偮丅偲偙傠偱丄庡偲偟偰乽揱摑廆嫵乿偺挷嵏丒尋媶偵廬帠偟偰偒偨巹偩偐傜偙偦丄妋偐偵乽揱摑廆嫵乿偺乽揱摑乿惈偵偮偄偰偼堦掕偺棷曐偑昁梫偩偲峫偊偰偼偄傞偺偩偗傟偳丄偦傟傜偲庒幰払偑扴偄庤偲側偭偰偄傞嬤擭偺乽廆嫵乿暥壔偲偺僊儍僢僾偵偮偄偰偼丄姶偠傞偲偙傠偑懡偄偺偱偁傞丅偙傟偼壗傕巹偩偗偺偙偲偱偼側偔偰丄搶杒擔杮偵偍偗傞乽揱摑廆嫵乿偺扴偄庤乮偦偺拞偵偼丄尋媶幰傗僕儍乕僫儕僗僩偵傛偭偰乽怴廆嫵乿偲埵抲偯偗傜傟傞嫵抍娭學幰傕偄傞帠傕晅偗壛偊偰偍偔丅乯払偑巹偲偺懳榖偺拞偱帵偟偨丄乽僆僂儉恀棟嫵乿偵傛傞堦楢偺帠審偵懳偡傞斀墳偵傕尠挊偱偁偭偨丅偮傑傝丄乽壗偑壗偩偐偝偭傁傝棟夝弌棃側偄丅乿乽偁傫側傕偺偼廆嫵偱偼側偄丅乿摍乆丅乽揱摑廆嫵乿偑偦傟側傝偵恎偵晅偄偰偍傝丄嬤擭偺庒幰払偺峴摦傕庒姳棟夝弌棃傞悽戙偵懏偡傞巹偼丄傂傚偭偲偟偨傜尋媶幰偲偟偰旕忢偵岾塣側棫応偵偄傞偺偱偼側偄偐側偳偲丄惤偵媗傑傜側偄帠傪弎傋偰丄廔傢傝偵偡傞丅乮2000/02/26乯
斞搰媑惏曇亀岾暉婩婅丂柉懎妛偺朻尟1亁偪偔傑怴彂丄1999.4
埲壓丄摨僔儕乕僘偵娭偡傞婰弎偱偼丄乽僐儔儉乿偵娭偡傞僐儊儞僩偼傂偐偊偨帠傪偍抐傝偟偰偍偔丅
偝偰丄亀柉懎妛偺朻尟亁僔儕乕僘戞1抏偱偁傞杮彂偼丄梋傝椙偄弌棃偲偼尵偊側偄丅傑偢丄戞1復愳懞朚岝榑暥乽僆僩儊偺婅偄亅垽偲惈偺僆僩儊暥壔亅乿偼偙偺杮偺宖偘偰偄傞僥乕儅偐傜偐偗棧傟偰偄傞丅乽僋傿傾丒僗僞僨傿乕僘乿傪栚榑傫偩榑廤偵擖偭偰偄傞傋偒傕偺偩傠偆丅戞3復拞懞彶榑暥乽寢崶婅朷偲恖惗憡択乿傕杮彂偺僥乕儅偲偼奜傟傞丅偙偺榑暥偼杮彂拞嵟埆偱丄掅懎偐偮嫽枴杮埵偺壓傜側偄尵愢偺梾楍偱偁傞丅幏昅幰偼栆徣偟偰梸偟偄偟丄曇幰偼偙傫側傕偺偼幪偰傞傋偒偩偭偨偲巚偆丅偱傕偦傟偼柍棟偐傕抦傟側偄丅17暸偱曇幰偑偙偺復偵偮偄偰弎傋偰偄傞偙偲乮乽忣曬壔幮夛偲側傝惈揑側夝曻偑恑傫偱偄傞偲偼偄偊丄夁嫀偺抝惈宱尡偵偙偩傢傞側偳惈偺偁傝曽偵偼栤戣揰傕懡偄丅乿摍乆丅乯偼丄曇幰偑偙偺壓傜側偄暥復傪恀柺栚偵撉傫偱偟傑偭偨帠傪昞柧偟偰偄傞偐傜丅偟偐偟丄乽乽惈揑側夝曻乿偼峏偵恑傓傋偒偩乿丄偲尵偭偰偄傞偲偟偐巚偊側偄尵愢傪暯婥偱採帵弌棃傞偙偺曇幰偺桬婥偵偼姶暈丄偲偄偆偐曫傟偰偟傑偭偨丅戞4復嬤摗岟峴榑暥偼撪梕偦偺傕偺偑柍拑嬯拑丅乽偲妛夛乿偱栤戣偵偟偰梸偟偄埵丅娛擖堸椏偵乽0Kcal乿偲偁傞偺偼偍偐偟偄丄拑梩偼扽悈壔暔側偺偩偐傜擱傗偣偽擬偑弌傞敜偩丄偙傟偼乽寬峃尪憐乿側偄偟乽怣嬄乿偱偼側偄偺偐丄側偳偲惡崅偵弎傋偰偄傞偗傟偳丄昅幰帺恎婥晅偄偰偄傞捠傝丄儊乕僇乕偼乽恖懱偵媧廂偝傟傞塰梴暘偑杦偳僛儘偩乿丄偲尵偭偰偄傞偵夁偓側偄丅巐幪屲擖偟偨傫偱偟傚偆丅偦傟偩偗偺帠丅戝帠側偺偼丄杮摉偵0Kcal側偺偐偳偆偐偱偼側偔偰丄堸傫偱偄傞恖乆偑偦傟傪婎弨偵偟偰峸擖偟偰偄傞偐偳偆偐丄偲偄偆帠側偺偱偟傚偆丠偦偆昞婰偡傞傛偆偵側偭偨偙偲偱攧傝忋偘偑偳偆曄壔偟偨偺偐偵偮偄偰儊乕僇乕偵栤偄崌傢偣偨傝偟偨偺偩傠偆偐丠傑偨丄拑梩偼敪峺搙偑崅偔側傞偵偮傟偰僇儘儕乕側偄偟擬検偑掅偔側傞丄偲偄偆崻嫆敄庛側帠傪弎傋偰偄傞偗傟偳丄偪傖傫偲幚尡偟偨傫偩傠偆偐丠寢壥偑帵偝傟偰偄側偄偲偙傠傪尒傞偲傗偭偰偄側偄偺偼嫲傜偔娫堘偄偁傞傑偄丅椢拑丄僂乕儘儞拑丄峠拑偲偄偆偙偺暥復偱埖傢傟偰偄傞3庬椶偺拑偺丄尨椏偺拑梩偲嵟廔惗嶻暔偺拑梩偺幙検摉傝擬検傪偒偪傫偲採帵偡傋偒偱偁傞丅偦傕偦傕妛惗傊偺傾儞働乕僩偵偟偨偲偙傠偱丄壗屘偵乽娛堸椏偺愛庢忬嫷乿偺僨乕僞偟偐帵偝傟偰偍傜偢乮p.157乯丄偦傕偦傕杮彂偺庡戣偱偁傞乽0Kcal栤戣乿偲乽傾儖儈僯僂儉娛偲傾儖僣僴僀儅乕昦偺娭學惈塢乆栤戣乿偵偮偄偰偺傾儞働乕僩側傫偰峫偊偨偙偲傕側偐偭偨偺偱偼側偄偐偲偄偆媈偄傪帩偭偰偟傑偆丅偦偆偄偆僨乕僞偙偦偑廳梫偩偲巚偆偺偩偗傟偳側偁丅1997擭偺傾儞働乕僩側偺偱偟傚偆偑側偄偺偐傕抦傟側偄偗傟偳丄嬤擭偼娛堸椏傛傝儁僢僩丒儃僩儖堸椏偺曽偑庡棳偵側偭偰偄傞丅偙傟偵偮偄偰傕挷傋偰梸偟偐偭偨偲偙傠丅乽僨傿僗僞儞僋僔僆儞乿偱偡傛丅傑偝偵丅側偍丄摨復偱偼傾儖儈僯僂儉偲偄偆嬥懏偵偮偄偰尵媦偡傞嵺偵丄乽傾儖儈乿偲昞婰偟偰偄傞偗傟偳丄偙傟偼堦懱壗側傫偩傠偆丅涋嶳媃偰偄傞傫偩傠偆偐丠偙偆偄偆暥復偱偼丄懎岅偼巊偆傋偒偱偼側偄偲巚偆丅僱僢僩忋側傜峔傢側偄偲巚偆偗傟偳丅偍傑偗偵傕偆堦偮丅傾儖僣僴僀儅乕昦偲傾儖儈僯僂儉偺娭學偼壢妛揑偵幚徹偝傟偰偄側偄丄偲偄偆偗傟偳丄壜惉傝夦偟偄偺偼帠幚傜偟偔丄偦偺偙偲偼偙偺暥復拞偱傕偟偭偐傝弎傋傜傟偰偄傞偺偵丄壗偱偦傟偑乽尪憐乿偺堦尵偱曅晅偗傜傟偰偟傑偆偺偩傠偆丠嬤摗偺曽偑辍偐偵乽尪憐乿偵怹偭偰偄傞傛偆偵巚偆偺偩偑乧丅偡側傢偪丄乽扤傕偑寬峃尪憐傪書偄偰偄傞乿丄偲偄偆丅媬偄偼戞2復愇堜尋巑榑暥乽弶寃偲幍屲嶰乿偩偗傟偳丄偙偺挊幰偺亀愴屻偺幮夛曄摦偲恄幮恄摴亁乮戝柧摪丄1998乯傪婛偵撉傫偱偟傑偭偰偄傞幰偵偲偭偰偼阒偐怴枴偵寚偗偨丅戞5復斞搰媑惏榑暥乽晄埨偲尰悽棙塿乿偼杮彂偺僥乕儅偵嵟傕崌抳偟偰偍傝丄榑弎傕偟偭偐傝偟偰偄傞偺偩偗傟偳丄垻枮棙枦偺亀擔杮恖偼側偤柍廆嫵側偺偐亁乮偪偔傑怴彂丄1996乯偵埶懚偟偡夁偓偺姶傪斲傔側偄丅偙傟掱傑偱偵堷梡偝傟傞傋偒廳梫側暥專偲偼巚傢傟側偄丅傑偨丄嵟屻偺曽偼杦偳恖惗榑偲壔偟偰偄偰丄乽柉懎亙妛亜乿揑側婰弎傪戝偒偔堩扙偟偰偄傞傛偆偵巚偆丅偙偺僔儕乕僘偼乽擔杮柉懎妛夛乿偺50廃擭傪婰擮偡傞傕偺偱丄妛弍彂偲偟偰偺懱嵸傪偲傠偆偲偟偰偄傞偼偢側偺偩偐傜丄乽傋偒榑乿偼傗傔傞亙傋偒亜偩傠偆丅栜榑丄乽柉懎妛乿偑偳偆偁傞亙傋偒亜偐偵偮偄偰媍榑偡傞偙偲偼丄廳梫偱偁傞丅乮2000/03/03乯
徏嶈寷嶰曇亀恖惗偺憰忺朄丂柉懎妛偺朻尟2亁偪偔傑怴彂丄1999.6
戞1抏偲偼懪偭偰曄傢偭偰廩幚偟偨撪梕偱偁傞丅偦傟偼丄奺榑暥偑偒偪傫偲乽恖惗偺憰忺朄乿偲偄偆僥乕儅偵崌抳偟偮偮丄峏偵偦偙偐傜堦曕摜傒弌偡巔惃傪尒偣偰偄傞偐傜偩丅戞1復媑惉捈庽榑暥乽偍怓捈偟偲惗傑傟曄傢傝乿偼乽敀乿偲偄偆怓傪拞怱偲偟偰丄恖惗偺奺抜奒偱尰傟傞乽巰偲嵞惗乿偲偄偆儌僥傿乕僼偵偮偄偰峫嶡偡傞丅媨揷搊偑偐偮偰峴偭偰偄偨暘愅偲梋傝曄傢傝偼側偄偗傟偳丄帠椺傕朙晉偵帵偝傟偰偄傞偟丄僐儞僷僋僩偐偮揔愗側婰弎偲側偭偰偄傞丅戞2復嶳揷怲栫榑暥乽憭媀偲嵳抎乿偼惤偵柺敀偐偭偨丅偦傕偦傕丄乽憭媀乿傗乽嵳抎乿傪乽恖惗偺憰忺朄乿偲尒側偡丄偲偄偆帇揰偦偺傕偺偑廳梫偱偁傞丅嶳揷偼偙偺復偱柧帯婜偐傜崱擔偵帄傞枠偺丄庡偲偟偰搶嫗搒壓偱偺憭媀偵偍偗傞乽梎乿偺巊梡偐傜乽嵳抎乿偺巊梡傊偲偄偆曄壔傪僩儗乕僗偟丄峏偵偼乽嵳抎乿偺堄彔揑曄壔偵傕榑媶偟偮偮丄偦偙偵尒傜傟傞偺偼乽巰乿傪乽椃棫偪乿偲尒側偡偙偲偐傜乽懠奅傊偺嵞惗乿偲尒側偡偲偄偆偙偲傊偺曄壔偱偁傞偲寢榑偡傞丅尒帠側暘愅偱偁傞丅戞3復拞懞傂傠巕丒娾杮捠栱榑暥乽徚偊偨傾僋僙僒儕乕乿偼擔杮偵偍偗傞恎懱憰忺偺曄慗傪僩儗乕僗偟丄乽捈愙恎懱偵偮偗傞乿憰恎嬶偑7悽婭屻敿偵巔傪徚偟偨偙偲丄偟偐偟側偑傜乽敮忺傝乿偺傛偆側傕偺偼懚懕偟丄擖杗傗偍帟崟偲偄偭偨傕偺傕懚懕丄側偄偟偼怴偨偵憂弌偝傟偨偙偲傪弎傋丄嵟屻偵嬤戙偵擖偭偰擖杗傗偍帟崟偲偄偭偨恎懱曄岺偺攔彍偑巒傑傝丄惣墷揑暈忺媦傃恎懱憰忺暥壔慡惙傪寎偊偨丄偲偄偆丅偦偟偰丄寢榑晹偱偼榟揷惔堦偺榑弎傪堷偒崌偄偵偟偰丄乽恎懱憰忺乿偺乽堄枴乿偺曄壔偵偮偄偰尵媦偝傟傞偺偩偑乮pp.109-10乯丄挿偔側傞偺偱徣偔丅戞4復栴栰宧堦榑暥乽柉梮偲彈惈亅恎懱壔偝傟傞乽柉庡庡媊乿亅乿偱偼怴妰導偵偍偗傞徍榓30擭戙傪敪抂偲偡傞乽柉梮乿偺棳峴偵娭偟偰丄偦傟偑乽柉庡庡媊乿傪恎懱揑昞尰偲偟偰昞徾偟偮偮寣擏壔偝偣偰偄偭偨僾儘僙僗傪捛偆丅偦偟偰丄妋偐偵偦傟偼乽彈惈偑傛傝奐偐傟偨幮夛揑娭學惈乿傪乽妉摼乿偡傞乮p.139乯偲偄偆堄枴偱偺乽柉庡庡媊乿偺怹摟丄側偄偟乽擔忢偺楯摥乿偐傜偺乽夝曻乿乮p.142乯偵偼栶棫偭偨偐傕抦傟側偄偲偼偄偄側偑傜丄偦偙偵偼乽彈惈傜偟偝乿偺嫮挷偲偄偆僱僈僥傿償側懁柺傕偁偭偨偲弎傋傞丅塻偄丅杮復偼杮彂拞嵟傕巋寖揑側榑峫偱偁偭偨丅戞5復徏嶈寷嶰榑暥乽奨偺忺傝偲婫愡姶乿偱偼搶嫗偺嬧嵗傪庡側帠椺偲偟偰丄宨娤峔惉暔偲偟偰偺乽奨偺憰忺乿傪帠嵶偐偵暘愅偟丄偦傟偑恖乆偺婫愡姶宍惉丄側偄偠帪娫攃埇摍偵傕塭嬁傪梌偊偰偄傞帠傪弎傋傞丅堦偮偩偗偪傚偭偐偄傪擖傟傞偲丄167暸偱娕斅傪乽壆崻娕斅乿乽壓偘娕斅乿乽抲娕斅乿偺嶰偮偵暘椶偟偰偄傞偗傟偳丄尰嵼嵟傕廳梫側偺偼乽幪偰娕斅乿側偺偱偼側偄偐丄偲巚偆丅峀崘庡側偄偟愝抲幰偺埫栙偺庡挘偲偟偰偼乽幪偰乿偰偁傞傫偩偐傜乽抲偒乿偱傕乽壓偘乿偱傕側偄丅姼偊偰乽愝抲応強乿偱尵偊偽乽壓偘娕斅乿偲乽抲偒娕斅乿偺拞姫埵偵埵抲偡傞乽幪偰娕斅乿偼丄奨偺宨娤忋壜惉傝廳梫側偺偱偼側偄偐偲巚偆丅偪側傒偵丄乽堏摦娕斅乿側傫偰偄偆偺傕偁傝傑偡丅堏摦庤抜偼恖娫偩偭偨傝丄帺摦幵偩偭偨傝丄揹幵偩偭偨傝丄旘峴婡偩偭偨傝偲杮摉偵懡條懡嵤偱偡偹丅戞6復幝尨捠榑暥乽恖惗傪嵤傞亅峀崘僐僺乕偵尒傞擔杮恖偺惗奤愝寁亅乿偱偼1992-3擭摉帪偺怴暦峀崘丄嫗惉慄丒嶳庤慄撪偺捿傝峀崘偵娭偟偰丄僞僀僩儖捠傝偺偙偲偑峴傢傟偰偄傞丅忣曬側偄偟尵岅壔偝傟偨僀儊乕僕偵傛傞憰忺丄偲偄偆偺傕妋偐偵廳梫側僥乕儅偱偁偭偰丄惤偵嵶偐偄強傑偱庤偺撏偄偰偄傞彂愋偩偲嵞擣幆偡傞丅偨偩丄杮榑暥偺拞恎偵娭偟偰偼丄乽儊乕僇乕乿偺峀崘偑嵟傕懡偄丄偲偟側偑傜丄壗屘偵乽椃乿乽儗僕儍乕乿乽寢崶幃応乿乽儅僀儂乕儉乿偵偟偐尵媦偟側偐偭偨偺偐偑椙偔暘偐傜側偐偭偨丅乽儊乕僇乕乿偺峀崘偵偼乽恖惗傪嵤傞乿丄偲偄偆梫慺偑側偄偲偱傕尵偆偺偩傠偆偐丠偦傫側敜偼側偄偩傠偆丅偙偙偵偼榑弎偵搒崌偺椙偄傕偺偩偗傪庢傝忋偘傛偆偲偄偆湏堄揑側慖戰偑摥偄偰偄傞傛偆偵巚偆偺偩偑丄偄偐偑偩傠偆丅偦傕偦傕丄偙偆偄偆僒乕償僃僀偼峀崘戙棟揦帺懱偑廩暘偵峴偭偰偄傞帠側偺偱偼丄偲偄偆婥傕偡傞偺偩偑丅柉懎妛偼偦偺忋傪峴偐側偗傟偽側傜側偄偲巚偆丅戝曄側嶌嬈偱偼偁傞偗傟偳丅
乮2000/03/03乯
忢岝揙曇亀梔夦曄壔丂柉懎妛偺朻尟3亁偪偔傑怴彂丄1999.8
戞3抏丅僞僀僩儖偼乽梔夦偲曄壔乿偵偟偨曽偑椙偐偭偨偺偱偼側偄偐偲巚偆丅慜敿偱偼梔夦傗夦堎尰徾傪埖偭偰偄傞傕偺偺丄屻敿偱偼戞2抏亀恖惗偺憰忺朄亁偺懕曇偲峫偊偰傕椙偄傛偆側恖惗偺奺抜奒偱偺堦楢偺乽曄壔乮乽傊傫偘乿偱偼側偔乽傊傫偐乿乯乿偑埖傢傟偰偄傞偐傜偱偁傞丅埲壓丄偞偭偲尒偰偄偔偙偲偵偡傞丅戞1復忢岝揙榑暥乽屢偺偧偒偲屜偺憢亅梔夦偺惓懱傪尒傞曽朄亅乿偼僞僀僩儖捠傝偺撪梕丅梋傝婥偵偟偰偄側偐偭偨懎怣側偺偱報徾偵巆偭偨丅偙傟偩偗攷棗嫮婰揑偵帠椺傪楍嫇偝傟傞偲丄惉傞掱丄偲桴偐偢偵偼偄傜傟側偄丅寢榑偲偟偰偼丄乽屢偺偧偒乿側傝乽屜偺憢乿側傝偲偄偭偨傕偺偑丄乽堎奅偲偄偆傕偆堦偮偺悽奅傪巚峫偺偆偪偵懳抲偝偣丄偦傟偲偺娭學偱尒幐偄偑偪側忬嫷偵堄枴傪偁偨偊丄懳張偟傛偆偲偡傞塩傒乿乮p.52乯偱偁傞丄偲尵偆偙偲偵側傞丅椙偔暘傝傑偟偨丅戞2復愒椾惌怣榑暥乽梔夦偲夦廱乿偼丄庡偲偟偰乽夦廱乿偲偼壗偐丄偲偄偆帇揰偱揨傔傜傟偰偍傝丄亀嶳奀宱亁偐傜亀僑僕儔亁偵帄傞丄偙傟傑偨攷棗嫮婰側婰弎偑揥奐偝傟傞丅乽夦廱乿偲偄偆岅偺帵偡堄枴撪梕偺曄壔偑庤偵嵦傞傛偆偵暘偐傞丄惤偵堊偵側傞榑峫偱偁傞丅戞3復媨揷搊榑暥乽尰戙搒巗偺夦堎亅嫲晐偺憹怋亅乿偼楅栘岝巌偺彫愢亀儕儞僌亁傪柉懎妛偺庤朄傪傕偭偰夝庍偡傞丅偙偙偱偼亀儕儞僌亁偵偍偗傞乽僂傿儖僗乿偲偼傑偝偟偔柉懎妛偑乽働僈儗乿偲屇傫偱偒偨傕偺傪昞徾偡傞偺偱偼側偄偐丄偲偄偆帇揰偑採帵偝傟傞丅椆夝偱偡丅戞4復愳怷攷巌榑暥乽挰偑壔偗傞亅傑偪偯偔傝偺側偐偺柉懎暥壔亅乿偱偼丄墦栰巗傪帠椺偲偟偰丄墦栰偺恖乆帺恎偵傛傞丄亀墦栰暔岅亁偵戙昞偝傟傞乽柉懎帍乿偲尰幚偺僊儍僢僾傪杽傔傞嶌嬈丄媦傃柉懎暥壔偺嵞峔抸嶌嬈偺嵼傝曽偑昤偐傟傞丅帠椺帺懱偼戝曄嫽枴怺偄偺偩偗傟偳丄152暸埲壓偺乽嬤戙壔乿斸敾丄乽揱摑暥壔乿楃巀偲傕撉傔偰偟傑偆婰弎偼偪傚偭偲捀偗側偄丅柉懎妛傕娷傔偰丄妛栤側偳偲偄偆傕偺偼壗偵傕栶偵棫偨側偄曽偑寢嬊偺強悽偺偨傔恖偺偨傔偵側傞偺偱偼側偄偐偲嵟嬤偼偮偔偯偔巚偆丅巹帺恎偼丄妛弍榑暥偵偍偄偰偼壗偺庡挘傕側偄丄嬌椡惌帯惈傪旔偗偨婰弎偵揙偟偨偄偲巚偆丅偦傟偼嬌傔偰崲擄側偙偲偱偼偁傞偺偩偗傟偳丅戞5復怉栰峅巕榑暥乽柤慜偲曄壔乿偱偼乽埆杺偪傖傫乿栤戣傪旂愗傝偵丄柤慜側偄偟柦柤朄傪弰傞柉懎丄峏偵偼柤慜偲崙壠偲偺娭傢傝丄乽晇晈暿惄乿栤戣偵枠尵媦偡傞丅乽柉朄戞750忦乿偵彂偐傟偰偄傞帠暱傪惓妋偵攃埇偟偰偄傞妛惗偑偳偺埵偄傞偺偐丄憗懍傾儞働乕僩傪庢傝偨偔側偭偰偟傑偭偨丅戞6復娾揷廳懃榑暥乽恖偺堦惗乿偼偙傟枠柉懎妛偑懳徾偐傜奜偟偰偒偨偲偄偆師嶰抝傗彈惈偺懚嵼偵岝傪摉偰傛偆偲偡傞丅寢嬊偺強丄乽柉懎偼丄攔彍偺榑棟偺忋偵惉棫偟偰偄偨偺偱偁乿乮p.214乯傝丄偦傟傪懳徾偲偟偰偒偨乽柉懎妛乿傕傑偨丄偦偺榑棟偵堷偭挘傜傟偰偟傑偄丄乽儉儔偱惗傑傟偨恖娫偑偡傋偰堦恖慜偺儉儔恖偲偟偰偺堦惗傪偍偔偭偨偐偺傛偆偵昤偄偰乿乮摨乯棃偰偟傑偭偨偺偩丄偲偄偆偙偲偵側傞丅偨偩丄乽柉懎妛乿偵偍偄偰偼乽恖偺堦惗偵偍偄偰抝惈偲彈惈偲偺娫偵丄偁傞偄偼惉恖偵偍偄偰庒幰偲柡偲偺娫偵丄惈嵎傪擣傔偰棃側偐偭偨丅乿乮p.203乯塢乆丄偲偄偆偺偼夝偣側偄丅悾愳惔巕偺亀庒幰偲柡傪傔偖傞柉懎亁乮枹樢幮丄1972乯摍偵尵媦偟偰偄傞帠偲柕弬偟偰偄側偄偩傠偆偐丠乽惈嵎傪擣傔側偄乿偲偄偆偺偑偳偆偄偆堄枴側偺偐丄傕偆彮偟徻偟偄愢柧偑梸偟偄強偱偁傞丅
娾杮捠栱曇亀妎屽偲惗偒曽丂柉懎妛偺朻尟4亁偪偔傑怴彂丄1999.10
戞4抏丅偙傟偱廔姫偲偄偆帠偵側傞丅僞僀僩儖傪尒偨偩偗偱丄乽惗偒曽乿側偳偲偄偆傕偺傪僥乕儅偵偟偰偟傑偆偲丄偦傟偙偦杦偳慡偰偺柉懎帠徾偵娭傢傞偙偲偵側偭偰偟傑偄丄廂廤偑偮偐側偔側傞偺偱偼側偄偐丄偲巚偆偺偩偗傟偳丄梊憐捠傝丄奺榑暥偺埖偆僥乕儅偵堦娧惈偑姶偠傜傟偢丄嶶枱側報徾傪斲傔側偄丅扐偟丄奺榑暥偺姰惉搙偼崅偔丄孾敪偝傟偨丅戞1復拞杚峅堯榑暥乽夛幮偺潀亅尰戙僒儔儕乕儅儞帠忣亅乿偼拞杚巵偺採彞偡傞乽宱塩恖椶妛乿傪暘愅庤抜偲偟偰丄乽僒儔儕乕儅儞愳桍乿傪戣嵽偵丄強堗乽夛幮恖娫乿偼崱擔偱偼婛偵偦偺楌巎揑巊柦傪廔偊偨偺偱偼側偄偐丄偲榑偠偰偄傞丅偦傟偼暘偐傞偺偩偗傟偳丄25暸偺乽尰戙偺乽忢柉乿偑傕偭傁傜僒儔儕乕儅儞偲側偭偰媣偟偄偙偲偼丄扤偺栚偵傕偁偒傜偐偱偁傞丅乿偲偄偆偺偼梋傝偵傕傑偢偄丅壗偐偲斸敾偺懡偄桍揷殸抝偺採彞偟偨乽忢柉乿奣擮偵傕丄彈惈偼偒偪傫偲擖偭偰偄偨偺偩偑丅昅偑妸偭偨偺偩傠偆偐丠戞2復嶳揷娹巕榑暥乽偆傢偝榖偲嫟摨懱乿偱偼丄乽偆傢偝榖乿傗乽悽娫榖乿偑丄乽悽娫乿側偄偟偼乽嫟摨懱乿偺宍惉偵廳梫側栶妱傪壥偨偟偰偄傞丄偲榑偠傞丅偡側傢偪丄乽乽悽娫榖乿偲偼丄偙偺怢弅帺嵼偺乽悽娫乿偵偁偭偰丄乽懠恖乿偲乽帺屓乿傪埵抲晅偗傞偺偵戝偒側栶妱傪壥偨偡榖偱偁傞偲壖掕偡傞偙偲偵偟偨偄丅乿乮p.68乯偲偄偆偺偼傗傗僩乕僩儘僕僢僋側揰傪彍偗偽奧偟帄尵偱偁傞丅晅偗壛偊傞偲丄偦傕偦傕偙偆偟偨媍榑偼傂傚偭偲偡傞偲僩乕僩儘僕僢僋偵側傜偞傞傪摼側偄偐傕抦傟側偄丅尵岅幮夛妛傗抦幆幮夛妛偺傾億儕傾偱偁傞丅戞3復敧栘摟榑暥乽寢崶偲憡庤乿偼埳摛敧忎搰丄攄杹壠搰丄娯崙偵偍偗傞崶堶宍懺偺帠椺傪堷偒崌偄偵弌偟側偑傜丄乽恊偑寛傔偨憡庤偲乿偺寢崶偑昁偢偟傕乽忢幆乿揑側傕偺偱偼側偔丄乽柉懎幮夛乿偱偼擩傠乽楒垽寢崶乿偺曽偑堦斒揑偱偁偭偨丄偲愢偔丅乽傾僔僀儗崶乿傗乽嵢栤偄崶乿偦偺懠傪乽楒垽寢崶乿偱偁傞偲傑偱尵偄愗偭偰偟傑偭偰椙偄偺偐偳偆偐偑媈栤偱偁傞丅偦傕偦傕丄偙偙偱尵偆乽楒垽乿偲偄偆偺偼壗側偺偩傠偆偐丠偙偺復偵尒傜傟傞傛偆側乽儓僶僀乿偺傛偆側姷峴傪丄嫲傜偔偙偆偟偨帠傪弎傋傞曽乆偑棟憐偲峫偊偰偄傞偺偩傠偆乽嬤戙揑側楒垽乿偲摨堦帇偡傞傛偆側尵愢傪擣傔傞偵偼丄鏢鏞傪妎偊傞丅彈惈偑抝惈偺傕偲傪朘傟傞傛偆側宍幃偑懚嵼偟偰偄側偐偭偨丄偲偄偆旕懳徧惈傪柍帇偟偰偄傞偐傜偩丅戞4復埨堜崃撧旤榑暥乽尰戙彈惈偲儔僀僼僗僞僀儖偺慖戰亅庡晈偲儚乕僉儞僌僂乕儅儞亅乿偼丄僞僀僩儖捠傝偺撪梕丅尰忬攃埇偐傜巒傔丄慿媦揑偵柉懎妛揑側尋媶偑柧傜偐偵偟偰偒偨彈惈偺儔僀僼僒僀僋儖偵娭偡傞婰弎傪峴偭偨屻偵丄乽嬤戙庡晈乿偺抋惗丄峏偵偼崱擔偵偍偗傞峏偵懡條壔偟偨乽尰戙庡晈乿偺抋惗偵枠尵媦偡傞丅搑拞偐傜乽彈惈柉懎妛乿斸敾偲壔偟偰偄偰丄偙傟偼暿偺強偱峴偆偐丄埥偄偼偙偪傜偵媍榑傪峣傞偐偳偪傜偐偵偡傋偒偱偼側偐偭偨偐丄偲傕巚偆偺偩偗傟偳丄幚偼偙偺晹暘偑杮彂拞嵟傕柺敀偐偭偨丅帺屓傪憡懳壔弌棃側偄丄扨側傞帺屓偺懱尡択傪朼偓懕偗傞偩偗偺乽乽懠幰乿晄嵼偺彈惈柉懎妛乿乮p.159乯偺懚嵼偑嬌傔偰乽婏柇乿偩丄偲偄偆偺偼桴偗傞丅偨偩丄帺徧乽彈惈柉懎妛幰乿払偑幏昅偟偰偒偨偦偆偟偨僥僋僗僩孮偼丄偦傟偼偦傟偱暘愅懳徾偲偟偰柺敀偄偲巚偆偺偩偗傟偳丅偦傟偼慬偔偲偟偰丄乽擔杮柉懎妛夛乿斸敾偱偁傞杮榑暥偺宖嵹偵摜傒愗偭偨擔杮柉懎妛夛偺枹棃偼柧傞偄丄偲弎傋偰偍偒偨偄丅戞5復娾杮捠栱榑暥乽乽巰偵応強乿偲妎屽乿偼偙偺僔儕乕僘拞嵟傕夾廰偱偁傝偐偮嵟傕栰怱揑側榑峫偱偁傞丅挊幰偼丄強堗乽帺嶦偺柤強乿偺懚嵼偑擔杮摿桳偱偁傞帠傪弎傋偨忋偱丄壗屘偦傟傜偑晽岝柧沍側応強偱偁傞偺偐丄偲栤偄丄偦偺尨場傪撈摿偺巰惗娤媦傃楈嵃娤偺嵼傝曽偵媮傔傞丅偦傟偼堦尵偱尵偊偽丄擔杮偱偼楈嵃偼巰傫偩応強偵偲偳傑傞偲峫偊傜傟偰偄傞丄偲偄偆帠偵側傞丅彯丄偙偙偱峴傢傟偰偄傞偺偼丄嶐崱偺堦楢偺旘峴婡帠屘偵偍偗傞堚懓偦偺懠偺懳墳偺擔娯斾妑傪拞怱偲偟偨丄搶傾僕傾偺晽悈巚憐丒嵃楫巚憐丒恊懓偵娭偡傞尋媶傪墖梡偟偨媍榑偱偁傝丄乽柉懎妛乿偼乽堦崙柉懎妛乿偐傜乽悽奅柉懎妛乿偵岦偐偆傋偒丄偲偟偨桍揷偺償傿僕儑儞乮廃抦偺捠傝亀柉娫揱彸榑亁拞偱弎傋偰偄傞丅乯偑偙偙偵偍偄偰偦偺執戝側傞堦曕傪摜傒弌偟偰偄傞帠偵側傞偺偐傕抦傟側偄丄偲偄偆偙偲傪弎傋偰丄挿偒偵傢偨傞彂昡傪廔偊傞丅乮2000/03/04丅PS2偺敪攧擔偱偡側丅03/06偵庒姳壛昅丅乯