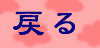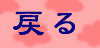出口顯著『臓器は「商品」か ―移植される心―』講談社現代新書、2001.4
-
人類学専攻の出口顯が、贈与論などを踏まえつつ臓器移植について論じる。ここで提示された臓器を代替可能な「商品」(本書で出口が挙げる例によれば、取り替えたり、食べさせたりすることが出来る「アンパンマン」の頭部がそれに当たる。)と考えるか、代替不能な「記号」(同じく、「アンパンマン」で言えば、アンパンマンがアンパンマンであるというアイデンティティを体現ないし表象するもの、即ちアンパンマンの心や、「マント」がそれに当たる。何故「マント」なのかは本書をご覧頂きたい。)と考えるか、という二分法は誠に有効であると思う。私なりに本書の議論を読み解くなら、臓器移植は基本的に前者の考え方に基づいて行なわれているのだが、それでもなお医師を含めた全人類は(やや大げさだけれど。)、様々に異なるとは言え後者的な身体論を大なり小なり持っており、それ故に臓器移植を巡って各社会毎に様々な議論や問題が生じている、ということになる。大切なのは、「商品」・「記号」という便宜上の概念設定に基づいて、身体に関する各社会・各個人毎の主観のありようを、可能な限り客観的に把握し、比較対象すること、ということになるだろうか。人類学という方法論は、そのためには実に有効な手段なのである。(2001/04/27)
Claude Levi-Strauss著、川田順造訳『悲しき熱帯 1・2』中公クラシックス、2001.03・2001.05(1955)
-
ベルギー出身で、20世紀最大と言って良いだろう人類学者C.Levi-Strauss(eにはアクサン付き)による、ノーベル文学賞級の書物の、川田順造による定評のある邦訳版の新書化である。ブラジル旅行(フィールド・ワークではない。)及びそれについて記述を行なうことを通じて著者が巡らした、文化とは、文明とは、そして人類学とは何か、といった思考の軌跡は、今日においても全く新鮮味を失っていない。本書には他に室淳介訳『悲しき南回帰線』(講談社学術文庫)があって、私は大昔にこちらを読んだのだが、ここでは取り敢えず、私自身が社会人類学などというものを専攻しているのには、本書の影響が極めて大であることを述べておく。繰り返しになるけれど、翻訳としては室訳よりもこちらの方が優れているのは、周囲に数多いる人類学専攻の人々が口を揃えて述べていることである。人類学への扉を開くために、或いは人類学の勉強をある程度済ました段階なりにおいて、少なくとも一度は目を通さなければならない文献であることは間違いない。おまけとして、上巻頭にはLevi-Strauss及び川田による新稿が、下巻末には川田作成によるLevi-Strauss年譜も収録されていることを付け加えておく。(2001/05/09、06/02に追記)
高見広春著『バトル・ロワイヤル』太田出版、1999.4
-
特に説明を要しないであろう、つい先だって映画化もなされた大ベストセラー。ようやく古本屋に出回りだしたので早速入手してとっとと読了。大変良く出来たエンターテインメント小説だし、むしろ「健全」とさえ言えるその主張するところには、それなりに共感を覚えた。この小説が持つ、「瀬戸内海の小島における、香川県城岩町立城岩中学校3年B組の生徒同士による、一人だけが生き残れる殺人ゲーム」という設定は一部の人々の間では物議を醸したけれど、そもそもこの殺人ゲーム=「プログラム」は、まかり間違えば今日の日本がそうなっていたかも知れないし、近い将来においてそうなるかも知れない超ファシズム的軍事国家である「大東亜共和国」が、その軍政を保持すべく強制的に行なっている(どう考えても「徴兵制」の暗喩である。)、という設定なのであり、そういう状況下で殺人行為の是非について逡巡する(しない者もいる。)少年少女達をきちんと描いているのだから、ある意味で「道徳的」でさえある。更に言えば、全体的な図式は、主人公を含めた主要登場人物3人が、殺人ゲームなどという「くそ食らえ」なことを少年少女に課すファシズム国家への反抗とその成否なのだから、本作品は前述のように極めて「健全」であるとも言えると思うのだ。逆に言えば、この「健全」さこそが私のような読者には物足りなさを感じさせてしまっていて、正直なところ、もっと不道徳でも良いのでは、などと考えた次第である(これまでに本作品などよりはるかに不道徳かつ反社会的な作品をたくさん読んできたもので…。)。なお、「大東亜共和国」ではロックが反社会的なものとして演奏され聴かれている、という設定だの、いにしえの偽善的TVドラマ『三年B組金八先生』へのあからさまな揶揄(殺人ゲームを取り仕切る人物が「坂持金発」という名前で、その部下には野村、田原、近藤という苗字の者がいる。どうせなら鶴見や杉田も登場させて欲しかった…。)には笑わせられた。(2001/05/15)
四方田犬彦著『日本映画史100年』集英社新書、2000.03
-
日本映画史100年を網羅する、コンパクトではありながら奥深い分析も随所に散りばめられた好著である。1950年以後の日本映画に関しては、私自身も膨大な本数を観てきたということもあって、別段教えられることはなかったのだけれど(ちなみに、若き俊才・青山真治が「青山真二」になっているのはミステイクです。)、さすがに19世紀末の草創期から、1930年代の第1期全盛期辺りについてはそもそもフィルムが現存していないこともあってか、知らないことだらけ、という感じで、誠に参考になった。更には、第5章「植民地・占領地における映画制作」の部分は、これから研究を始めることさえ一瞬考えさせるような(といっても暇がない…。極めて興味深い記述であり、とりわけ117ページから始まる「満映」に関する論述は、先月読んだ山田正紀の『ミステリ・オペラ』との連続性もあって、まさしく「目から鱗」なのであった。(2001/06/11)
上野俊哉・毛利嘉孝著『カルチュラル・スタディーズ入門』ちくま新書、2000.09
-
1970年代にその端緒をなすカルチュラル・スタディーズの、簡にして要を得た入門書である。大まかなことは分かっている積もりなので、斜めに読んでしまったが(ごめんなさい…。)、それでもなお、32ページから始まるフランクフルト学派との関係についての記述はなかなかに興味深いものであった。とりわけここでは、Th.アドルノの『否定弁証法』(木田元訳、作品社、1996)が、カルチュラル・スタディーズや、サバルタン・スタディーズ、あるいはポスト・コロニアリズムといった文脈で読まれている、という指摘があり、これは誠に示唆的なものであった。なお、上記の文献(『否定弁証法』)についてもそうなのだが、本書全般において、文献に関するデータをきちんと載せる姿勢が見られないのは、一つの問題である。日本語で書かれた文献については著者、出版社、刊行年を、日本語以外の言語で書かれた文献については、邦訳がないものは原題、出版社、出版年を、邦訳があるものは翻訳者、出版社、出版年を付けるのが筋というものだろう。これでは、せっかくカルチュラル・スタディーズを学ぼうとして、本書を手に取り、更に理解を深めるべく参照された文献を探そうとする意欲的な人々に対して失礼である。ということで。(2001/06/11)