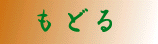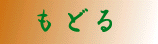宮崎賢太郎著『カクレキリシタン オラショ―魂の通奏低音』長崎新聞社新書、2001.10
-
長崎県内の「カクレキリシタン」を長年調査・研究してきた同著者がまとめた、「カクレキリシタン」について知識を得たい方々には誠に簡にして要を得た入門書であると同時にまた、その網羅的記述手法の採用によって同信仰形態の全体像をつかむには格好の一書である。
-
本書の要点は次の一文に端的に示されている。すなわち、宮崎氏が15年間の調査で得た知見では、「現在のカクレキリシタンはもはや隠れてもいなければキリシタンでもない。日本の伝統的な宗教風土のなかで年月をかけて熟成され、土着の人々の生きた信仰生活のなかに完全に溶け込んだ、典型的な日本の民俗宗教のひとつである」(p.5)ということになるのだそうだ。私見では「日本の伝統的宗教風土」だの「典型的な日本の民俗宗教」というのがそもそも一体何であるのかを更に問いつめる必要があると思うのだけれど、それはおく。ここでは取り敢えず、少なくとも「カクレキリシタン」たちが実践していた信仰が、それら自体が「典型的」なものであるかどうかは別として少なくとも日本国内に存在する民俗宗教には違いない「庚申信仰」だの「念仏信仰」だの「伊勢信仰」等々とそんなに変わりのないものであること、および恐らくはその歴史的・社会的文脈の相違が作用して前者は廃滅寸前という状況を迎えたのであろうことは本書を通して良く理解できたのであった。
-
なお、この著者はたびたび「カクレ」という語を単独で用いているのだが、この語についての説明が存在しない。最低でも、この語が民俗語彙なのか学術用語なのかを明らかにして頂きたかった次第である。以上。(2002/03/11)
伊藤俊治著『バリ島芸術をつくった男 ヴァルター・シュピースの魔術的人生』平凡社新書、2002.01
-
タイトルの通り、20世紀前半における「バリ島芸術」創出に関し多大な影響力を持った写真家にして画家であるドイツ人ヴァルター・シュピース(Walter Spies)の評伝である。もちろん新書ということもあり、その生い立ちやら何やらについての記述はごくごくあっさりしたもので、本書の中心はシュピースがバリ島において何を見、何を聴き、そしてまたバリ島人や欧米の知識人たちといかなる関わり方をしたのか、更には最も重要な点として、今日我々が目にするバリ芸術、端的にはバリ舞踊やバリ絵画と呼ばれるものの創出にどのようにして関与したのか、といった事柄の記述・分析に置かれている。
-
ポスト・コロニアリズムや観光人類学の成果に配慮しつつ、それらの多くが語ってきたようにバリ芸術があくまでも「つくられたもの」であることを明示しつつも、それでもやはりこの著者はそれらの立場にはやや批判的なスタンスをとっており、あくまでもバリ芸術の創出はほとんどバリ島人となってしまったシュピースとバリ島人とのコラボレーションなのだということを主張しているように読めた。そういう言説の正当性・妥当性は置くとしても、取り敢えずは、バリ島文化史研究において必ず言及されてきたシュピースという人物に焦点を当てた、希少な書物として、極めて有用であることは間違いなく、ご一読をお勧めする次第である。
-
なお、一つだけ突っ込みを入れておくけれど、202頁には「観光人類学」その他が「バリの本質」を何一つ語っていない云々と述べられているのだが、そもそも観光人類学その他の研究者はバリの「本質」を捉えようとしているのではなく、バリ島を舞台にして行なわれてきた観光や植民地政策その他の社会事象をその研究対象としているのだから、この物言いは的外れなのである。もう一つ言うと、そもそも本書もまた、「バリの本質」を語ろうとするものではないのだし、それはとても難しいことである、というよりはそういうことを目指すこと自体が最早時代遅れなのだ、ということも述べて終わりにしよう。(2002/03/11)