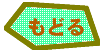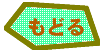中村靖彦著『狂牛病 ―人類への警鐘―』岩波新書、2001.11
-
日本国内でも既に3頭への感染が確認され(2001/12/18現在)、食肉・畜産業界に深刻な打撃を与えている「狂牛病」(より正確には牛海綿状脳症=Bovine Spongiform Encephalopathy。略してBSE。)なる「病気」と、それが引き起こした波紋・騒動をコンパクトにまとめたもの。今のところ、情報が錯綜気味のこの「病気」について、きちんと書かれた本はこれ位しかないので、不安なり興味なりを抱かれた方は、取り敢えず一読されることをお薦めする。これを読むと分かるのだけれど、既に対策が講じられた現在日本国内で売られている牛肉は、まあ一応「安全」なのだな、と思う。しかし、むしろ問題なのは対策が講じられていなかった時期に食べた牛肉、特に内臓なのであって、潜伏期間が2-8年(研究者によってはもっと長いとされる場合もある。)と極めて長いことから、過去においてはそういうものを食べていた私自身もひょっとすると感染している可能性もあるわけで、今後しばらくは恐怖の時間が続くことになってしまった次第である。(2001/12/18)
広井良典著『死生観を問いなおす』ちくま新書、2001.11
-
本の背表紙によれば、「医療や社会保障に関する具体的な政策研究から、時間、ケア等の主題をめぐる科学哲学的な考察まで、幅広い活動を行っている」という同著者なのだけれど、本書の中身は完全に後者。著者は死の問題を「時間論」として捉えるべきであることを提唱しつつ、主として仏教における円環的時間とキリスト教における直線的時間を対比しながら、考察を巡らせる。正直言って、こんな議論をするよりは、どこかの社会における具体的かつ現実的な問題を取り上げて、それについて考察を巡らせる方が遙かに生産的であると考えた次第。すなわち、キリスト教徒(って、そもそもどこの社会の?)が果たして本書にあるような直線的時間観を本当に持っているのかどうかなんてことはきちんと検証してみない限り分からないことなのだし、仏教に至っては、例えば日本に住む大多数が、一応仏教寺院で葬式その他を行なっているのは事実としても、仏典にあるのと同一の時間観を持っているとは考えられない、ということ。大事なのは、事実関係を押さえることなのである。このような、たかだか読書を通じて得た知識で「政策」なんてことをやられた日にはたまらない、とすら思う。あっと、この人、元厚生省の役人なのか。危ない、危ない。以上。(2001/12/24)
速水融著『歴史人口学で見た日本』文春新書、2001.10
-
帯と表紙裏に「コンピュータを駆使して」なんてことが書いてあるけれど、本文を読んでいって、更には著者自身が記した「ハイテク化する研究に、ロー(老?)テクをもって立ち向かわざるをえない状況になっている始末である。」(p.183)という言葉を見れば分かる通り、この人の研究はあくまでも第1次資料の手作業による地道な整理を長年積み上げることによって成し遂げられたもの。それが、誠に凄いものなのである。さよう、速水氏は各地に残る「宗門改帳」の分析を通じて、日本近世の社会のありようを、他の誰もがなし得なかった形で、より具体的な姿で復元することに成功したのである。それは、まさしく「刮目」すべきもの。なお、本書で具体的な形で示されたデータは速水氏が長期にわたって研究を続けてきた諏訪地方と濃尾地方に限られていて、192頁から始まる東北日本型・中央日本型・西南日本型という3類型があるという日本の家族構造についての分析には、それを裏打ちする詳細なデータが記載されていないのが誠に残念なのだが、それは置くとしてももしそういう類型化が可能であるとすれば、人類学や社会学における長年の論争にも終止符が打たれかねないわけで、この人の論文・著作には一渡り当たっておく必要を感じた次第なのであった。(2002/01/22)
島田荘司著『御手洗パロディサイト事件2 パロサイ・ホテル 上・下』南雲堂、2001.09
-
第1弾は既に紹介済みの「御手洗パロサイ・シリーズ」第2弾である。ということは、第1弾は好評だったんですな。物凄くマニアックな作品だと思ったのだが…。それは兎も角、上下巻で計1,000頁強からなる本作は、誠に練りに練られた、しかも多彩な内容を持つ25編の短編からなる、「島田荘司著」となっているからには当然自作自演によるのだろう偽装御手洗潔ものパロディ本格ミステリ作品集である。勿論単なる短編集ではなく、25編の作品には、山形県沖は飛島にあるとあるホテル地下に存在するらしい財宝を発見するためのヒントが隠されている、という設定で、これに関する謎解きが所謂島田荘司テイストを如実に体現する大変結構なものとなっている。個々の作品の出来もそうだけれど、オムニバス形式の長編小説として見た場合にも、前作を遥かに上回る作品、と申し上げておこう。前作同様誤字脱字その他がやたらと目立つのが気になったのだけれど、取り敢えずは是非是非ご一読のほど。(2002/02/08。同年02/18に一部変更。)
内田康夫著『ユタが愛した探偵』徳間書店、2001.12
-
東洋大学出身のミステリ作家による、ご存知「浅見光彦」もの長編推理小説である。実は、私がこの長者番付常連作家の作品を読むのは今回が初めてのことになる。この作品も、この人得意の所謂旅情ミステリであり、その舞台はタイトルからも分かる通り沖縄。そうそう、「ユタ」と言えば、沖縄県などで活動している霊媒ないしはシャマンのことを指すことは周知のことである。まあ、この言葉は蔑視の意を含むとも言われているので、こういう本のタイトルに用いるのは余り好ましいことではないのかもしれないけれど、そもそも蔑視の意を含むようになった「沖縄の近代」というものをもう一度見直すためにはあえてこの語を使うのも一つの戦略なのかも知れないとも思う。
-
話がとんでもない方向にいっているのだが、一つ断っておくと内田康夫氏にはそういう意識はないことは、明白であると考える。何故なら、内田氏は本書において、名探偵・浅見光彦を愛することになるヒロイン・式香桜里(しき・かおり)は、幼少の頃より人の霊が見え、未来を予言する能力に長けていることにより周囲から「ユタさんみたい」と言われているのだが、それを職業にしていないので「ユタではない」、と本文にしっかりと書いているのにも関わらず、タイトルからしてどう見てもこのヒロインを「ユタ」として扱っているわけだ。ちょっと、それはデリカシーに欠けるんじゃないか、ということで、その程度の著者に「沖縄では近代においてそのような宗教職能者は次第に蔑視の対象となり…」といった大変重要なことへの気配りを期待するのが酷、というものなのである、ということを述べたかった次第。
-
なお、「ユタ」の活動その他を含めた沖縄の巫俗に関する記述には、私の見る限りさほど違和感は無いのだが、肝心の謎解きにそのことが絡んでこないのには「これって一体何なの???」、という感じであった。別に舞台は沖縄でなくても良いし、ヒロインは特に「ユタ」のような女性である必要を感じなかった、ということである。以上ボロクソに述べてきたが、まあ、今後内田康夫の作品に言及することは恐らく無いと思うので、ファンの方はご安心くだされ。ということで。(2002/02/26)