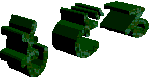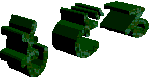長谷川眞理子著『生き物をめぐる4つの「なぜ」』集英社新書、2002.11
-
中学・高校辺りの課題図書にでも指定されると良いだろうな、と思われるような、極めて良質の書物である。もちろん、大学生・大学院生やその他の方々が読んでもためになることは保証する。さて、タイトルにもある4つの「なぜ」とは、N.Tinbergenという動物行動学者が提示したもので、動物のさまざまな行動について「1.その行動が引き起こされている直接の要因は何だろうか、2.その行動は、どんな機能があるから進化したのだろうか、3.その行動は、動物の個体の一生の間に、どのような発達をたどって完成されるのだろうか、4.その行動は、その動物の進化の過程で、その祖先型からどのような道筋をたどって出現してきたのだろうか」(p.5。数字は原文では丸数字)という諸疑問になる。中身を紹介すると、本書では「雄と雌」(要は性分化)、「鳥のさえずり」、「鳥の渡り」、「光る動物」、「親による子の世話」、「角と牙」、「人間の道徳性」と題された各章で、それらの現象・行動・性質について上記四つの角度から、明らかになったこととそうでないことをきちんと区別しつつ説明していく。生物学・動物行動学等が明らかにし、提示してきた興味深い事実・仮説その他を散りばめるとともに、いかにこれらの学問が面白いものであるかを「これでもか」というくらいに感じさせてくれる好著である。繰り返しになるけれど、お薦めです。以上。(2003/04/23)
濱田篤郎著『旅と病の三千年史 旅行医学から見た世界地図』文春新書、2002.11
-
SARSなどというものが中華人民共和国を中心にアウトブレイクしつつあるかに見える状況だけれど(現段階で感染者4,000人弱、死者200人強。)、本書の内容は人が移動すること、つまりは「旅」と、それによって罹患し、あるいは流行する「病」との関係を、アレキサンダー大王の時代から今日に至るまでという長いスパンで見つめ直したもの。書かれていることは私の知らないことばかりで、実に勉強になったのだけれど、それは兎も角、医師である著者の濱田氏が実践しているのは「旅行医学」というもので、要は外国旅行を実施する人々に対し、現地で健康を維持するために行なう予防接種や情報提供、あるいは帰国者の診察等々、ということになるのだろう。どうやら、日本という国ではこの領域が圧倒的に未発達で、それは私自身そんなものがあること自体知らなかったことに端的に現われているのだけれどそれは措くとして、その原因は第2次世界大戦終結までに行なわれていた植民地医学とでも呼ぶべきものの悪しき記憶にあるのだと濱田氏は推測している。さすがにそんなことを言っていられないくらい海外渡航者が増加し、更には悪しき記憶も次第に薄れつつある中で旅行医学はようやく日の目を見つつある、という状況らしいのだが、これは誠に面白い現象である。観光・医療・植民地主義、という3題目は、まさに私の関心事なのであり、ちょっと追求してみようかな、と思い始めた次第である。以上。(2003/04/23)
伊田広行著『シングル化する日本』洋泉社新書、2003.04
-
社会政策論、労働論、家族論をやっている著者による、日本社会論。第1章では晩婚化その他による独身者が増加すると同時に、それとも関連しつつ少子化が進む状況の中で、日本社会は経済的その他の面で破綻しつつあることを国勢調査などのデータから示し、第2章では何故そうなってきたのかを著者なりの視点で分析。続く第3章以降では問題はこれまで日本がとってきた「家族単位」の社会・法制度にあるのであり、これを「個人単位」にするシングル化が必要ではないか、と説く。ふむ、これだと、タイトルは『シングル化すべき日本』ということになりはしないだろうかと思いつつ読了。林道義の「父性と母性の復権論」や山田昌弘の「パラサイト・シングル元凶論」についての批判には共感を覚えたのだが、本書で用いられているデータが著者自身で集めたものではなく公的機関による極めておおざっぱなものであること、更には本書が分析よりも著者が抱く理想的社会像を描こうという、いわば「画に描いた餅」的内容であることは否めず、やや不満足であった次第。更に言えば、参考文献リストが2頁にも満たないというのは、アカデミシャンが執筆した本してはあんまりではないだろうか。著者及び出版社は、「新書だから許される」、などと考えているのかも知れないが、下記のような書物も存在することを忘れないで欲しいものだ。以上。(2003/05のある日にアップしたのだが消滅…。これは第2版。06/02)
酒井邦嘉著『言語の脳科学 脳はどのようにことばを生みだすか』中公新書、2002.07
-
タイトルの通り「言語の脳科学」を実践している著者が、この分野における研究史と最新の研究成果を網羅的に示した、いわば入門書的な位置づけを持つ書物。第56回毎日出版文化賞を受賞しているのだけれど、この分野に興味を持つ一般の方々、あるいはこれから入っていこうとする研究者の卵のような方々には必読書とも言うべき内容で、まことに頷けた次第。膨大な量の参照された文献群もきちんと記載されており、こういう配慮はあってしかるべきだと思うと同時に、酒井氏の勉強量が大変なものだということを実感した。まあ、いっぱしのアカデミシャンならこの位は当然ではあるのだが…。
-
さて、本書に述べられている、近年におけるテクノロジーの発達によってより詳細な測定・分析・議論が可能となった「言語の脳科学」が明らかにしてきたことをほんの少し紹介すると、例えばヒトの脳が他の動物と違うところは、その文法運用能力にあることが分かってきたのだそうだ。更には、「母語」(英語だと、mother tongueとなるこの言葉は、ジェンダー・フリーではない。例えば「第一言語」などとすべきだろう。ちなみに、「母国語」なんていう意味不明な言葉を使っている方々がこの世界には結構いるのだが、そういう人の書いているものは信用するに値しない。)を運用する能力の基礎は本人の意志が定まらない生後数年でほとんど出来上がることが明らかになったそうで、これはN.Chomskyが提唱する「言語運用能力は生得的なものである」という主張が基本的に裏付けられたことを示すのだそうだ。
-
なお、本書で用いられている「言語」という語は、より厳密に言えば「言語運用能力」のことであり、そのように読み替えながら読まないと齟齬を来たしかねないだろう。言葉を理解し、作り出す能力と、そのようにして作り出された言葉が流通することとは別次元の事柄であるからだ。
-
それに関連して、実のところ「言語」という複雑な事柄に関しては、生理学的側面と社会的側面というおおざっぱに分けて二つの側面からアプローチする必要があると思うのだが、本書の記述が基本的に前者に重心を置いていることは「脳科学」という言葉が示す通り。本書では槍玉にあげられている社会言語学その他が行なっているのが言語の社会性についての分析なのだけれど、問題はその間を埋めるにはどうすれば良いのか、ということにもなる。実は、これはとても難しいことで、両者がまっぷたつに分かれて研究が進められているかのような現状が存在する、ということを述べて終わりにしよう。(2003/05/20にアップしたのだが同じく消滅…。これは第2版。06/02)