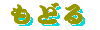
以下、簡単にプロットを紹介したい。ヴェトナム、タイその他をさまようイラストレーター・西島哲郎が、バリ島はクタに滞在中、バイヤーからヘロイン2グラムを購入、これが元で当地の警察に逮捕され、下手をすると極刑を免れない状況に追い込まれる。フランスから帰国した哲郎の妹・カヲルが現地に赴くと、実はこの逮捕、ジャワから派遣された警察署長が「点数稼ぎ」のために仕組んだ囮捜査によるものらしいことが分かり、カヲルとその支援者vs現地警察の法廷闘争が始まる。その結末については本書をお読み頂きたいが、Luc Besson監督のある映画みたいだ、とだけ述べておこう。
なお、上のように記述すると、「バリ島ないしインドネシア共和国ってとんでもないところだ。」、という印象を与えかねないのだが、本書で表面上「悪役」に位置づけられた警察署長はジャワから派遣されたいわば異人なのであり、境界的情況において奸計を働くこの人物、あるいは彼をその成員とするバリ島(これについては一時的な成員だが…。)ないしインドネシア共和国を一概に「悪」と見なすのは、お門違いである。更には、著者が本書後半に登場するスペイン出身のバリ文化心酔者・マヌエルに語らせている通り、バリの社会や文化とは、「バロン・ダンス」に典型的に見られるように、善と悪の境界がはっきりせず、あるいは簡単に入れ替わってしまうという、西欧キリスト教社会などとは隔絶した論理構造を持つ、ということがこの物語の底流にあるメッセージなのだから、もし本書を一読し、「バリ島その他がとんでもないところである、というイメージを読者に与える池澤夏樹はとんでもないやつだ。」などということを考えるようなら、それは決して犯してはならない完全なる誤読なのである。
実のところ、この著者はマヌエルやカヲルの言葉を借りてバリ島を礼賛しつつ、暗部をきちんと描く、そうしておいてそれらが必ずしもその通りではなく、いつでも反転しうるということまで述べる、という離れ業をやってのけているわけで、それ故、本書が第54回毎日出版文化賞を受賞したことについても全く頷けるのである。
ちなみに、この小説の冒頭で、カヲルがパリ(「バリ」と紛らわしいのだが、これは恐らく意図的なものでしょう。)においてあるエキセントリックな神父に河に連れて行かれ、無理矢理(といって、途中からカヲルはこれを全面的に受け入れてしまう。)洗礼を受けさせられる場面があるのだが、これはその後の「哲郎救出作戦談」とはプロット的には全く関わりを持たない。何故このような場面が冒頭に置かれているのか、なのだが、これは先頃物故した遠藤周作へのオマージュなのではないかと、勝手に考えている。そう、どう考えても、この場面は遠藤の最後の長編『深い河』を彷彿とさせるのである。と述べたところで、終わりにする。(2001/05/23)