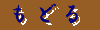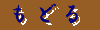貴志祐介著『硝子のハンマー』角川書店、2004.04
-
1996年デビュウの超寡作作家・貴志祐介による実に4年半ぶりの第6長編。作品毎に全く異なるスタイルをとり続けてきた同作家だが、今回は前作『青の炎』(角川文庫、2002(1999))がとった倒叙法を後半の長大な謎解き部分に使用。これを用いた理由は当然謎解き役が語り得ないことを犯人自身に語らせる、ということにあるわけで、これによって所謂「名探偵もの」が陥りやすい、<探偵役が本来分かるはずのないことまで語ってしまう>という難点を避けつつ、動機や犯行法の文字通り「全て」を活写する、という目的を見事な形で果たし得ている。
-
もちろん、著者が初めてとった本格ミステリの王道とも言うべきスタイルを持つ前半部である、12階建てビル最上階の介護業者社長室という「密室」的状況で起きた社長殺しを、防犯コンサルタントでありかつまた本業は泥棒であるらしい謎解き役男性と(この辺も森博嗣的なのだが…)、彼に事件解明を依頼する女性弁護士との推理合戦も、森博嗣を彷彿とさせるかのような、建築技術だの防犯関係についての蘊蓄が目白押しで実に愉しめた。(この作者、相変わらず「これでもか」、というくらい勉強しまくりです。)また、倒叙形式をとる後半部途中で明かされる驚くべき殺害方法に至っては、物理学の基本が理解出来ている私には思わず膝を叩くほどのもので、「この作家、実は理系?」(経済学部卒なわけですが…。ちなみに、理系の人間は経済学部に行くことも結構あります。)などと詰まらないことを考えた次第である。
-
ところで、これまで登場人物に関して連続性のある作品を一つも書いてこなかった同著者だけれど、この作品における謎解き役・榎本径(えのもと・けい)はこれ一冊で終わらせるには余りももったいないキャラクタであることも事実。森博嗣が創り出した保呂草順平と並ぶ泥棒探偵として、シリーズ化を望む読者も多いことだろうけれど、多分それはなされないのだろう。素人作家達によって同人小説みたいなものが大量に書かれることを予想しつつ、この辺で終りにする。(2004/06/25)