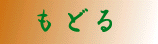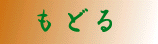Stuart Piggott著 鶴岡真弓訳『ケルトの賢者「ドルイド」 語りつがれる「知」』講談社、2000.01(1968→1993)
-
アナール派による歴史学説の再検討作業やM.Foucaultによる知の考古学・系譜学などが、学問の世界においてある種の一般性を持ち始めていた時期に書かれた英国の考古・歴史学者Stuart Piggottによる「ドゥルイド」論である。(ローマ字表記は‘druid’なんで、発音的にはこう表記した方がよいでしょう。)
-
さて、帯によると「古典的名著」ともされる本書は、一読すればすぐ分かるように、確かにドゥルイドについて学び、考える上での基本文献なのであり、そういうことをしようとする私のような者がまずはここから始めねばならないほどの内容となっている。
-
何しろ、この書物ではギリシャ・ローマ時代から中世末頃に至るまでという長期間にわたって書かれそして描かれ続けた資料内に存在する「ドゥルイド」像、考古学的資料から得られる「ドゥルイド」に関する客観的データとその解釈、更には近代に至ってヨーロッパ人にとっての自己認識・他者認識のよすがとして創り出され・実践されてきた「ドゥルイド」観の全てが、批判的に検討されるのである。
-
シャマニズムとドゥルイディズム(そんなものがあるとして、だけれど…。)の関係を仄めかした最終部分は「なるほど」と思わせるし、これは私自身追求しなければならないテーマとなった次第。やや気になったのは、この著者は近年行なわれている「自称ドゥルイド」達の宗教的実践を揶揄気味に記述しているのだけれど、その人達にはその人達なりの論理なり主張なりがあるはずで、それを「捏造されたイメージ」に基づいた、あるいはそれを利用した愚かな実践、と言ってしまうのはどうかと思う。それはそれで、研究対象としてとても興味深いと思うからだ。以上。(2002/04/13)