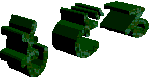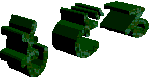長島信弘著『新・競馬の人類学』講談社+α文庫、2002.05(1988)
-
以前岩波新書で出ていた『競馬の人類学』を大幅に増補改訂したいわば決定版の登場。内容はタイトルの通りで、人類学者である長島信弘氏が、もう一つのライフ・ワークである競馬について、熱く、時には極めて冷静に語るというもの。日本国内の競馬に関しては私も結構詳しいつもりなのだが(馬券を買わなくなったのは、20歳になってからかな?)、「本場」英国や、トリニダード・トバゴ、ケニアといった国々における競馬なんてものに関する記述は誠に興味深いものである。そうそう、人類学の基本は様々な社会・文化間の比較検討なわけですが、例えばそれぞれの社会における競馬その他の賭け事の在り方が、その社会の基本構造と何らかの相関関係にあったりしたら、一理論築けてしまうことになる…。ただし、事はさほど単純ではなく、そう簡単にはいかないようです。ということで。(2003/04/10)
森博嗣著『そして二人だけになった Until Death Do Us Part』新潮文庫、2002.12(1999)
-
同著者による所謂犀川&萌絵シリーズやVシリーズとは一線を画す独立した大長編本格ミステリである。とある盲目の天才科学者主導で建造された、本州と四国を結ぶ海峡大橋の橋脚部に作られた「バルブ」と呼ばれる閉鎖空間内で起こる連続殺人事件と、それを巡る顛末が語られる。これまで読んできた限りでは、結局森博嗣が最も得意とするのは、結局マッド・サイエンティストものなのだと思うのだけれど、本作もそれに属することになる。お分かりのようにA.Christieが1939年に書いたAnd Then There Were None(邦題は記載する必要ないですな。)をもじったタイトル、各章冒頭にあるA.Einsteinが著して岩波文庫にも入っている『相対性理論』からの引用、更には全体を通読することでようやく明らかになる大仕掛け等々、誠に読み応え十分な傑作である。なお、天才科学者の思考パターンがやや凡庸かつ陳腐なのが気にかかったが、科学者をやめて実業界・政界入りを果たしたことになっているから、これはこれで良いのだろう。もう一点、バルブ内で用いられているテクノロジに関する記述が微に入り細に入りなものでない、あるいはそもそも大したものではないのもこれまた気になったのだが、本作はこの人のデビュウ作『すべてがFになる』(1996。現在講談社文庫で読めます。)などとはやや性格の異なるミステリなので、これもこれで良いのかも知れない。以上。(2003/04/10)
森博嗣著『月は幽咽のデバイス The Sound Walks When Moon Talks』講談社文庫、2003.03(2000)
-
Vシリーズの第3弾長編。とある屋敷でのパーティ時に、隣室で起こった「密室」と見なしうる状況下での殺人事件とそれにまつわる顛末が描かれる。さて、密室にカギかっこをつけたのは、それを作り出す仕掛けは警察が捜査で早々に発見したはずで、書き手かつ主役にちかい人物である保呂草も「あとがき」的な部分でそのことを暗ににおわせているのだけれど、そうだとすると本書後半の展開ないしこれまた主役級の刑事二人の言動や行動は余りにも不自然ではないか、と考えた次第。いかがなんでしょう?それはともかく、前作あたりから明らかになってきた書き手である保呂草の「本業」を鑑みるに、このシリーズが実はピカレスク・ロマン的色彩を帯びたものなのかな、などと思い始めたところ。文庫化作業が進めば、色々分かってくるのでしょう。
-
以下蛇足。本書で最も面白かったのは、気圧と水の比重等々に関して瀬在丸紅子とその息子が語りあう部分。どんなに長いストローを使っても、この星(我々が住んでいる地球)の表面で水は10mほどまでしか吸い上げられないのだけれど(ここまでは高校の物理で習うはず。)、それでは10mを超える高さを持つ木々はどうやっててっぺんの方まで水を吸い上げているのか、というのがいわば読者への宿題として投げかけられる。私自身は一応一つ二つの答えを思いついたのだけれど、本当のところは調べてみないと分かりませんね。皆さんも考えて、あるいは調べてくだされ。ということで。(2003/04/12)
二階堂黎人著『クロへの長い道』講談社文庫、2003.02(1999)
-
オリジナルの単行本は双葉社刊。それでもって本書は通称「しんちゃん」こと6歳の幼稚園児・渋柿信介を探偵役とする、端的に双葉社の看板コミックである『クレヨンしんちゃん』のパロディと見なせる、ハード・ボイルドのテイストたっぷりな本格ミステリ短篇集である。どの作品も本格ミステリとしてきちんとまとまったものなので、わざわざこんなに突拍子もない設定にしなくても良いのに、と思うのだが、その辺は商売なのだろうか…。要するに「ウケねらい」ないし笑いをとろうとしてのことなのだろうけれど、実のところ、私はあまり「可笑しい」と思いませんでしたよ…。
-
ちなみに、以上3作品の文庫版解説は、どれもこれも誠にひどいものである。それぞれの解説者達が抱く森や二階堂といった作者や個々の作品に登場するキャラクタ達に対する思い入れの深さは分かるのだが、これらの駄文は到底印刷されて流通されるべきものではない。これらは、ただのファン・レターではないか。以上。(2003/04/12)
Ursula K. Le Guin著 小尾芙佐訳『言の葉の樹』ハヤカワ文庫、2002.06(2000)
-
高名な人類学者を両親に持つSF界の女王Le Guinによる、原著は2000年刊行の長編。原著のタイトルはThe Tellingというものなのだが、本書でまさしく「語られる」のは、焚書等々が行なわれ過去の「文化伝統」を抹消し新たな道を歩もうとしている惑星「アカ」に派遣された、地球人女性サティ(意味深な名前です。)がその星の辺境で知ることとなる「語り」(=telling)という文化の貴重さと重さ等々。まあ、要するにこれは、人類学者が各地で見てきたことをそのまま宇宙レヴェルに引き延ばしたものなわけだけれど、これまでの作品ではここまであからさまではなかった人類学への、あるいは両親の仕事への思い入れを、露骨といってよいほどまであからさまに表明ないし吐露してしまったところが面白いといえば面白いと思った次第。なお、本書をよりよく理解するために、植民地政策を含む政治と言語の問題を論じた基本文献であるBenedict R.O’G. Anderson著『言葉と権力―インドネシアの政治文化探求』(中島成久訳、日本エディタースクール出版部、1995)を紹介しておきましょう。併せてお読み下さい。(2003/04/14)
埴原和郎著『日本人の骨とルーツ』角川ソフィア文庫、2002.09(1997)
-
高名かつ誠に尊敬すべき自然人類学者である著者が、日本列島に住む様々な特性を持つ人々の起源について、主として各地で発見されてきた骨や歯といった遺物などから得られたデータに基づいて所謂縄文系・渡来系の混成という「二重構造モデル」を打ち出したのは周知の通り。本書はこの問題を中心に、アイヌ、奥州藤原氏、更にはヒマラヤの雪男にまで及ぶ幅広い問題にまで言及し、自然人類学の面白さを堪能させてくれる内容となっている。基本的に一般向けに書かれたものとはいえ、図表その他が実に充実し、また自然人類学における最新の研究成果がまとめられているのは、講義などでこういう話を扱わざるを得ない私のような者にも大変ありがたいのであった。私事になりますが…。以上。(2003/05/04)
村上龍著『共生虫』講談社文庫、2003.03(2000)
-
谷崎潤一郎賞を受賞した長編の文庫化。ある引きこもりの青年がノート型のパーソナル・コンピュータを母親の援助で導入。インターネットへの接続環境も整え、「ウエハラ」というハンドル・ネームで有名なジャーナリスト・「サカガミヨシコ」が運営する公式サイト内のBBSへの書き込みを行なうところから物語は始まる。これに応じたのはサカガミ本人ではなく「インターバイオ」を名乗る自称研究団体の面々。その構成員達から電子メールにより、自身が体内に宿していると思いこんでいるその引きこもりの原因でもある「虫」のような存在は、人類を絶滅に導くために仕組まれた自然界のプログラムともいうべき「共生虫」であると示唆されたウエハラは、引きこもりを中断し、人類を「絶滅」すべく行動を開始する…。というお話。
-
緊張感に満ちた展開、相変わらずの粘り着くような文体には圧倒されるばかりなのだが、本作品の中心テーマであろう、近年におけるコミュニケーション形式のドラスティックな変容による、自己像・自意識構成のこれまたドラスティックな変容とでもいったものへの洞察は誠に深いものがあると考えた次第である。引きこもり青年は、日常的にはせいぜい母親と、あるいはほんの時折精神科医としか対面状況のコミュニケーションを行なっていない。これが、突如として目の前に圧倒的な質感・量感をもって現われた、非対面状況コミュニケーションを旨とするインターネット内に存在する、基本的にそこにアクセスするものが流し込む膨大な情報群により、自己の引きこもりの「原因」である「虫」の正体を「突き止め」、行動に移る。さよう、ここでは対面状況で得られる情報よりも、非対面状況で得られる情報の方が、ウエハラ青年にとっては「妥当」なものでありかつ、「従うべきもの」ですらある、という誠に屈折した状況が描かれているのである。
-
こういう形で、一応村上龍は今日の日本社会、のみならず一頃言われたような情報過多を遙かに超えてしまったかに見える超情報化社会とでも言うべきこの世界の在り方には「かなりヤバイところがある」と感じ、そしてそれに対し警鐘を鳴らそうとしているのは確かなのだし、本書のフランス語訳を行ない、文庫版解説を書いている Sylvain Cardonnel 氏も日本読者は恐らくそう読むだろう、というようなことを述べているのだが、それは本作品の一面に過ぎないと思う。
-
即ち、オタク達が自らの殻を打ち破り「世界」との戦いを開始するまでを描く『昭和歌謡大全集』(集英社、1994。現在幻冬舎文庫で読めます。)にかなり似ているこの小説は、実のところ自分の所属する家族や学校その他において、その構成員との関係をうまく築くことが出来ずやむを得なく引きこもりとなった青年が、確かに歪んだ形とは言いながら世界への一歩を踏み出す、というある意味で解放・開放の物語として読むことも可能なのである。
-
そうそう、確かにめんどくさくてかつまたくたびれると私自身も思うし、こういうサイトに接続しているあなた自身もそのような感覚を日常抱いているのではないかと邪推する<対面状況でのコミュニケーション>だけれど、原因は様々あると思うがそれには全く適応出来ず全面的に遮断してしまったような人々、あるいは遮断しないと文字通り生きていけない人々が存在するのは紛れもない事実なのである。ネット社会は、そのような方々への福音ともなり得る、とは考えられないだろうか、というのが本作品のやや隠れた一主張なのではないかと、勝手に解釈した次第。勿論著者が、毒にも薬にもなるインターネット万能社会の、毒性の方を強調しているのは、言うまでもないことではある。
-
ちなみに、奥泉光が書いた『浪漫的な行軍の記録』のキータームにもなっている「希望」という言葉が本書の「あとがき」にも登場し、「引きこもりの人は、偽の社会的希望を拒否しているのかも知れない。」(p.302)と述べられているのだけれど、ここで著者が「引きこもり」という一般的にはネガティヴに捉えられがちな現象・行為に対してある種のポジティヴな意味付け・意義付けを行なっているのは間違いのないところである。このことは、著者が小説の本文中においてウエハラなる引きこもり青年を、かなりヤバイ人物であると同時にまたどこか愛すべき部分のある人物として(言ってみれば、『白痴』におけるムイシュキン公爵のように、ですな。)、いわば両義的存在として描写しているように読めてしまうこととも繋がっているものと思う。まあ、どちらかというと「ヤバさ」が強調されているのだが…。
-
というわけで、つらつらと記述してきた如く、一個人においてさえそうなのだから複数の人間が読めばこれまた別のといったような感じで、誠に様々な読み方が可能でありそれが故に毒にも薬にもなりそうな本書は、まさにインターネット上を流れる、それこそ様々な解釈が可能で、かつまた毒にも薬になるような情報群の、極めて気の利いたパロディともなっているようにも思うのだが、それを最後に述べてまとめとしておきたいと思う。以上(それにしても、長いな。ううむ…。それだけインパクトのある作品、ということでしょうな。)。(2003/05/10)
綾辻行人著『どんどん橋、落ちた』講談社文庫、2002.10(1999→2001)
-
「館」シリーズの第7作目を講談社『IN-POCKET』に連載中の著者が、1990年代の主として後半に発表した短編を集めた作品集。全5作のうち4作には所謂「読者への挑戦状」がつくという、本格ミステリの体裁をとる。記述上のフェアネス(本作中では、地の文には嘘はない、殺害者以外の台詞には嘘がないことがその中でも最も重視されている。)を頑なに守りつつ、前の作品を読んでいれば真相に近づきやすくなるという連作がどうしても持ってしまう難点を解消しつつ、という具合に、ミステリ作家の苦労がにじみ出ている作品集で、ある意味例えば「館」シリーズが何で約10年もの間途切れているのかを説明してしまっているかのように読んでしまった。以上。(2003/05/19)
高村薫著『半眼訥訥』文春文庫、2003.02(2000)
-
大阪市生まれの直木賞作家・高村薫による、帯によると「初の雑文集」。1993年から1999年までに主として新聞に掲載された短い文章が大量に収録されている。ハードボイルド、あるいは警察小説というジャンルで、極めて質の高い、そしてまたかなり社会性の強いドラマを生み出してきた著者が語る、今日の世界についての一言一言は、非常に重さがある。1990年代という、情報化、という点では本当に日進月歩だった時代、そしてまた、バブル後、という長い経済的な低迷期にあたる時代についての、観察力と洞察力に富んだ当事者による貴重な記録、にもなっている、と思う。以上。(2003/05/20)
二階堂黎人著『諏訪湖マジック』徳間文庫、2002.10(1999)
-
とある旅行社の課長代理という役職にある、美貌に恵まれてはいるがその実まことに奇矯な人物という設定の「水乃サトル」を探偵役とする作品群の中で、トラベル・ミステリという位置づけが可能な長編第2作である。大宮駅の北にある跨線橋から落とされた轢断死体の謎、八潮の倉庫で見つかった銃殺死体の謎等々を中心に、更にはまた戦国武将・武田信玄の墓を巡る謎に関する蘊蓄を随所に織り交ぜつつ、名探偵・水乃サトルの長野県を中心とした関東甲信越の主として東部における大活躍=謎解きのプロセスを描く。実のところ、同じ作者による「二階堂蘭子」もののようなガチガチの本格ミステリが結局のところ大好きな私には、この作品はやたらと「軽い」ものに感じられたのだが、それはこの作者の狙い通りなのだから仕方がないところ。この辺りの事情は、前作にあたる『軽井沢マジック』(徳間文庫、1997(1995))の「初版本ノベルス後書き」にもしっかりと記述されているのでお読み下さい。なお、本作および前作に共通して言えるのは、どちらの作品もその核心部分は、警察の捜査が進めば間違いなく明らかになってしまう事実が、様々な理由から起きる捜査上の遅延により未だ明らかにならない段階でサトルが謎解きをしてしまう、という結構綱渡り的な構造を持つ、ということである。確かに「軽い」この作品ではあるけれど、その辺の技巧を味わいつつ読了した次第。上に述べた綾辻行人といいこの二階堂といい、ミステリ作家の日々行なっている作業は実に大変なものなのです…。以上。(2003/05/24)