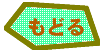本作が『幻惑の…』と一緒に文庫化されたのは、前にも述べた通り同著が前著の偶数章に当たるためである。両者が独立した作品であることも既に述べた通り。付け加えると、両者の独立具合は著しいもので、前作が奇術師殺しとその死体消失を巡る大掛かりなトリックを駆使した本格ミステリの体裁を持つものであるのに対し、本作は誘拐及び密室情況での人間消失を巡る本格ミステリというよりは寧ろサイコ・ドラマとでも言うべきものなっている。いや、それどころではなく、本書とこれに続く『今はもうない』(次項参照)は一連の犀川・萌絵シリーズの中でも異彩を放っている。これについては後述しよう。
最後になるが、本書のラストは全くの〈偶然〉の出来事なのだけれど、奇蹟の〈奇〉を各章のタイトルに冠した前作が、基本的に犯人の意志通りに全てのことが運ぶ言ってみれば必然性をその底流に持つとすれば、偶然の〈偶〉を各章のタイトルに冠した本作において、一連の出来事は基本的に偶然性・偶発性・非意図性を孕みながら展開する。奇蹟と偶然はどちらが起きやすいか、と言えばその答えは後者なのであって、この辺りの捻れ具合が個人的には面白かった。
それは兎も角、ここではそうした人々を「エキセントリックな」と解してしまうメンタリティをこそ問題にしなければならないだろう(それは私及び前記の人々を明らかにエキセントリックな人物として描いている森氏にも共通するものだ。)。それは、本書では、〈正常〉と〈異常〉の境界を巡る思索がなされているからだ。美少女フィギュア・マニアから(とは言え、完成品を買ってくる人達から、ガレージ・キットの原盤を自分で起こす人達まで、と極めて幅広い。)、マーダー・プロップ・コンストラクション・キット・マニア(普通はこんなものがあること自体を知らない。簡単に言えば死体の模型です。これも前者同様、多様なのでしょう。)を経て、更には実際の死体を切り刻むに至る系列のどこに、その線引きを行ない得るのか。このことと、そもそも人間の個体としての境界線はどこにあるのか、という極めて深遠なテーマとが交互に問われることにより、本作に単なるミステリを超えた意味付けを与えている。勿論、死体切断を巡ってなされる犀川・萌絵による思考・対話に、京極夏彦作品の影響を見るのは私一人ではないだろう。
尚、本作において殆どコスプレ・ドールと化している西之園萌絵だが、本書には愛知県警本部のサーヴァ内に秘密裏に設けられた西之園萌絵ファンクラブのホームページ云々、という記述がある(138頁)。さすがに愛知県警本部にはないとしても、多分既に似たようなものは作られているのだろうと思う。「西之園萌絵」で検索すれば出てきそうだが、怖いので止めておく。考えてみれば、この欄も引っかかるんだろうけれど…。
もう一つ気になったのは、真賀田四季が何故に萌絵や犀川に興味を抱き、一連の事件を演出してみせなければならないのかが、私にも「よく、わからない」(584頁)ということ。但し、これは今後の作品で少しずつ明らかにされていくのかも知れない。期待しよう。
以下は蛇足。既に『まどろみ消去』の中の一編においてRPGへの言及を行なっていた、否、それどころかRPGを偽装した作品を書いていた同著者であるが、本作でも「ナノクラフト社」が開発した『クライテリオン』なるRPGが事件の鍵を握る重要なアイテムとして登場する。この、作品内RPGである『クライテリオン』のエンディングは、〈僧侶から一片のパンを与えられる〉、という誠にあっけないもの。(これは、例えば『ドラゴン・クエスト7』において、艱難辛苦の後に主人公に与えられるのが結局2片の「アンチョビ・サンド」のみ、という事実に通底する。DQ7の原作者・堀井雄二は絶対に本書を意識している。気のせいかな?)本作を読み終えるにあたり、我々は著者の誘導に従って、〈何故にこれ迄このシリーズを読んできたのか?〉という懐疑を行なうことになるのだが(ならない人もいるんだろうが…。)、結局のところ50-60時間を費やして得られるのは『クライテリオン』のエンディングのように、いやそれ以上にあっけないものかも知れない〈読書をした〉、という記憶のみ。それでいいのだ。人は記憶によってのみ生きるのだから。(2000/12/25)