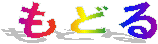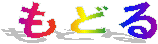鶴岡真弓著『ケルト美術』ちくま学芸文庫、2001.12(1995)
-
本書の元になったのは1995年刊の『ケルト美術への招待』(ちくま新書)。ヨーロッパ美術の隠れた、そして再発見されたその一つの源流とも言うべきケルト美術の極めて優れた紹介本であったのが前著だけれど、今回は図版を中心として大幅な増補がなされている。特に、巻末のブックガイドや博物館ガイドは、元本を読んでしまっていた私にも誠にありがたいものなのであった。文庫にしては1,400円と値は張るけれど、購入する価値は充分にあると思う。以上、簡単ながら。(2002/03/03)
四方田犬彦著『われらが<他者>なる韓国』平凡社ライブラリー、2000.6(1987)
-
基本的には映画史家なはずの四方田(よもた)犬彦による、日本国籍を持つ同氏にとっての隣人にしてそれこそ「他者」なる「韓国」をテーマにしたエッセイ集である。この人の名前にそもそも「犬」が入っていること自体面白いのだけれど(韓国の人々が犬を食するのは良く知られたことです。欧米の動物愛護団体その他がどう考えてもマンネリなイチャモンを2002年FIFAワールドカップ日韓共催にあわせて「勧告」したのも、これまた良く知られたことです。)、それはおくとして、1979年から1980年という、韓国史上でも大変重要な時期に外国人講師として同地に滞在した経験を縦横無尽に活かしたテクスト群は、誠に興味深いもの。政治・経済情勢から食文化・演劇・文学・映画・コミックにまで及ぶ、本書に記された膨大な情報の量には圧倒されること請け合いである。<他者>理解ほど難しいことはない、とつくづく実感させられることの多い今日この頃なのだけれど、取り敢えずは2時間足らずで行ける同国について、少しでも「理解」を深めようと考える皆様には一読をお勧めしたい書物である、と述べて終わりにしよう。(2002/03/05)
山田正紀著『ナース』ハルキ・ホラー文庫、2000.08
-
本欄でもおなじみのエンターテインメント作家、山田正紀による書き下ろしSFホラー長編である。中身は「これでもかっ!!!」というほど徹底的なまでにB級。ジャンボジェット機墜落現場に向かった日赤看護婦7人が、現地で遭遇したのは「動き回る死体」達。本小説では、その死体達と看護婦達の戦闘を、やや破綻気味の文章でつづっていく。何だか物凄く手抜きな感じの小説で、ややガッカリした次第。実のところあまりお勧めしないが、発行部数が極端に少なそうなので、将来レア・アイテムとして高値がつくかも知れないことだけは述べておこう。以上。(2002/03/18)
二階堂黎人著『奇跡島の不思議』角川文庫、2001.08(1996)
-
既に紹介した『人狼城の恐怖』(講談社文庫。以下、発行年省略。どちらも極めてシンプルなタイトルなのだけれど、これが案外新鮮にさえ思えるのが不思議である。)と比べてもさほど遜色のない誠に素晴らしい作品だと思うこの小説は、680頁に及ぶ大長編本格「フー・ダニット(犯人当て)」ミステリである。舞台は茨城県近海の孤島=「奇跡島」。主要な登場人物群である大学の美術サークルの面々その他は、同島に立つ廃館に残された膨大な美術品の鑑定を依頼され、その作業を進めるうちに連続殺人事件に遭遇。当然のことながら本作品では、その一部始終が描かれるとともに、終盤では真犯人を巡って純然たる「犯人当て」が展開される。大学生の時分に「西洋美術史」なんていう授業を取っていた(けど全然出席しなかった…。)私にとっては懐かしいとさえ言える西洋美術史の蘊蓄をふんだんにまぶしたこの作品だけれど(この点、解説で我孫子武丸が述べている通り、本書が麻耶雄嵩の『夏と冬の奏鳴曲(ソナタ) PARZIVAL』(講談社文庫)に一脈通じるものがあるのは確かなことである。)、そういう意味でも頭の体操その他にはもってこいなのであった。以上。(2002/03/22)
山口雅也著『續・日本殺人事件』角川文庫、2000.05(1997)
-
既に紹介した『日本殺人事件』(角川文庫、1998(1994))の続編を文庫化したものである。本書は、前作に述べられた一連の経緯から探偵事務所を開業した、日本語に堪能な在日アメリカ人「トウキョー・サム」を主役とする二つの中編からなるのだけれど、第1編は「スモウ・レスラー」、第2編は「ゼン(禅)」の僧侶を主要な登場人物に据える。このことと、この本の初出年が1997年ということを鑑みるに、どちらの中編も基本的に本書5頁にさりげなく言及されている京極夏彦による、それぞれ『どすこい(仮)』(集英社、2000。連載初出は1996年から。)、『鉄鼠の檻』(講談社ノベルス、1996年)のパロディなのだろうと思う。まあ、それを超えて、第1編は本格ミステリ、第2編はメタ・ミステリとして、極めて良質かつ楽しめる内容であったことを述べておきたい。ところで、この続きは、書かれないのだろうか?以上。(2002/03/22)
森博嗣著『地球儀のスライス A SLICE OF TERRESTRIAL GLOBE』講談社文庫、2002.03(1999)
-
「創平&萌絵」第1次シリーズ終了後に刊行の短編集。「創平&萌絵」ものは2編のみ、この後に続く「V」シリーズの登場人物がいずれかの作品に登場しているらしきことが表紙裏に仄めかされているのだが、そっちを全然読んでいないのどの作品なんだか全く不明。大部分の作品において叙述トリックが多用されており、密室ものは基本的に皆無(一件そう読める「素敵な日記」も、比重の大きさとしては叙述トリックものである。)。本書に収められた多種多様な形態を持つ作品群は、ミステリなのかさえ判然としない、はっきり言ってファンタジィとしか読めない作品も含め、この著者の構築しうる作品世界の幅広さを物語っているのだが、結局のところ私にとって一番面白かったのは理系師弟コンビの「創平&萌絵」ものである「石塔の屋根飾り」および「マン島の蒸気鉄道」の2編であった。まあ、後者については謎解きが簡単すぎるんで拍子抜けなのだが、マン島を訪れて、実際にそのまだなくなっていないんだろうウルトラ・マニアックな鉄道を見てみたくなった次第。それは置くとして、「石塔の屋根飾り」という、たぶん名古屋大の教官なのだろう小寺武久氏の講義で森氏が耳にした「研究上の実話」を元にしたそうな「建築社会学」的考察を含んだ小品は、誠に興味深いものなのであった。(2002/04/04)
John Darnton著 嶋田洋一訳『ネアンデルタール』ソニー・マガジンズ文庫、2000.04(1996。原著も同年みたい。)
-
絶滅したはずのホモ・サピエンス・ネアンデルタレンシスが、ユーラシア大陸中央の人跡未踏地帯に生き残っていた、という設定で書かれたとても良く出来たエンターテインメント小説である。当然この本の元ネタは、こういう疑似科学的なもの大好きのArthur Conan Doyleが書いた古典『失われた世界』(現時点では創元SF文庫から出てます。)なのだけれど、同著者は本書を、最近の考古学・社会生物学などの研究成果をきちんと活かしつつ、なかなか読み応えのある作品に仕上げている。中でも、後半に描かれるような、それぞれが独自の文化・社会構造を築き上げたネアンデルタール人の平和的集団対戦闘的集団の対立に、本来外部の存在であるホモ・サピエンス・サピエンス=ヒトが、何らかの形でコミットして良いのか、という問題については、社会人類学を専攻する私にも色々と考えさせられた次第。まあ、この点は実のところかなり安易に処理されてしまい、主人公達は上記の対立に堂々とコミットしてしまうのだけれど、自分の命がかかっている場合はやむを得ないのかも知れない。そのこと自体、ある意味でダーウィニズム的行為なのだ、ということを一応述べて、終わりにする。(2002/04/09)
Edward W. Said著 大橋洋一訳『知識人とは何か』平凡社ライブラリー、1998.03(1993→1995)
-
少々古い本だけれど、パレスティナ問題が拗(こじ)れに拗れている現状において本書を紹介することは意義あることと考えてここにその概要を簡単に記す。『オリエンタリズム』、『文化と帝国主義』等々の著者であるこのパレスティナ生まれの文学理論家が、1993年にBBCで放映された、著者自身によってなされたリース講演に基づくテクストの中で行なっているのは、まず第一には専門分化が進み社会一般にコミットすることの無くなった、あるいはほとんど無自覚に、または半ば自覚的に覇権主義国家その他の片棒を担いでしまっている現代の「知識人」像を描き出すこと、そしてまた第二にはその本来あるべき姿は、基本的にアウトサイダーでありアマチュアである、更には自己の置かれた文脈を把握しつつ自らが描くこの世界の行く末に関するイメージやこの世界の「真実」を「表象・代弁」(=represent)する存在なのだ、という提言である。その実践は誠に困難だと、ため息が出てしまうのだが、以後鋭意努力を重ねねばなるまい、と気持ちを新たにしつつ、明日からは西ヨーロッパに赴く私なのであった。以上。(2002/04/18)
鈴木忠志・中村雄二郎『劇的言語【増補版】』朝日文庫、1999.02(1976→1977)
-
これもやや古い本である。本書は、舞台芸術の演出家・鈴木忠志と、哲学者・中村雄二郎による1976年初出の対談に、1998年に行なわれた対談「『劇的言語』の現在」を加えた増補版である。「劇的言語」とは、当然「詩的言語」へのアンチ・テーゼないし補完的概念として持ち出されたものなのだけれど、本書では言葉と身体行為(=演技)の関係が議論の中心となり、例えば能・歌舞伎が持っていたはずの身体性・全体性等々の掘り起こしとその復権が、言語主導となることにより本来「演劇」が発揮すべき力を失ったかに見える新劇などを含む近代演劇を再生させるよすがになるのではないか、といった事柄が徹底討議される。それはそれとして、増補された部分に書かれた、連合赤軍によるテロは文系的で近代的、オウム真理教によるテロは理系的で現代的、という図式は、私見では余りにも「粗雑」である。ここでは例えば19世紀後半のヨーロッパでは既に、発明後さほど時間を経ておらずそれなりに作るのが大変だったはずのダイナマイトによる爆破テロが頻発していたことは周知の事柄なのだ、とのみ述べておこう。以上。(2002/04/18)
服部まゆみ著『一八八八 切り裂きジャック』角川文庫、2002.03(1996)
-
1996年に東京創元社から単行本で出ていた、服部まゆみの恐らく代表作となるであろう大著の文庫版である。総ページ約770。時はタイトルの通り1888年。大英帝国を震撼させた謎の殺人鬼「切り裂きジャック」。その正体を、美青年探偵・鷹原惟光と、医学生・柏木薫が追う。狂気と喧騒に満ちたロンドンを再現し、「エレファント・マン」ことジョーゼフ・ケアリー・メリックやヴァージニア・ウルフといった当時ロンドンにいた数々の著名人を登場させ、未解決の事件を再構成してみせた筆力は何ともすさまじいものだと思う。古典として、読み継がれるべき作品かも知れない。それほどのパワーを持った作品である。以上。(2002/05/18)
木村敏著『偶然性の精神病理』岩波現代文庫、2000.02(1994)
-
数多くの著作を持つ精神医・木村敏による、哲学的論集である。本書において著者は、分裂病(今後は「統合失調症」と呼ばれることになりそう。)や離人症という症例を通して、生物個体としては「偶然」の存在(この言葉も吟味が必要だけれど、それはおいておく。)である人間が、固有名や主体性や、あるいは時間の流れの中にいる私意識とでもいうようなものを持つ社会的個人性という、いわば存在の「必然」性を仮構しつつ生きている、ということを暴き出しつつ、偶然性と必然性の「あいだ」について、深い洞察を行なっている。あくまでも症例という具体的事象の観察から発して深い思弁へと向かうような、同著者が本書で実践している「現象学」的方法論とは、例えば基本的には同じような出発点を持つ人類学や社会学という学問的実践においても参考にすべき極めて示唆的なものではないか、と考えた次第。以上。(2002/06/02)