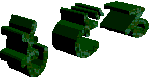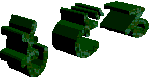山田正紀著『風水火那子の冒険』カッパ・ノベルス、2003.04
-
新聞の配達および販売拡張員にして名探偵である「風水火那子」を主人公とする、『GIALLO』誌に掲載された中編4本を収めた本格ミステリ集。ここに収録されたこの天才作家の中編群は(他の著作における短編でさえそうなのだが…。)、普通の作家だったら長編にしてしまうだろう程の中身を持つものばかり。一つ一つの作品に、アリバイ・トリック、密室トリック、動機を巡る謎等々、本格ミステリの基本要素をきっちりと織り込みつつ、それでいて舞台設定や展開においてはただ単に「風水火那子が謎解きをする」という一点のみしか共通点を持たないような、極めてヴァラエティ豊かな作品集にしてしまっているところが何とも素晴らしいと思う。取り敢えずのご一読をお薦めする。ちなみに、最後の作品「極東メリー」は、日本海沿岸に出没する某国の不審船を扱っているのだが、何とも時宜にかなう内容である。作品紹介からははずれるけれど、一向に進展がみられず、国際問題だったはずの事柄がいつの間にか国内問題になってしまった観さえある所謂「拉致問題」の早期解決を強く望む、ということを述べておこう。(2003/06/02)
田辺繁治著『生き方の人類学 実践とは何か』講談社現代新書、2003.03
-
社会人類学・文化人類学的なそれこそ「実践」を、新書というスタイルを取るが故の、これまたそれこそ「実践」上の制約を受けつつも最良の形で体現するような内容を持つ極めて優れた書物である。
-
本書のテーマはサブ・タイトルにもなっている「実践」にまつわる諸問題。この本において著者は、古代ギリシャから今日まで様々に論じられてきたこの言葉ないし概念が意味する事柄につき、前半では理論的に、後半では自らがタイ国で行なったフィールド・ワークに基づいた具体的記述と分析を通して考察する。
-
著者が念頭に置いているのは、ほんの先頃亡くなったフランス共和国の社会学者P.Bourdieuの実践概念と、それを更に一歩進めて、実践と、それを生みだしまたそれによって創られるという二つの側面を持つ、P.Bourdieuが「ハビトゥス」(「身体化された習慣」位の意味に理解しておけば取り敢えず良ろしいかと思います。)という言葉で表現したものの相互関係を、それらの表出と構築の現場において観察・分析すべきことを説きかつ実行したJ.LaveおよびE.Wengerの研究。それらを基に、タイ国における「霊媒カルト」、「エイズ自助グループ」を具体的事例として分析する、というような具合に、理論と事例研究が見事にかみ合った、人類学の最先端を手っ取り早くつかもうという方にも、あるいは私のような研究者にも誠に示唆的な書物である。
-
なお、詳細な参考文献リストに加え、索引までついているところが素晴らしい。少なくとも、人類学やその周辺分野に興味を持つ方にとって、これは<必読書>です。以上。(2003/06/21)
松島まり乃著『アイルランド民話紀行 ―語り継がれる妖精たち』集英社新書、2002.06
-
ジャーナリストの松島まり乃氏が書き下ろしたタイトル通りの内容を持つ好著である。アイルランド共和国では、どうやら元々「物語」を語り紡ぐことを是とする「伝統」のようなものがあって、それは一旦TVその他の影響で壊れそうになったのだけれど、かといって簡単に壊れ去るものでもなく、あるいはTVなどの「外圧」が逆に作用する形で物語サークルやプロの物語師などを生みだし、今日は物語全盛、といった状況を迎えているらしい。本書ではそういうことを、実際に行なわれている物語サークルの活動、プロフェッショナルな物語師や著名なミュージシャン達の語るそれこそ「物語」などを通して描き出す、ということになる。事例は具体的、著者の目的意識も明快、筆致も読みやすくかつ読者の興味を一時も失せさせることがない、という優れた「民話紀行」となっている。是非ともご一読の程。
- なお、本書の中には「古代、ケルト社会は母権社会であり、女性は自由に社会参加をしていた。」(p.125)という文章があるのだが、今日のアカデミズム内部では「母権社会」なり「母権制」の存在を疑問視する意見が大多数を占める。それは端的に、証拠がないからであるのだけれど、というわけで、もし古代ケルト社会が母権社会であったことが証明できたら、大変なことなのである。以上。(2003/07/21)
京極夏彦著『陰摩羅鬼の瑕(おんもらきのきず)』講談社ノベルス、2003.08
-
第6弾の『塗仏の宴(ぬりぼとけのうたげ)』が出たのが1998年なので、待たされること早5年。この度ようやく刊行の運びとなった「京極堂」シリーズの書き下ろし(部分的に既出)第7弾長編である。第6弾まで、ヴォリューム及びプロットの複雑さ・混迷さを漸次増大・増長させてきたこの著者であるけれど、今回は750ページという長くもなく短くもないヴォリュームの(それでも長いか…。)、これまでの作品に比べかなり分かり易い、いわば直線的なプロット構成を持つ作品に仕上がっている。
-
思うに、様々な宗教現象、宗教思想などに関しての衒学的レヴェルを超えたほとんど学術的次元(この人に全然追いついていない研究者は多々おりますが…。)での記述を作品の中心に据えてきたこのシリーズだけれど、この作品はそれを継承しつつ、同じ著者による『嗤(わら)う伊右衛門』(中央公論社、1997)や『覘(のぞ)き小平次』(中央公論社、2002.09)といった時代小説と呼び得る作品群が持つ「枠物語」的構成を持ち込んで練り上げた新趣向の作品である、と考える。実のところ、一読して物足りなさを感じる読者も多々ありそうなのだが、私個人としては小説としての完成度という点において、同シリーズの中でも傑出してはいないながらもさほど浮いた存在ではないようにも思う次第。誠に曖昧な表現だが、そういう作品である。
-
さて、本書の舞台は長野県は白樺湖畔に位置する「由良伯爵邸」。過去に4人の花嫁が婚礼の翌朝に殺害されてきた、という背景の元、由良邸では現当主・昂允(こういん)の、5回目の婚礼が行なわれようとしている、という舞台設定。そんな舞台設定の元、既に述べた通りの極めて明快なプロットにより、花嫁の護衛を依頼された探偵・榎木津礼二郎とそのお伴をする小説家・関口巽、あるいはかつてこの事件を担当した元刑事・伊庭銀四郎、更には真打ちたる古書肆・中禅寺秋彦等の活躍によって「驚愕」の真相が明らかにされることになる。
-
何故「驚愕」に括弧が付くのかは、本書を一通り読んでいただければお分かりになるかと思う。実際問題、本書で描かれる事件の真犯人は、同様のテーマを京極氏に先駆けて扱った笠井潔の『哲学者の密室』(光文社、1992)を彷彿とさせるような、存在と存在者、そして死と向かい合う存在等々を巡る対話が描かれる21ページまででほぼ分かってしまうのだし、最大の謎として語られていくその動機に関しても、由良邸内に置かれた大量の鳥類剥製についての描写だの、由良昂允が基本的に50歳を超えるに至るまで「引きこもり」状態に置かれていたというような事実から「何となく」推察されてしまう。『姑獲鳥の夏』(講談社ノベルス、1994)から始まる同シリーズが、特にその第2弾である『魍魎の匣』(講談社ノベルス、1995)において顕著な如く、「普通とは違う」論理ないし世界に生きる者の「犯罪」を描いてきたのは周知のことであるけれど、この作品でもそれは踏襲される。どこかしらでこれまでの作品とは一線を画するようなねじれなりひねりなりが入るのかな、と思っていたのだが、それは無い。この辺り、やや肩透かしの観があったことは否めない。
-
とは言え、本書で語られる儒学ないし儒教と仏教や日本の先祖供養との関係についての考察は誠に興味深いものであるし、それとの関係で述べられる妖怪「うぶめ」についての新考察も実に楽しめるものであった。林羅山がそれほど重要な人物であったとは、と膝を叩いた次第である。
-
なお、本書でなされている、Martin Heideggerとその批判者達が行なってきた存在と存在者についての議論をミステリに応用する、といったようなことは、笠井潔が上述した本の中で既にやってしまったことなので、このこと自体はやや低めに評価されるべき事柄であろう。まあ、角度を変えてみるならば、「同じことの反復」なりその「超克」なりというのは、本書内でもさりげなく仄めかされている通りHeideggerの思想内における中心課題でもあった訳だし、本書における死や存在を巡る問題と儒教や祖先崇拝を巡る議論との絡ませ方は大変見事なものである、ということは述べておかなければならない。ついでにもう一つ、本書670ページに書かれている「むさかり絵馬」という語は、正しくは「むかさり絵馬」である。これは小さな「瑕」だけれど、山形県内でフィールド・ワークを行なってきた私にとってはかなり重要なことなので一応付記しておく。以上。(2003/08/20)